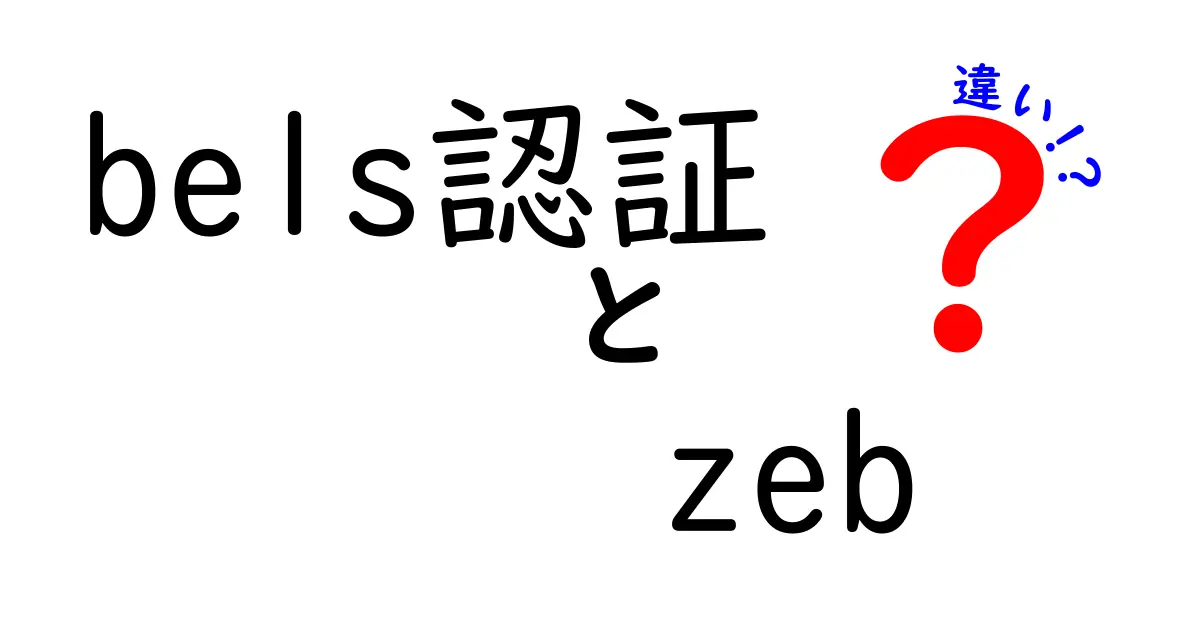

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:BELS認証とZEBの違いを正しく理解するための基礎知識
建物の省エネを評価する仕組みにはいろいろありますが、今回のメインは「BELS認証」と「ZEB」です。
この二つは似ているところもあるけれど、目的と評価の仕方が違います。
まず大事なのは、BELSは“エネルギーの使い方の数値を星で示すラベル”、ZEBは“使うエネルギーをできるだけ減らし、必要なら自分で作れるようにする設計思想”という点です。
それぞれどんな場面で使われるのか、誰が認証するのか、どんなデータが必要かを知ると、家や学校の建物を見ても何がすごいのかが分かります。
以下で、BELSとZEBの基本を順番に解説していきます。
・BELSは星の数で評価します。
・ZEBは設計と運用の両方を重視します。
この二つを混同せず、用途に合わせて理解することが大切です。
さて、具体的な違いを見ていきましょう。
BELS認証とは?どんな評価基準か
BELSはBuilding Energy Labeling Systemの略で、日本語では「建物省エネラベル」と訳されます。
認証を受ける建物は、設計時や改修後にエネルギーの消費量を計算して、1平方メートルあたりの年間エネルギー消費量を評価します。
評価の結果は星の数(例:1つ星、2つ星、最大5つ星)で表示され、星が多いほどエネルギー効率が良いと判断されます。
ポイントは「消費エネルギーの数字が見える化される」という点です。
この評価は、建物の用途や規模、地域の気候などによって基準値が変わります。
また、BELSは新築だけでなく改修後にも適用される場合があります。
この評価を取得することで、環境配慮のアピールや資金調達の際の優遇を受けやすくなることがあります。
中学生のみなさんには、エネルギーを“使わない”工夫が星として表れるイメージを持ってほしいです。
例えば、窓の断熱を良くして照明をLEDにする、そんな取り組みがBELSの星を上げる要因になります。
ZEBとは?どう設計・運用されるのか
ZEBはZero Energy Buildingの略で、日本語では「ゼロエネルギー建物」と呼ばれます。
意味は「建物が自分で使うエネルギーをできるだけ減らし、必要な分を再生可能エネルギーなどで賄う」という考え方です。
ZEBの特徴は、設計の初めから省エネを徹底し、実際に使う年間のエネルギー消費を小さく抑えることです。
しかしそれだけでなく、建物が発生する余剰エネルギー(太陽光発電などの余剰分)を電力網に返せるようにするなど、“自給自足”に近い仕組みも取り入れます。
評価は設計段階と実際の運用の両方を見ます。
ZEBの認証には階層があり、完全なゼロエネルギーを目指すもの、準備段階のものなど複数のレベルが存在します。
ZEBを達成するには、断熱・窓・照明・空調といった基本的な設備が高性能でなければなりません。
地域の気候条件や建物の使い方を考え、太陽光発電や地熱などの再生可能エネルギーを組み合わせるのが一般的です。
両者の違いを一言でまとめると?具体的な使い分け例
BELSはエネルギーの使い方を数字と星で可視化するラベルであり、建物の現状の性能を外部から評価・比較しやすいのが特徴です。
設計や改修の前後で比較しやすく、資金調達の際の補助金申請や入居者に対する説明材料として使われます。
ZEBは“ゼロエネルギーを目指す設計思想”と運用方針で、実際のエネルギー収支を年単位で0に近づけることを目標にします。
したがってZEBは建物の長期的な省エネ計画と太陽光発電などの発電設備を組み合わせた総合的な取り組みです。
使い分けの例としては、オフィスビルや学校では「まずBELSで現状の省エネ度を示し、入居者に説明する」。
新築や大規模改修で省エネを徹底したい場合は「ZEBを目指して設計・運用を計画する」という順序が現実的です。
このように、評価の“切り口”と“目標の高さ”が異なる二つの制度を、状況に合わせて使い分けるのがポイントです。
以下の表にも簡単にまとめておきます。
| 観点 | BELS認証 | ZEB |
|---|---|---|
| 目的 | エネルギー消費の可視化・評価 | 近ゼロエネルギーを目指す設計・運用 |
| 評価方法 | 定められた基準に対して消費量を計算・星付与 | 設計段階と実運用のエネルギー収支を総合判断 |
| 対象範囲 | 建物全体の省エネ性能 | 建物の設計思想・運用方針まで含む |
| 適用の時期 | 新築・改修後の評価が中心 | 設計段階から実運用まで長期的な取り組み |
まとめと日常生活への影響
私たちが建物を見るとき、BELSの星の数やZEBの考え方を知っていると、環境にやさしい選択をしやすくなります。
例えば新しい学校の建設計画を耳にするとき、BELSの星が高いかどうかだけでなく、ZEBを目指しているか、発電設備や断熱材の性能がどうかをチェックすると良い判断ができます。
日頃の暮らしにも影響があり、家の中の断熱や窓の選び方、照明の選択など、身近なところで省エネ意識が高まります。
もちろんコストやデザインの好みも大切ですが、将来のエネルギーコストを考えると省エネ投資の価値は大きいです。
この知識を友達と共有して、学校での省エネキャンペーンや家庭の電気代の見直しにも役立ててください。
最近の話題でいうと、BELSとZEBは“省エネの道具箱の中の違う道具”のようなものです。
BELSは星を見せて“今この建物はどれくらい省エネか”を一目で伝える看板、ZEBは設計から運用までを見直して“実際に消費を減らして自分で作るエネルギーを増やす”計画そのものです。
学校や家のリフォームを考えるとき、最初にBELSで現状を把握し、次にZEBを目指すと、現実的で実行力のある計画になります。
ただし、両方を同時に100%実現するにはコストと技術のバランスが必要です。
だからこそ、次の学校建設や自治体の省エネ計画では、まず現状把握→長期目標の順序で検討するのが現実的で賢い選択です。





















