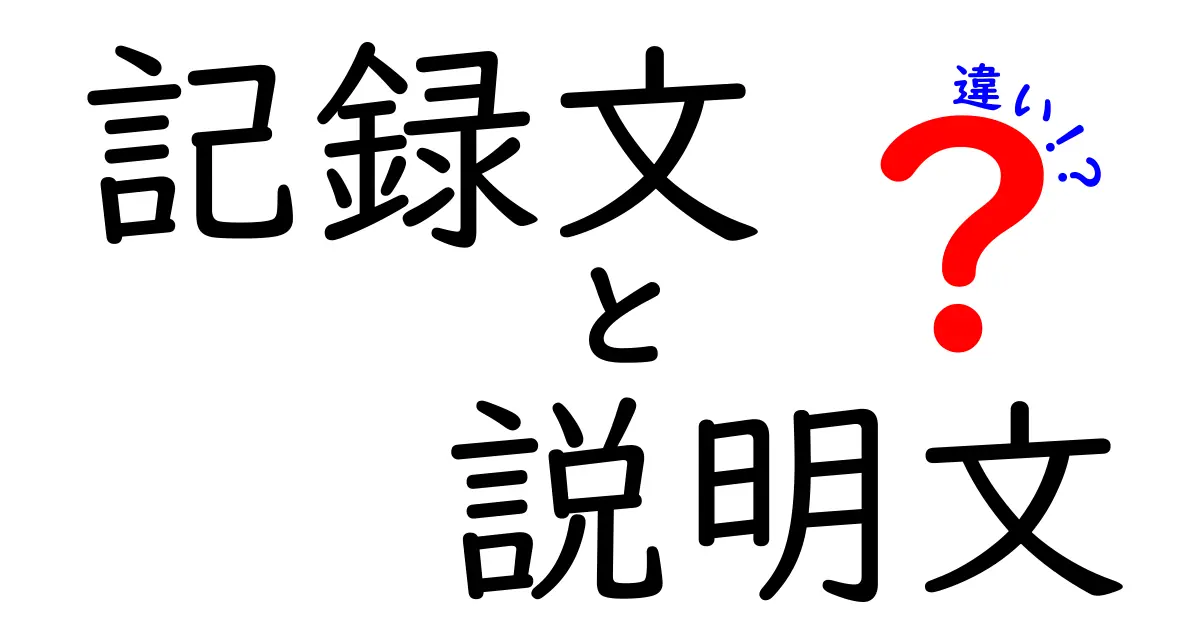

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
記録文と説明文の違いを正しく理解する
記録文と説明文は、情報を伝えるときの“見せ方”が違います。記録文は起きた出来事をそのまま時系列で記録することを目的としており、事実関係を変えずに書くと読者は後からでも誰が何をしたかを追えます。たとえば、学校の授業日誌、部活の練習記録、イベントの報告書などがこれにあたります。これらは主観を控えることが基本で、語り口はできるだけ客観的で、特定の意見や予測を挿入しません。文章の順序は「起こった順」「誰が」「何を」「いつ」「どこで」の順に並べるのが分かりやすいです。記録文では、日時・場所・関係者の名前を特定することが読者の混乱を防ぎ、後から読み返して状況を再現できるようにする工夫が大切です。次に説明文ですが、読者に「どうしてそうなるのか」を理解させることを目的とします。原因と結果、仕組み、手順、原理といった要素を、論理的な順序で組み立て、読者が現象の背後にある原理をつかめるように構成します。説明文では、主張を裏付ける根拠の提示順序が重要で、適切な接続語を使って因果関係をつなぎ、読み手の理解の道筋を作ります。さらに、説明文では例示の方法にも配慮します。適切な具体例は理解を深めますが、抽象的すぎる説明は避け、専門用語には短い定義を添えると読者が混乱しません。最後に、記録文と説明文を混同しないためのコツをひとつ挙げるとすれば、「最初に何を伝えたいのか」を明確化することです。これにより、同じ題材を扱っても、記録としての正確さと説明としての理解の両方をバランスよく保つことができ、読み手は混乱せずに情報を受け取れます。
本文の長さに気をつける理由は、読者の目の負担を減らすことと、要点を取りこぼさせないためです。
記録文の特徴
記録文の特徴は、まず「過去形を中心に用いて、事実を順番に並べる」点です。出来事が起きた日付、時刻、場所、関係者、何が起きたかを逐次記録することで、読者が後から再現できるようになります。次に「客観性を優先する」ことです。意見や評価は最小限または別の段落で明示します。語彙は具体的で、曖昧さを避け、読み手によって解釈が分かれない表現を選びます。さらに「因果関係の説明を避け、事実の列挙を重視する」ことが多いため、設問で「なぜそうなったのか」を問われても、必要であれば別に説明文を用意します。記録文を書くときには、情報の出典を示し、誤記を避けるために複数の情報源を確認する習慣をつけると良いです。最後に、段落分けと見出しの使い方にも配慮します。時間の流れを追いやすく、後から読み返して要点を拾いやすい構成を目指します。
説明文の特徴
説明文の特徴は、まず「どうしてそうなるのか」という問いに答えることを主体に構成されます。主題を提示し、続いて原因、しくみ、手順、例を順番に示し、読者が結論に納得できるように論理を積み上げます。語彙は一般的で専門用語を使う場合は要点を短く説明し、図解が役立つ場面では例を添えると理解が深まります。説明文は時に現在形を使い、普遍的な真理を伝えることが多いです。論理のつながりには接続語を活用し、「だから」「しかし」「一方で」「結果として」などを適切な位置に配置します。研究論文風の実用的な説明もあれば、日常の手順を説明する口語的な説明もあります。読者が自分で考える余地を残す場合は、結論を示す前に小さな仮説を提示する方法も有効です。
日常の文章での使い分けと練習のコツ
日常の文章での使い分けは、練習で自然に身につく力です。まずは目的をはっきりさせ、記録文なら“現場で起きた出来事を正確に伝える”こと、説明文なら“読者が理解できるように説明する”ことを最優先にします。次に構成を考えます。記録文は一般に「誰が・いつ・何を・どこで・どうしたか」を時系列で並べ、説明文は「主題→理由→結論」という筋道を意識します。実践練習として、日常生活の出来事を2つの形で書き分ける練習を続けると、違いが見えやすくなります。たとえば同じニュースの出来事を、まず記録文として1段落、次に説明文として別の段落で書くと、読者は情報の性質の違いを体感しやすくなります。読みやすさの工夫として、短い文と長い文を混ぜ、適切な場所に改行を入れること、そして要点を太字で示すことも役に立つでしょう。最後に、表現の幅を広げるために、同じ情報を複数の言い方で表す練習を繰り返すと、語彙力と構成力が同時に伸びます。
ねえ、さっきの話をもう少し深掘りしてみよう。記録文と説明文の違いを見ると、どちらを選ぶべきかの判断基準が見えてくるんだ。記録文は“その場の事実をそのまま伝える力”が最重要で、時間と場所、誰が何をしたかを正確に並べる練習をすると良い。説明文は“どうしてそうなるのか”を読者に納得させる論理構成が要になる。ここで大事なのは、同じ題材でも書き分けを意識すること。たとえば部活の報告をする場合、最初に“事実の列挙としての記録文”を書き、後から“原因と仕組みを解説する説明文”を追加する。そうすると、読者は情報の性質の違いを体感しやすくなる。





















