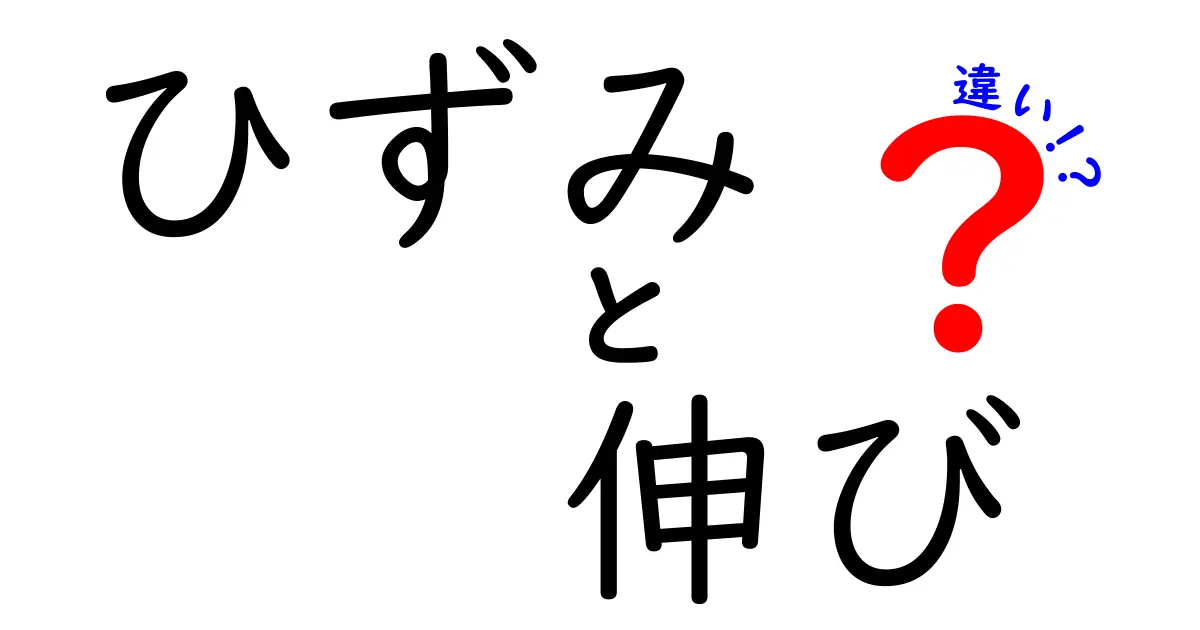

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ひずみと伸びとは何か?基本から理解しよう
皆さんは「ひずみ」と「伸び」という言葉を聞いたことがありますか?これらは物質の変形や性質を表す言葉で、特に材料や構造を学ぶときによく使われます。
伸びとは、物体の長さが元の長さからどれだけ増えたかを示す量です。例えばゴムを引っ張ったときに長くなる様子を思い浮かべてください。伸びは具体的な長さの変化を意味します。
一方、ひずみは、その伸びを元の長さで割った比率のことを指します。つまり、長さの変化を元の大きさに対して比べたもので、単位を持たない無次元の値です。これにより、同じ伸びでも元の大きさが違えばひずみは違ってきます。
このように、伸びは変化した長さそのものですが、ひずみはその変化を元の長さに対する比率で示しているのです。
ひずみと伸びの違いを具体例と表で学ぶ
ひずみと伸びの関係をもっと具体的に理解しましょう。
例えば、長さ1メートルの棒が5センチ(0.05メートル)伸びたとします。
このときの伸びは0.05メートルです。
ひずみは「伸び ÷ 元の長さ」なので、0.05 ÷ 1 = 0.05となります。これは5%のひずみがかかっていることを意味します。
別の棒が2メートルで、同じく0.05メートル伸びた場合、ひずみは0.05 ÷ 2 = 0.025となり、2.5%のひずみです。同じ伸びでも元の長さが違うため、ひずみは異なります。
この違いがあるため、ひずみは物質の変形を比較するときにとても役立ちます。
| 元の長さ | 伸び | ひずみ (伸び ÷ 元の長さ) |
|---|---|---|
| 1メートル | 0.05メートル | 0.05 (5%) |
| 2メートル | 0.05メートル | 0.025 (2.5%) |
| 0.5メートル | 0.05メートル | 0.1 (10%) |
このように、物のサイズの違いによって同じ伸びでもひずみは大きく変わることがわかります。
ひずみと伸びの違いを知ることの重要性
では、なぜひずみと伸びの違いを理解することが大切なのでしょうか?
物理や工学、特に建築や材料学では、物質がどれだけ変形するかを正確に測ることが必要です。
伸びだけを見ると、単純な長さの変化がわかりますが、それだけでは材料の「強さ」や「柔らかさ」、安全性を判断しにくいという問題があります。
そこにひずみの考え方が役立ちます。ひずみは元の長さによる変化の割合を示すため、異なるサイズの材料や構造物の変形を公平に比べられます。
また、ひずみは応力(物体にかかる力)がどのように負荷されているかを理解するのに欠かせません。
つまり、伸びは身近で理解しやすいけれど、物理の世界ではひずみを使うほうがより正確で役立つのです。
この違いを知ることで、科学や技術の勉強はもちろん、身の回りの物の性質もより深く理解できるようになります。
「ひずみ」という言葉、聞いたことはあっても実際どんな意味かはよくわからない人も多いですよね。実はこのひずみ、物理や材料の世界では物体の変形を比率で示すとても大切な指標なんです。例えばゴムを引っ張ったとき、その長さがどれだけ変わったか(伸び)は見えますが、ひずみはその伸びを元の長さで割ることで、その変形の大きさを数字の比率で表します。だから大きなものと小さなものでも変形の大きさを公平に比べることができます。日常生活ではあまり使わない言葉ですが、科学や工学の世界ではとても重要な考え方なんですよ。
次の記事: 溶接と溶着の違いって何?初心者でもわかる簡単解説! »





















