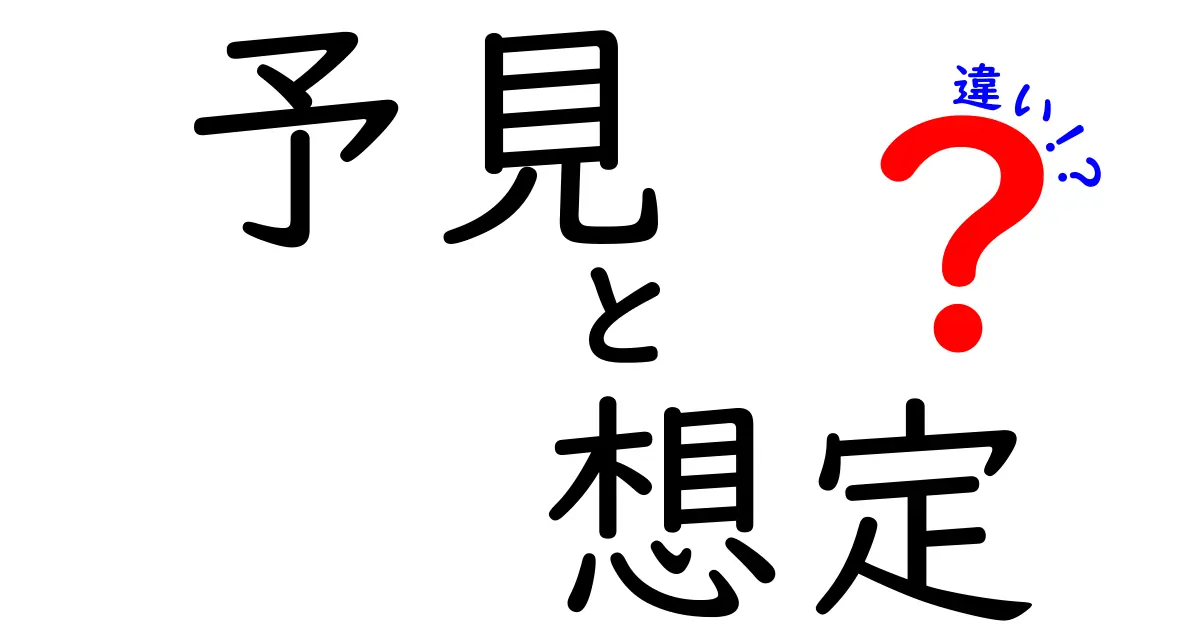

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
予見と想定の違いを理解する基礎
現代社会で情報はあふれていますが、その中から正しい判断を導くには、予見と想定の違いを知ることがとても大切です。
まず、予見とは、過去のデータや今ある情報をもとに、将来何が起こるかを見通す力のことを指します。天気予報や株価の動き、交通状況の変化など、証拠や根拠が伴うことが多く、確率の計算やシミュレーションが使われます。これに対して、想定は、まだ起こっていないことを自分の計画や前提で思い描くことです。実際のデータが不足している場合でも、仮説を立てて行動を組み立てますが、外部の検証が追いつくまで不確実性が残ります。
この2つの違いをはっきりさせると、危機管理や意思決定の際に「何を根拠に考えているのか」を自覚しやすくなります。証拠重視の予見は検証と更新が前提、一方で想定は前提の再検証を前提に柔軟に修正していくべきです。日常生活でも、物事を判断する前に「この予見はどのデータに基づくのか」「この想定はどの前提に立っているのか」を分けて考える習慣をつけると、失敗を減らすことができます。
この章では、予見と想定の違いを意識する理由を整理し、使い分けの基本的な考え方を身につけるためのポイントを整理します。これから紹介する例を自分の場面にあてはめて考えると、仲間内の意見の衝突を減らし、計画の実現性を高めることができます。
なお、予見と想定は相互補完的です。どちらか一方だけに偏ると、現実の変化に対応できなくなることがあります。柔軟に使い分けるコツは、まず「自分が何を予見しているのか」「何を想定しているのか」を言葉にして書き出すことです。これが判断力を高める第一歩になります。
実生活での使い分けの具体例と注意点
ここでは日常生活と仕事での具体的な使い分けを見ていきます。
・予見の例として、天気予報が示す雨の可能性を考え、傘を持って出かける計画を立てる場面が挙げられます。これは外部データを根拠にした判断であり、確率に基づく対応です。
・想定の例として、会議で新しいアイデアを発表する前提として「参加者はこの意見に賛成してくれるはずだ」という仮説を立てる場面が考えられます。これは自分の前提や経験に基づく判断で、実際の反応を見て仮説を修正します。
・グループ作業では、進捗が遅れるリスクを予見してスケジュールの余裕を取りつつ、予想外の質問や反対意見に備える想定を同時に用意しておくと安定します。
・安全対策を立てる場面では、予見としてデータに基づく被害の推定を行い、想定としてもし仮に状況が悪化したときの対応手順を複数準備します。ここでのポイントは、前提を明確にし、それを検証する仕組みを作ることです。
・学習の計画を立てるときには、将来の到達目標を予見として設定しますが、具体的な学習日程や教材の選択は想定として留保し、状況に応じて変更します。
このように、予見と想定を使い分けると、計画の現実性が高まり、柔軟性も保ちやすくなります。重要なのは、どの判断が予見に基づくか、どの判断が想定に基づくかを自分で認識することです。
最後に覚えておきたいのは、両者は相互補完的だという点です。予見だけに頼るとデータが外れたときに大きなショックを受け、想定だけでは現実の変化に追いつけません。実用的な方法としては、定期的に根拠を見直し、データが更新されたら予見と想定を同時にアップデートする癖をつけることです。これが賢い判断への第一歩になります。
友達Aと友達Bがカフェで雑談します。Aは『予見って、データが揃っていればほぼ当たるよね』と言います。Bは『でも想定も大事。外部データがなくても、計画を動かす力になる』と返します。Aは『確率が高い予見で動こう』と提案しますが、Bは『ただし前提を疑って更新することが必要だよ』とアドバイス。二人は、予見と想定を使い分けることで意思決定の幅を広げられると納得します。結論は、予見を根拠に、想定を前提として、それぞれを定期的に検証・更新すること。まさに学習と成長のコツです。





















