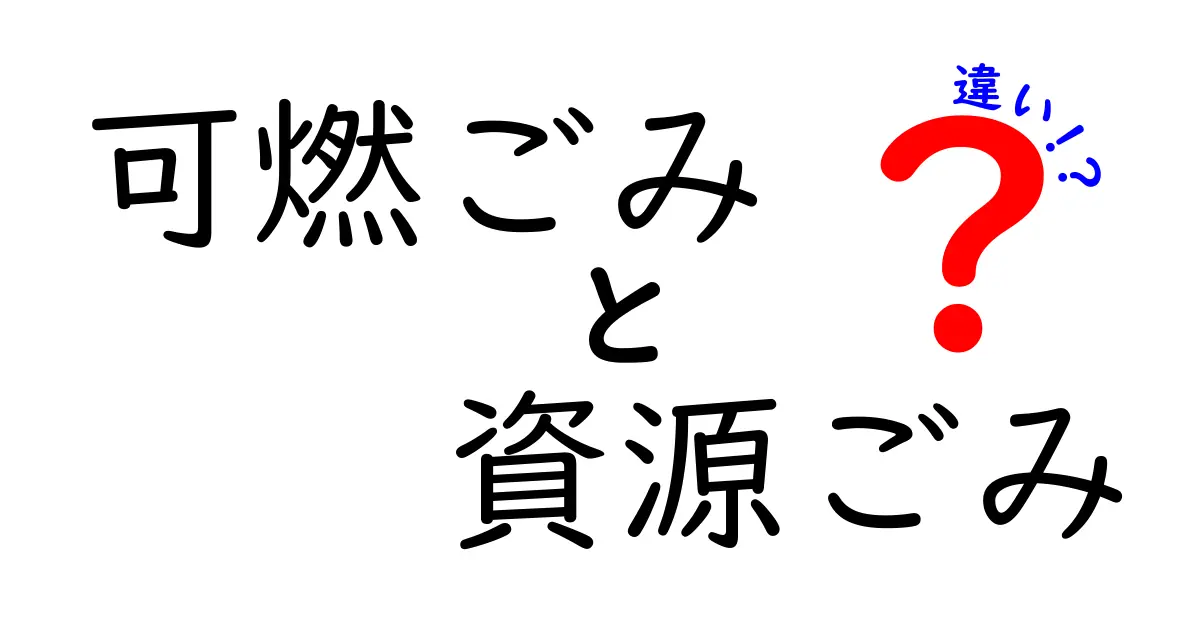

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
可燃ごみと資源ごみの違いを正しく理解するための基礎知識
皆さんが日常で出すごみには大きく分けて二つの仲間があります。可燃ごみと資源ごみです。可燃ごみはおもに焼却して処理され、食品の残りや紙くず、布や木材、壊れたおもちゃなど、燃やせるものをまとめて出します。地域のルールによっては生ごみと紙を分ける場合もあります。
一方、資源ごみは再利用できる材料として回収され、リサイクルの工程を経て新しい製品になります。具体的にはペットボトルの容器や缶、古紙、段ボール、プラスチック容器などが該当します。
この二つは分類が大きく異なるため、分別のルールを間違えるとリサイクルの機会を逃してしまいます。
地域ごとに分け方の細かなルールは異なりますが、基本としては「燃えるかどうか」「再利用できるかどうか」「出し方の規則」を軸に考えると覚えやすいです。
この違いを理解すると、家庭での動作が楽になり、環境にも優しくなります。
ですので、まずは自分の自治体の分別表を手元に置き、疑問があれば公式サイトや窓口で確認しましょう。
家庭での分別の実践とポイント
日常の分別実践においては基本を押さえることが大切です。まずは「燃えるかどうか」「再利用できるか」で分ける癖をつけましょう。
家庭では生ごみや食品のくず、布類、紙くずなどは可燃ごみへ。生乾きの状態を避け、こまめに密閉して出すのがコツです。
反対にペットボトルや缶、紙、段ボールなどは資源ごみとして出します。ボトルはキャップを外し、容器はすすいで水分を切り、紙は乾いた状態でまとめると回収がスムーズです。地域ごとに細かなルールがあるので、公式情報をチェックして最新の出し方を把握しましょう。
資源ごみの回収日や出し方は自治体によって差があります。回収のタイミングを守ることはゴミ減量だけでなく、回収作業の効率化にもつながります。
また分別は地域によって違う点を常に意識してください。新しいルールが出ることもあるので、自治体の広報やサイトの更新を習慣にするとよいです。
ここまでのポイントをまとめると、洗浄の基本、分別の基準、地域ごとのルールの三つです。これらを日々意識するだけで、資源のムダを減らし地球にやさしい生活へ近づきます。
次のステップとして、表を使って具体的な分類を整理してみましょう。
資源ごみをめぐる雑談風の小話です。友だちのAが「資源ごみって結局何が再利用になるの?」と聞くと、友だちBは「地域や工場の設備次第だよ。たとえばPETボトルは新しいボトルや繊維になることが多いし、缶は鉄やアルミとして生まれ変わる。紙は再生紙に生まれ変わることが多いね」と言います。私は子どものころ、資源ごみを出すとき中身をきれいにしておくのが大事だと教わりました。油分が多い食品の容器は洗いすぎなくても回収される場合がありますが、洗浄は回収の効率を高める基本です。結局、私たちのちょっとした心がけが新しい製品づくりを支えるのです。たとえば、ペットボトルはすすいで乾かし、キャップを外すという小さな手間が、リサイクルの場をよりスムーズにします。こうした日々の小さな工夫が、未来の地球を守る大きな力になると信じています。





















