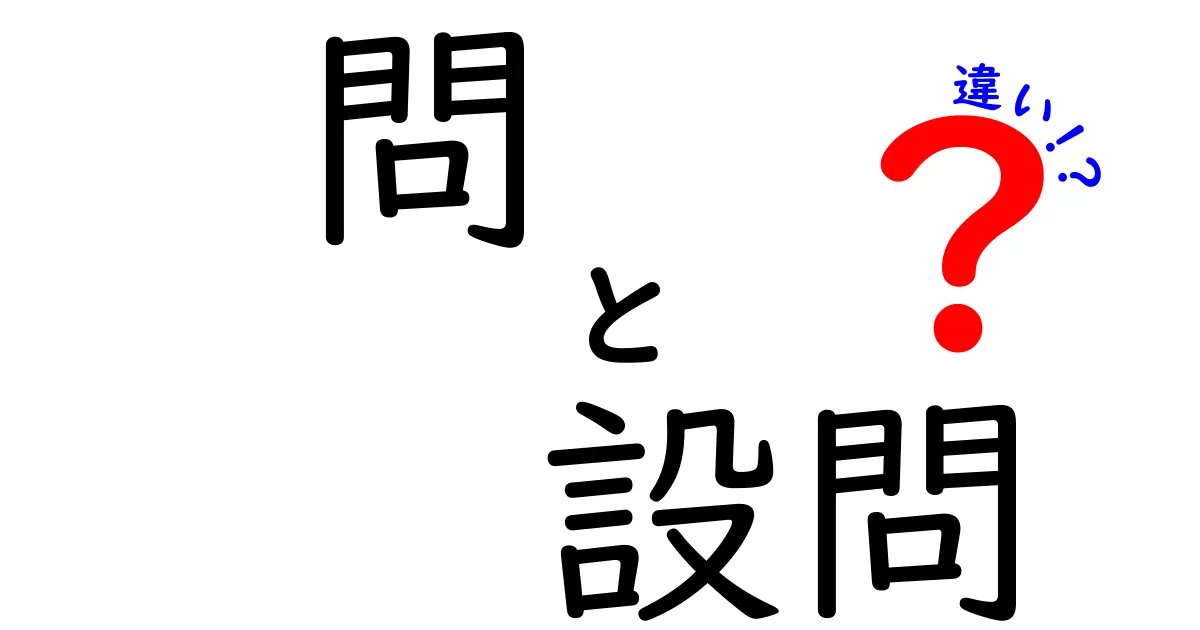

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
問と設問と違いの基本を知ろう
このテーマは日常の文章作成や試験対策で頻繁に現れる内容です。まず覚えておきたいのは「問」「設問」「違い」という3つの言葉が、それぞれ別の意味と用途を持つという点です。「問」は一般的な質問や問題を指す広い概念で、話題を引き出すきっかけや議論の入口にもなります。一方で「設問」はテストや課題の中の具体的な質問項目を指す専門用語です。設問は問題の性質や難易度、求められる答えの形式などをはっきり規定しており、受け手はそれに沿って解答を作成します。これらの違いを把握しておくと、文章を書くときの表現選びや、試験での解答の組み立て方がスムーズになります。
日常生活の中でも、ニュース記事の段落、宿題の指示、インタビューの質問など、さまざまな場面で「問」と「設問」の使い方が現れます。たとえば、友だちに質問する時には「問」という字を使い、試験の問題へ解答を書く場面では「設問」という語が自然です。ここで重要なのは、受け手が何を答えるべきかを明示する点です。
この理解は、語彙力を高めるだけでなく、文章を読むときの焦点を定める助けにもなります。
つまり、問と設問の違いを知ることは、言葉の使い分けだけでなく、思考の整理にも役立つのです。
問とは何かを理解する
問とは一般的な質問や問題の総称です。誰かに情報を求めるときや意見を引き出したいときに使われることが多く、話者の目的は“相手に答えを返してもらうこと”です。具体的には、日常会話での質問文や、新聞記事の見出しの根幹となる疑問文など、幅広い場面で現れます。
この「問」は難易度が低くても高くても構いません。抽象的な問いも具体的な問いも、問いの基本形を共有している点が特徴です。以下の例を見てみましょう。
例1: 「この本の著者は誰ですか?」
例2: 「地球温暖化を防ぐには何をすべきですか?」
このように、問は答えを求める意図を明確に表します。
設問とは何かを理解する
設問はテストや課題の中の具体的な質問項目を指す専門用語です。設問は「何をどう答えるべきか」をはっきり指示します。採点の基準や答えの形式、字数制限、図表の有無など、解答の具体性を決める要素が設問には含まれます。たとえば数学の設問では「xの値を求めよ」という形で解くべき手順が決まっています。国語の読解設問では「本文の要点を3つ挙げよ」など、求められる情報が定められています。設問は受け手に対して“この場で、こういう答えを出してほしい”という期待を明示する道具です。
設問の特徴として、番号付きの項目で構成され、解答欄の記入形式や必要条件が明記されています。読解問題の設問なら「本文中の◯◯を指す語を選べ」など、解答の根拠となる情報を特定させる設計になっています。
違いを使い分けるコツ
日常の文章や会話では「問」や「問い」を使い分けるのが自然です。一方でテストや課題の場面では「設問」を用いるのが適切です。使い分けのコツは場面を意識すること。日常的な情報交換や議論では相手の理解を促す目的の「問」を選ぶと良いでしょう。反対に、学校の宿題や試験の案内文、解答の手続きが決まっている状況では「設問」を使い、指示に従って解答を組み立てます。
この区別を意識するだけで、文章の読み手に伝わる意味が格段にクリアになります。
このように、場面に応じた適切な語を選ぶことが、相手に伝わりやすい文を作る第一歩です。さらに深く理解したい人には、実際の文章例を比較してみると良いでしょう。次のポイントを覚えておくと、語感の違いがよりはっきり分かります。1) 設問には必ず解答の対象がある。2) 問は会話の入口としての役割が大きい。3) どちらを使っても意味が伝わる場合でも、場面と目的に合わせて選ぶと読み手に優しい文章になる。これらを踏まえれば、日常のコミュニケーションから学習教材まで、さまざまな場面で適切な言葉を選べるようになります。
友だちと勉強中、私はこう言いました。「ねえ、なんでこの問題には『問』って言うんだろう?ただの質問のようだけど、設問のように解答を決める指示があるわけじゃない。設問っていうと、なんとなく“ここをこう答えろ”って紙に書かれている感じがするよね。私たちがテストで見かけるのは、まさに設問の形をした命令文。だから、日常の会話と試験の両方を上手にこなすには、この二つの違いを知っておくことが大事だよ。"





















