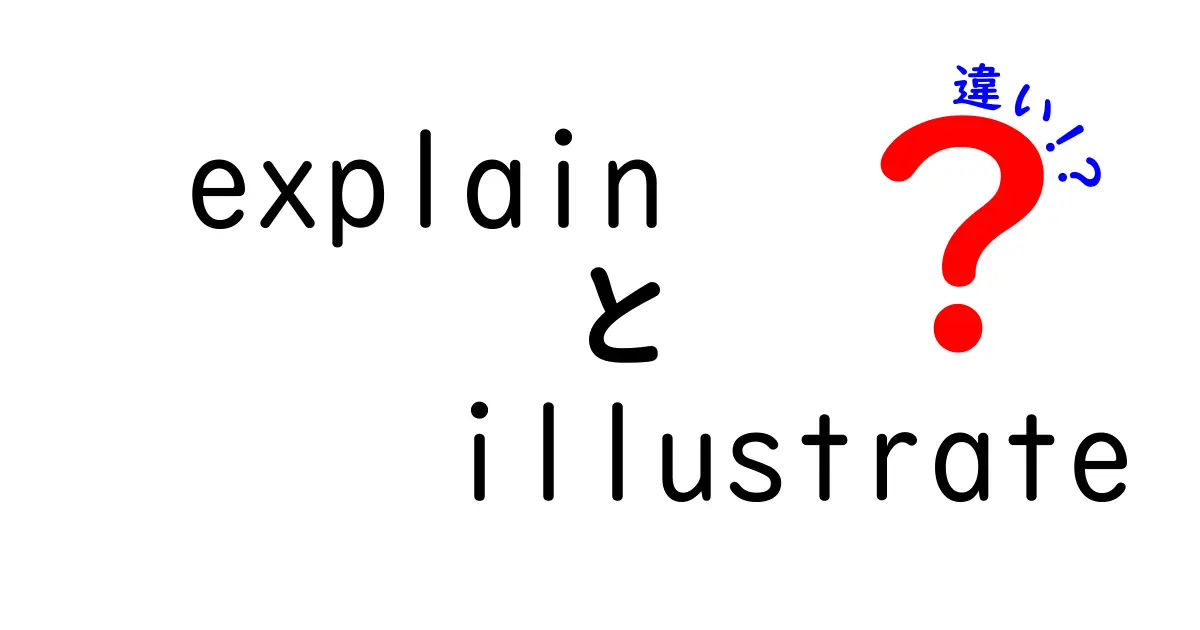

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
explainとillustrateの違いを完全解説!今すぐ使い分けをマスターする実践ガイド
このガイドでは英語の explain と illustrate の違いを、学校の授業や日常の文章作成で迷わず使い分けられるように詳しく解説します。
まずは基本の意味から、具体的な使い方、誤解されやすいポイント、そして実際の文例までひとつずつ丁寧に解説します。
本文は中学生にもわかりやすい言葉で進めます。
重要なポイントは「explain は原因・仕組み・根拠を明らかにする説明」、「illustrate はイメージ・例・図解で理解を深める説明」という二つの軸です。これを理解すれば、読者にとって分かりやすい文章づくりがぐんと楽になります。
また、後半には使い分けのコツを実用的な表と具体的な文例でまとめています。
読み終わるころには、あなたの文章が「理由の説明」から「イメージの共有」へと広がるのを実感できるでしょう。
基本的な意味の違いを理解する
まず押さえておきたいのは explain と illustrate の基本的な役割の違いです。
explain は物事の原因・仕組み・論理的な理由を明らかにすることを目的とします。つまり読者に“なぜそうなのか”を理解させるための説明です。例えば科学の授業で「この現象が起こる理由は何か」を説明する時には explain を使います。
一方で illustrate は言葉だけでは伝わりにくい概念を“イメージ化する”ことを目的とします。図・例・比喩・比喩的な表現などを用いて、読者の頭の中に視覚的なイメージを作るのが illustrate です。例えば数学の概念を説明する時に、図を見せてその概念を視覚的に結びつける場合には illustrate が適しています。
この二つの違いを理解しておくと、文章の目的に合わせて適切な語を選べるようになります。なお、日常の文章では explain 的な説明の後に illustrate の要素を加えると、読み手の理解がより深まります。
強調したいポイントは explain は論理と因果の説明、illustrate はイメージと例の提示 という二つの柱です。これを意識するだけで、説得力と伝わりやすさが大きく変わります。
表を見ても分かるように、explain は論理的な筋道を示す役割、illustrate は心に浮かぶイメージを作る役割があります。これらを上手に組み合わせることで、説明文章の質を高めることができます。なお、現実の文章ではしばしば two-step の構成が有効です。まず explain で根拠を示し、その後に illustrate で実例や図・比喩を用いて理解を深めると、読み手の理解度が一段階上がります。
使い方のコツと場面別の例
次に、具体的な使い方のコツを場面別に紹介します。
コツその1:説明の前に目的を決める。読み手に何を理解してほしいのかを最初に決め、その目的に合わせて explain と illustrate を選ぶ。
コツその2:説明の順序を意識する。まず explain で全体像を提示し、続けて illustrate で局所のイメージを補足する。
コツその3:図や例を活用する。数字だけでなく、図や身近な例を組み合わせると理解が深まる。
コツその4:語彙の使い分けを練習する。日常的には explain の語が多く、教育的な文章やプレゼンでは illustrate の要素を多く取り入れると良い。
実際の文例を見てみましょう。
1) explain を使う例: この薬が効く理由は、体内での反応がpHの変化に左右されるからです。
2) illustrate を使う例: 粒子の動きを図で描くと、速度が上がるときの軌跡がわかりやすくなる。
3) explain と illustrate を組み合わせた例: まず原因を explain し、次にその原因を図で illustrate して視覚的に理解させる。
このように、場面に応じて explain と illustrate を適切に組み合わせることが、伝わりやすい説明のコツです。
最後に、よくある誤解として「説明と図解は同じものだ」という考えがありますが、実際には説明と図解は異なる役割を持ちます。図は補助的な素材であり、主役はあくまで説明の中身です。正しく使い分けることで、読み手の理解を大きく高めることができます。
この章のポイントは使い分けを意識して文章設計を行うことです。読者のニーズに合わせて explain と illustrate を適切に組み合わせれば、難解な内容でも分かりやすく伝えることができます。
今日は illustrate という語を深掘りします。 illustrate は単なる“絵を描く”という意味だけでなく、言葉の意味をより生き生きと伝える“図解・例示の技”なんだとお知らせしたいです。友達と話しているとき、難しい話題を説明する際に、ただ説明するだけよりも、絵や身近な例を一緒に見せる方が、相手の頭の中にイメージが立ち上がりやすいですよね。 illustrate の力を使いこなすと、伝わり方がぐんと違います。絵や図が苦手でも、身近な例を増やす練習をすればすぐに上達します。





















