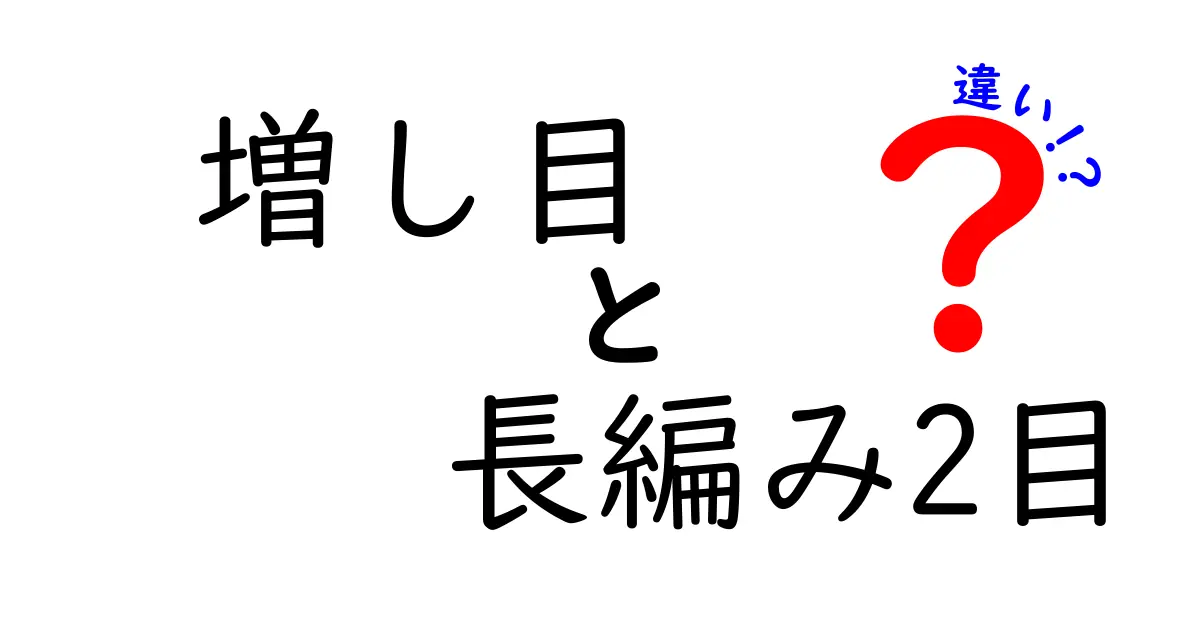

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
増し目と長編み2目の違いを徹底解説
ここでは、 crochetの初心者さんにも分かりやすく、増し目と長編み2目の違いを丁寧に解説します。
最初に結論を伝えると、増し目は形を広げるための基本的な操作で、どの段でも複数の目を作ることができます。一方、長編み2目は、同じ目に長編みを2回編むテクニックで、1目の代わりに2目を作る方法です。この二つは目的と手順が異なるため、用途に応じて使い分けることが大切です。以下で、用語の意味、例、作り方の違い、注意点、そして実際の練習方法を順を追って説明します。
この記事を読めば、増し目と長編み2目の違いがはっきり分かり、パターンに迷わず取り組めるようになります。
セクション1:基本用語の違いを知ろう
増し目とは、編み地の形を広げたり、先へ進むときに「新しい目を追加」する行為のことです。段の端や中央、または模様の切れ目で、1目以上を追加することが多く、帽子のつばを広げる、スカーフの輪郭を広くする、セーターの袖山を作るなど、さまざまな場面で使われます。増し目にはいくつかの基本パターンがあり、1目を2目に増やす場合と、2目ずつ追加していく場合があります。
ここで大切なのは、増し目をする場所と回数をPattern(パターン)に合わせて決めることです。間違えて同じ場所ばかり増やしてしまうと、編み地が波打ったり、形が崩れたりします。初心者のうちは、まずは比較的安定した模様の中で練習し、1段で2〜4目程度の増し目に慣れていくと良いでしょう。
また、長編み2目は別の技法です。長編みは1目の基点から編む基本の長さのかたまりで、長編み2目は同じ基点の位置に対して、同じ刺し方で2回長編みを編むことを指します。これにより、同じ位置に2つの長編みが並び、密度が少し変化します。増し目と長編み2目は、いずれも編み地の形状や密度を操る“設計の道具”ですが、役割が異なる点を最初に理解しておくことが、あとで混乱しないコツです。
セクション2:具体的な作り方の違いを実践で比較
まず、増し目の基本的なやり方を見てみましょう。段の途中で増やしたい場合、増やしたい目の前の目に対して、同じ目の位置に新しい目を追加します。たとえば「1目増やす」場面では、2回目の針の動作を同じ場所で行い、1目の代わりに2目を作るイメージです。増し目は段の終わりだけでなく、模様の変化したい場所でも行われます。
次に、長編み2目の作り方です。1つの目に対して、同じ刺し方の長編みを2回編みます。これを1つの基点として、2つの新しい目を作ることで、1目増やすのと似ていますが、増やし方の意味が少し異なります。長編み2目は、主に密度の調整に使われ、段の風合いを変えたいときに有効です。実際の手順のコツは、同じ目に対して2回連続で同じ刺し方を行うこと、2回目の長編みを編む前に針をしっかり引き抜かず、糸のテンポをそろえることです。
ここで、同じ段で増し目と長編み2目を組み合わせる応用例を挙げます。例えば、帽子の縁では増し目を使って輪郭を広げ、次の段の頭の方で長編み2目を使って密度を少し落ち着かせる、という組み合わせです。このように、増し目と長編み2目は、用途に合わせて順序良く使い分けると、形状と風合いを自由にコントロールできます。
実践する際の注意点としては、増し目は「どこで」「何回」増やすかをPatternに沿って守ること、長編み2目は「同じ場所に2回編む」ことを忘れず、編み目の間隔が崩れないように均等に編むことです。初心者のうちは、両者を同じ段で混ぜすぎず、まずは一方だけに集中して手法を身につけるのが安全です。
以下の表は、増し目と長編み2目の基本的な違いを要点だけ整理したものです。
この表を覚えておくと、パターンの指示を読んだときに「次は何をすればよいのか」がすぐ分かります。
さらに、実際の作品での使い分けを体験すると理解が深まります。
練習のコツとしては、同じ編み目の位置で増し目と長編み2目を順番に試してみることです。段を越えて編み進めるとき、形がどう変わるかを手で感じ取りながら進むと、記憶にも残りやすくなります。
以上のポイントを押さえれば、増し目と長編み2目の使い分けが自然に身についていきます。
セクション3:似た用語との混同を避けるコツ
crochetには似た言葉がいくつか登場します。例えば、増し目と似た言葉としてすじ目や細編みの増し目などがあります。これらを混同すると、Patternの意味が崩れて作品の形が崩れます。混同を避けるコツは、用語の定義を紙に一度書き出して、使う場面を場面ごとにメモしておくことです。
また、指示を読むときは、段の開始地点と速度、針の号数、糸の種類を意識して読み解くと、誤解が減ります。最初は、基本の用語だけを使ってPatternを追い、慣れてきたら応用的な表現へと移ると良いでしょう。
他にも、動画やイラストつきの解説で視覚的に確認する方法を組み合わせると、理解がぐっと深まります。色や糸の太さが変わると、同じ技法でも編み地の見え方が変わる点も覚えておくと役に立ちます。
セクション4:練習用ミニ課題と今すぐ作れる表
ここまでの知識を実践で確かめるためのミニ課題を用意しました。まずは増し目だけを使った小さなサンプルを作り、次に長編み2目だけを使って同じサイズのサンプルを作ります。これを比較することで、形の違いと手触りの違いを体感できます。以下の表は、課題の要点をまとめたものです。
| 課題名 | 目標 | ポイント |
|---|---|---|
| 増し目サンプル | 1段あたり2〜4目の増し目を体感 | 増やす場所を均等に、形が崩れないように |
| 長編み2目サンプル | 同じ目に長編みを2回編んでみる | 2回編むことで密度の変化を感じる |
この課題をこなすだけでも、増し目と長編み2目の違いが体感としてつかめます。
難しく感じる場合は、糸の太さを変えず、手元の動作だけをゆっくり繰り返すと良いでしょう。練習を重ねるほど、Patternを読む力と、手の動きの連携が自然になっていきます。
放課後の編み物クラブで、先生が『増し目は形を整える道具、長編み2目は密度を調整する道具だよ』と教えてくれた日のことを覚えています。その言葉を胸に、私は増し目と長編み2目を分けて練習することを始めました。最初はどちらを使えばよいか分からず戸惑いましたが、手元の糸の太さや編み方のリズム、作品の仕上がりを想像しながら試していくうちに、違いが自然とわかるようになりました。今では模様作りの幅が広がり、難しいパターンにも挑戦できるようになりました。





















