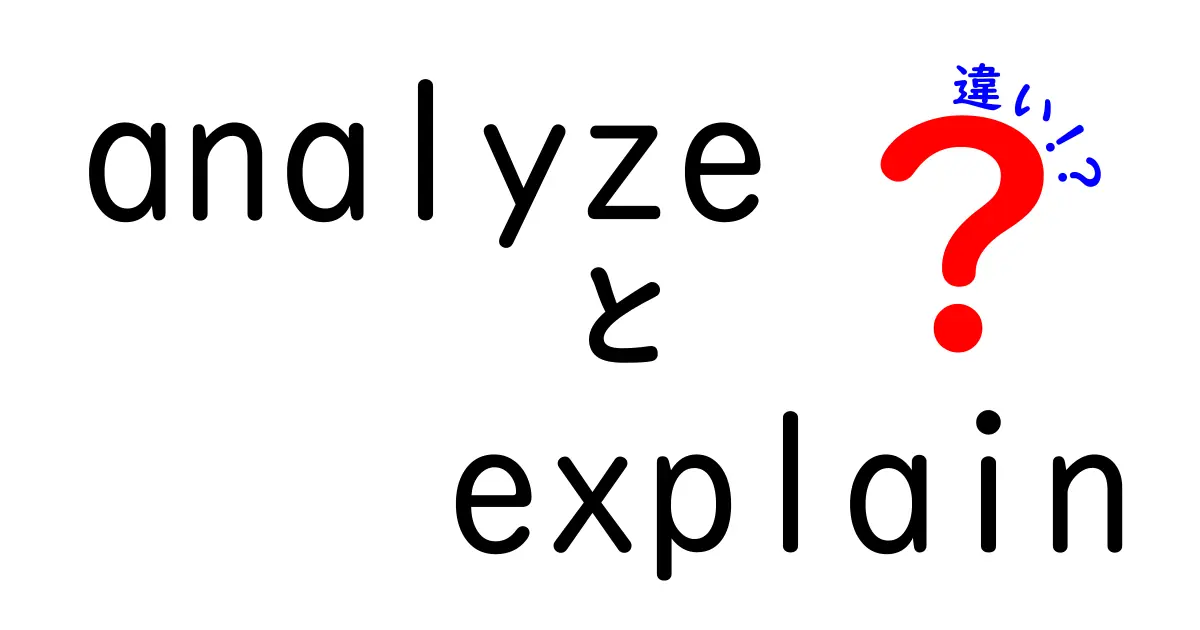

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
analyzeとexplainの違いを理解するための基本
「analyze」と「explain」は、似ているようで実は目的や使い方が異なる英語の動詞です。日本語に訳すとどちらも「説明する」に近い場面がありますが、英語圏の使い方には大きなズレが生まれやすいポイントがあります。analyze は物事を構成要素に分解し、それぞれの要因や関係性を調べる作業を指します。explain は分解した結果を、読み手や聞き手が納得できるように順序立てて伝える行為です。
この2つの動詞の違いを意識するだけで、学校の課題やレポート、プレゼンテーションの質がぐっと上がります。
具体的には分析は現象のしくみを「見える化」する作業であり、説明はその成果を「伝えること」に焦点があります。分析は問いかけの方法であり、説明は回答の伝え方です。したがって分析を先に行い、そこから得られた結論を説明へとつなげるのが、伝わる文章づくりの基本となります。
要点は目的と順序です。分析の目的は内部構造の理解、説明の目的は外部への理解促進です。
日常の場面での使い分けを少し詳しく見てみましょう。学校の授業ではデータや現象を分析して結論を導くことが多く、説明はその結論を友達や家族にわかりやすく伝える作業になります。ニュース記事や研究報告では、分析で得た根拠を説明することで信頼性を高めます。つまり分析と説明は、知識を深める段階と伝える段階の、別々の役割を果たす二つの技法なのです。
この順序の理解が、論理的で説得力のある文章づくりの第一歩です。
analyzeの使い方と具体例
analyze は対象を X を分析する、Y を分析する のように使います。語法の基本は 主語 + analyze + 目的語 の形です。例としては「データを分析する」「現象の原因を分析する」などです。分析を行う際のポイントは、全体を一度に見ようとせず、まずはパーツに分解して一つ一つの要素を確認することです。こうすることで、関係性や因果の流れが見えやすくなります。日常の場面でも、問題の本質を見つけるためにデータを集め、仮説を立て、検証するという手順を踏みます。
分析の過程は、情報の「集め方」「分け方」「結びつけ方」が問われます。たとえばスポーツの試合の分析では、選手の動き、得点のパターン、相手の戦術などをパーツごとに見ていき、どの要因が勝敗に影響したかを探ります。
さらに日常語としての使い方も見ておきましょう。英語の表現としては「to analyze data」「to analyze a situation」などの形が基本です。ここでの注意点は、分析の目的を明確にすることです。「何を知りたいのか」「どの結論を導きたいのか」を最初に決めてから分析を進めると、途中で迷子になりません。分析は手順がはっきりしているほどスムーズに進み、結論の説得力が増します。
分析の実践例をもう一つ挙げます。学校の社会科でニュース記事を分析するとき、まず事実関係を列挙し、次に原因と結果を因果関係で結び、最後に結論をまとめる。この順序で作業すると、読者が納得しやすい文章になります。最後に、表現の工夫として 結論を先に示してから理由を説明する構成 や、データの根拠を引用する際の出典の提示を忘れないことが大切です。
explainの使い方と具体例
explain は「なぜそうなるのか」「どうしてそういう結果になるのか」を伝えるときに使います。基本の形は 主語 + explain + 理由/原因/背景 の組み合わせです。例えば「この結果はなぜ起きたのかを説明する」「彼の意図を詳しく説明してください」などです。説明を作るときのコツは、相手の立場を想定して背景情報を順序立てて提示することです。まず事実を提示し、次に理由や根拠を並べ、最後に結論をまとめると、聞き手は内容を追いやすくなります。
日常的な場面では、友人に「どうしてそう考えるのか」を説明する際にも explain を使います。説明のポイントは 要点を短く整理し、例や比喩を用いて分かりやすく伝えること です。文章全体の構成を意識すると、難しい話題でも誰にでも伝わる説明になります。
説明の技法にはいくつかの型があります。例えば新しい情報を伝えるときは「背景 → 事実 → 理由 → 例 → 結論」という順序が役立ちます。教育現場では、子どもが混乱しやすいポイントをあらかじめ拾い上げ、それを克服する道筋を示すのが効果的です。具体例としては、科学の授業で「何が起こっているのか」という事実を提示し、次に「なぜそれが起きるのか」という原因、そして「どうすれば解決できるのか」という提案を順番に説明します。
説得力を高めるには、出典とデータを明示し、専門用語を必要最小限に抑えることが大切です。
実践的な活用場面として、レポートやプレゼンテーションでの説明を想定します。まず結論を明確に伝え、次に根拠となるデータや事実を示します。最後に要点を簡潔にまとめ、聞き手が持つ疑問を先回りして答えると、説得力が格段に上がります。
explain は伝える技術、analyze は理解する技術という二本柱のうちのもう一方です。
友だちのアヤとソウタがカフェで英語の analyze と explain について雑談します。アヤは数字のデータをいじるのが得意で、ソウタは人に伝える話し方が得意。二人はまず examine の違いから話を始め、次に実際の場面でどう使い分ければ伝わりやすいかを、実例を交えながら深掘りします。会話は自然な日常語で進み、途中でお互いの誤解を指摘しながら正解に近づいていく温かい雰囲気です。





















