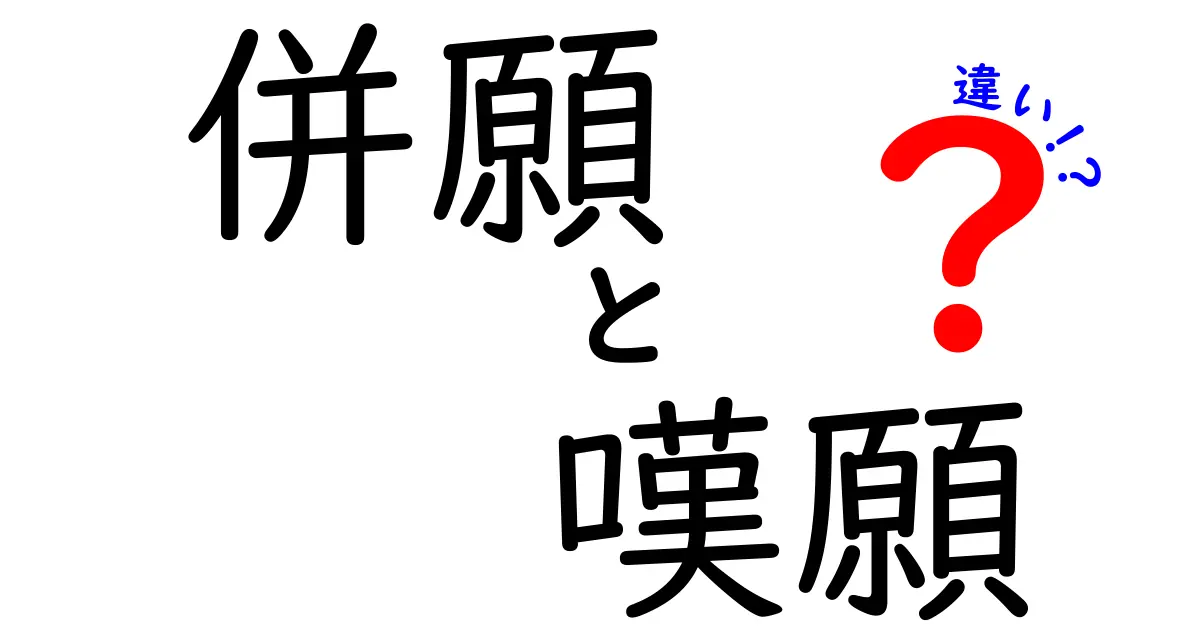

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
併願と嘆願の基本を理解する
ここではまず、併願と嘆願という2つの言葉が何を意味するのかを整理します。
併願とは、複数の学校や団体に同時に応募することを指します。受験期には、志望校の可能性を広げるために複数の選択肢を同時に進めるのが一般的です。手元のスケジュール、出願書類、受験料、締切日などをひとつひとつ整理して、無理なく回すことが大切です。
一方の嘆願とは、学校側へ「特別な配慮をください」と正式に頼む行為です。正当な理由がある場合に限り、事情を丁寧に説明して認めてもらえることがあります。嘆願は決して日常的な対応ではなく、理由の真実性と提出書類の整合性が求められます。
この2つは目的も性質も大きく異なります。併願はチャンスを増やす実務的な戦略、嘆願は特別な事情を伝える正当な依頼という理解で覚えておくと混乱が減ります。
これらを混同して用いると、信頼性が低下したり、結果として自分の希望が叶いにくくなることがあります。よって、まずは自分の現状と目的をはっきりさせ、各制度の適用範囲と締切を丁寧に確認することが大切です。
以下では、併願の実務と嘆願の実務、それぞれの使い分けのポイントを、実践的な観点から詳しく解説します。
併願の実務ポイント
併願を実際に活用するには、計画性と情報の整理が命です。まず志望校を現実的な順に3〜5校程度に絞り、各校の募集要項を比較します。
・願書提出の締切日をカレンダーにマーク
・出願に必要な書類(成績証明、推薦状、写真、受験料など)の準備を早めに開始
・模試の結果や内申点を踏まえ、現状の偏差値と志望校の難易度のバランスを取る
・受験日程を重ならせず、体調管理の計画も立てる
・志望動機を各学校に合わせて微調整する
併願の目的は「第一志望以外の選択肢を確保すること」です。
このため、出願書類の揃え方、提出期限の厳守、費用計画を特に重視します。出願料は学校ごとに異なる場合が多く、予算配分を先に決めておくと安心です。
さらに、併願を組む際には、学力以外の要素も考えます。例えば、通学の便、学費の支払い体制、校風、部活動の充実度など、実際の生活と学習の両方を見据えることが大切です。
併願は「準備の量とスケジュール管理」が勝負です。計画表を作り、各校の提出書類を早めに発送することで、焦りやミスを減らすことができます。失敗を恐れず、締切前の最終確認を怠らないことが大切です。
嘆願の実務ポイント
嘆願を出す場合は、まず自分の状況を客観的に整理します。嘆願は、単に「お願いすれば受かる」というものではなく、正当な理由を具体的に証明することが前提です。嘆願の流れは以下のようになります。
1) 嘆願の必要性を自分の言葉で明確化する。
2) 客観的な証拠を集める。例えば、医療の事情、家族の看護負担、学校側の募集条件との整合性など。
3) 公式の提出先・窓口を確認する。
4) 書類の体裁を整え、事実関係を丁寧に説明する。
5) 提出期限を厳守する。
嘆願書は感情に訴えるだけではなく、事実関係の証明と適切な理由付けが重要です。提出時には、添付資料の整合性にも注意します。
また、嘆願が必ず通るわけではない点を理解しておくことが大切です。審査には学校側のルールや他の受験生との比較が絡み、結果は様々です。
嘆願を考えるときは、 substitute 代替案も同時に用意しておくと安心です。
嘆願はあくまで「最終手段」として位置づけ、通常は併願の準備と並行して慎重に検討します。
併願と嘆願をどう使い分けるか
併願は「機会を最大化する通常の手段」として真っ先に考えるべきです。第一志望校が難しくても、他の学校を受けることで合格の可能性が高まります。嘆願は「特別な事情があり、当然に認められるべきと判断される場合」にのみ検討します。両者を同時に進める場合には、嘆願を書面の作文として活用するよりも、まず併願計画を確実に回すことが賢明です。
このとき注意するべきは、嘆願の理由が薄すぎたり、過度に感情的だったりすると信頼性を損う点です。嘆願はあくまで正当性と具体性を重視します。
そして、すべての手続きは「期限を守る」「情報を正確に伝える」「件名と提出先を間違えない」という基本が最も大切です。信頼性の高い申請は、結果を左右することがあります。
まとめとして、併願は現実的な選択肢を増やす実務手段、嘆願は正当な理由を丁寧に伝える特別な依頼です。これらを混同せず、目的に応じて適切に使い分けることが、受験を成功へと導く鍵になります。
具体的なケーススタディと注意点
ケース1: 第一志望校の筆記試験が難しく、合格ラインへ到達しない可能性が高い。ここで併願を活用して他校での合格確率を高める。ケース2: 家族の看護が必要で、受験日程に支障が出る恐れがある。嘆願を検討する前に、まず学校へ連絡して事情を説明し、提出書類の再調整や別日程の相談を行う。ケース3: 募集要項が複数校で異なる場合、併願の書類を重複させないよう、各校の指示を厳守する。
このような具体的ケースを想定することで、何が正しい対応かが見えやすくなります。
最後に、表での比較も参考にしてください。次の表は、併願と嘆願の基本的な違いを短く整理したものです。
友達とカフェで話していたときのこと。Aくんは「併願って、たくさん出せばいいんでしょ?」と言い、Bさんは「違うよ。併願は“機会を増やす手段”であって、嘆願は“特別な事情を正しく伝える行為”だから、それぞれの目的に合った使い方をするべきだよ」と説明してくれました。私はこの話を聞いて、手続きは計画と誠実さが鍵だと実感しました。
それぞれを区別して使い分けることは、結果的に自分の志望校選択を守ることにつながります。中学生にも伝えたいのは、感情ではなく事実と締切を守ること。守るべきルールを理解すれば、焦りも減り、落ち着いて判断できるようになります。





















