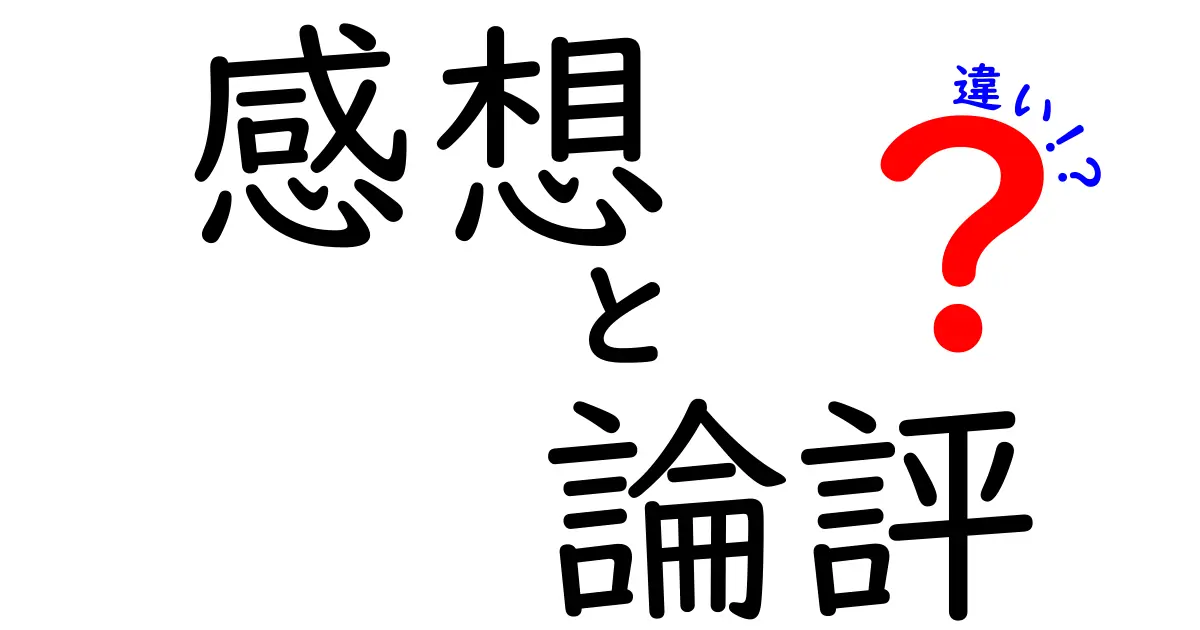

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
感想と論評と違いを徹底解説する理由
この項目は、日常の会話や授業でよく使われる「感想」と「論評」の違いを、はっきりさせるための導入です。私たちは何かを体験した直後、まずは自分の感情を素直に言葉にします。そこから、なぜそのように感じたのかを考え、他者の意見と照らし合わせて自分の認識を整えます。こうした作業を繰り返すと、意見のぶつかり合いが起こりにくくなり、話し合いがより建設的になります。
感想と論評の違いを理解することは、ニュースを読むとき、映画を批評するとき、学校の課題を書くときなど、あらゆる場面で役立ちます。
本章では、感想と論評の定義を整理し、違いを見える形で示していきます。
最終的には、感想と論評を適切に使い分けられるようになることを目指します。
感想は心の声、論評は根拠と評価基準の組み合わせという基本認識を押さえましょう。
感想とは何か
感想は個人的な心の声であり、体験を通して浮かぶ主観的な印象や感情を自由に表現するものです。
良い点も悪い点も、好き嫌いも、直感的な温度感も含まれます。例えば映画を見て「音楽がとても良かった」「色彩が印象的だった」「主人公の気持ちに強く共感した」というように、体験の直後に生まれる感覚を素直に言葉にします。
ただし、感想だけでは作品の総合的な評価を示す根拠には不足します。人それぞれ感じ方が違うため、同じ場面でも受け取り方は分かれがちです。
感想を書くときには、いつ・どこで・何を見たかという体験の文脈を添えると読者に伝わりやすくなります。
このセクションの次では、感想をどうやって「論評」の材料に変えるのかを考えます。
論評とは何か
論評は作品や出来事に対して、評価基準を設定し、理由と証拠を添えて判断を示す文章です。感想が心の声であるのに対し、論評は価値判断を裏付ける筋道を整理します。
具体的には、演技力・脚本の構成・演出の意図・社会的背景など、評価の軸を決め、それぞれに対して具体的な事例を挙げます。
論評には反論の余地があり、別の視点やデータを提示されると見直しが生まれやすい特徴があります。
読者は結論だけでなく「なぜそう思うのか」を知ることで納得感を得られます。
違いを理解する実践的コツ
日常の議論で感想と論評を混同しないコツは、最初に「私の感想」と「根拠となる論評」を分けて考えることです。
練習として短い文章を書いてから、後半に論評の要素を追加してみましょう。
強調したいポイントは単なる箇条書きではなく、段落内の文脈で示すと読みやすさが増します。
また、他人の意見を聞くときは「なぜそう感じたのか」を質問し、 証拠の有無を確認します。これを繰り返すと、感想と論評の境界線が自然と身についてきます。
友だちとカフェで雑談している場面を想像してください。Aさんは『この作品の感想はよかった』と言い、Bさんは『でも論評としてはこういう点が弱い』と返す。感想は体験を通して生まれる心の声で、直感的な印象を語るだけで終わりがちですが、論評はその感想を裏付ける理由と証拠を添えることで説得力を持たせます。私たちは普段、感想と論評を混同して使う場面が多いですが、区別を意識するだけで文章の質が格段に上がります。さらに、感想をどう論評の材料に変えるか、どの sequenceで情報を並べるかなど、実践的なコツを友人同士の会話風の例を通じて掘り下げていきます。





















