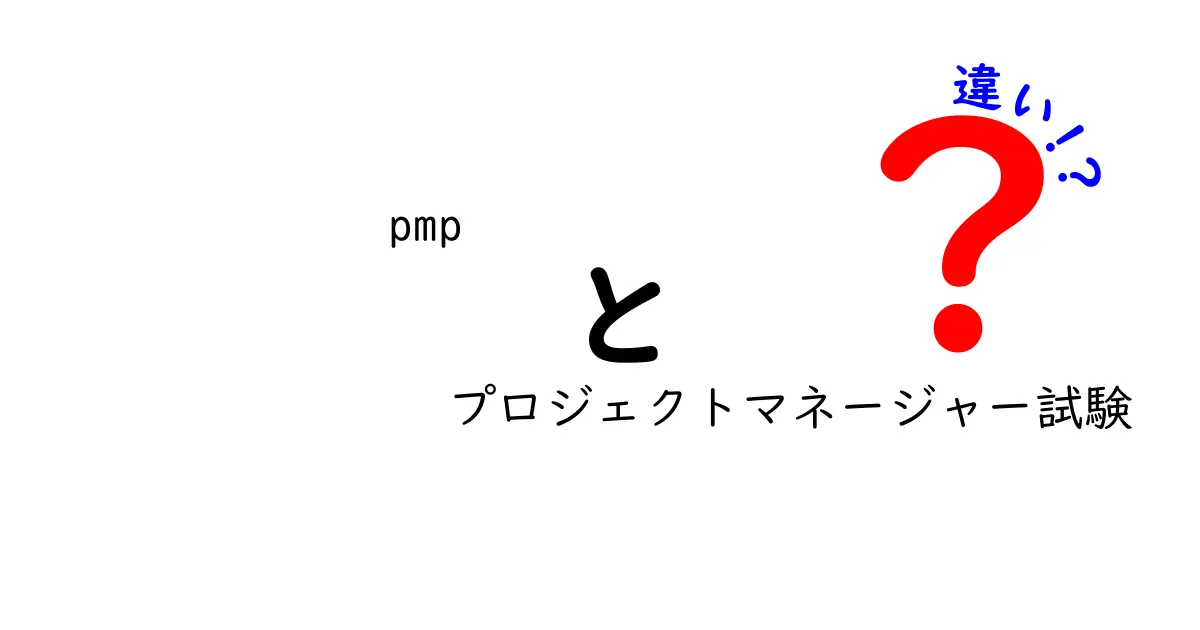

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PMPとプロジェクトマネージャー試験の違いを徹底解説
まず結論から言うと PMP は世界規模の認定資格で、プロジェクトマネージャー試験は一般的な名称で、主に日本国内の教育機関や企業が実施する検定・評価の総称のことを指します。PMPは PMI (Project Management Institute) が公式に認定する資格で、取得には学歴と職務経験の厳格な要件と、4時間の試験がセットになっています。取得後は世界中の企業で共通言語として評価されやすく、履歴書に加えることで国をまたいだ仕事の機会が広がる可能性が高いです。一方で「プロジェクトマネージャー試験」という名称はかなり幅広く使われ、実際には団体ごとに試験の設計や難易度、受験要件、更新の有無が異なります。つまり同じ“試験”でも、実際に得られる資格名の価値は大きく異なる場合があるのです。
特に中小企業や地域の講座では、ビジネス上の基礎力を測るための内部試験として設計されていることが多く、国際認証ほどの汎用性は期待できないことがあります。PMPを狙う人は海外での転職や海外勤務を前提にする人が多く、英語での受験・学習にも対応する必要があります。対して国内のプロジェクト適性検定は、日本語での説明が中心で、国内の求人市場での通用性やキャリアパスの幅がやや狭くなることが多いのです。
PMPの特徴をさらに押さえると、試験は内容が People、Process、Business Environment という3つの領域に分かれており、PMの実務を横断的に理解していることを問われます。問題の難しさは実務経験と直結しており、ただ公式テキストを丸暗記するよりも、実際のプロジェクト経験をどうPM手法に落とし込めるかが問われます。受験要件としては学位を問わず35時間以上のPM教育が必要で、4年制大学の学位がある人は36か月以上、学歴が高校程度の場合は60か月以上のPM経験が求められます。さらに資格を維持するには3年ごとにPDUsと呼ぶ継続教育単位を取得し、更新手続きを行う必要があります。これらの点から、PMPは「長い目でキャリア設計をする人向けの投資」だと言えるでしょう。受験料は地域や会員かどうかで異なりますが、概ね非会員で5万円前後、英語試験の受講や公式教材を含めると追加費用がかかります。
以下は PMP と一般的なプロジェクトマネージャー試験の基本的な違いを比較した表です。見やすさのために、要件・認定機関・試験形式・更新・費用の4つのポイントを並べています。
4年制大卒の場合は36ヶ月以上のPM経験
高校卒の場合は60ヶ月以上のPM経験
日常の場面での実践的な使い道と選び方のコツ
結局のところ、資格を選ぶ際のコツは自分のキャリア計画と、今後の勤務地域、英語力、学習時間の確保です。海外のプロジェクトを増やしたい人は PMP の取得価値が高まりますし、国内でのデジタル系案件を多く扱う企業であれば日本語対応の講座で足りる場合もあります。学習法としては、実務経験をベースにケーススタディを多く解くこと、PMBOK ガイドの概念を日常の業務に落とす練習を重ねることが有効です。模擬試験を受けて自分の弱点を把握し、必要に応じて勉強計画を3か月スパンで組み直すと効果的です。
また、試験の語学サポートも重要です。PMPは英語の原典があるため、英語が苦手な人は日本語版の教材で学習を始め、徐々に英語版へ移行する段階を設けると良いでしょう。どんな場面でその知識を使うのかを具体的に描くと、学習の動機づけも強化されます。最後に、資格はあくまで道具です。実務での成果や、チームをまとめる力、リスク管理の実践の成功体験が評価される場面は多いです。
友達とカフェで PMP の話をしていた時のこと。彼女は難しそうだけど挑戦したいと言い、私はこう答えた。PMP は世界標準の資格で、取得すると海外の仕事にも強くなるケースが多いよと伝えた。実務経験を積んでから学ぶべき内容が体系化されているので、日常の業務の中で考え方の幅が広がるのが魅力だ。学習のコツは実際の案件に落とし込む練習と模擬試験の反復。英語が苦手でも日本語教材から始め、徐々に原典へと移行すると良い。
前の記事: « 傍受と受信の違いを徹底解説!中学生にも伝わるやさしい入門ガイド





















