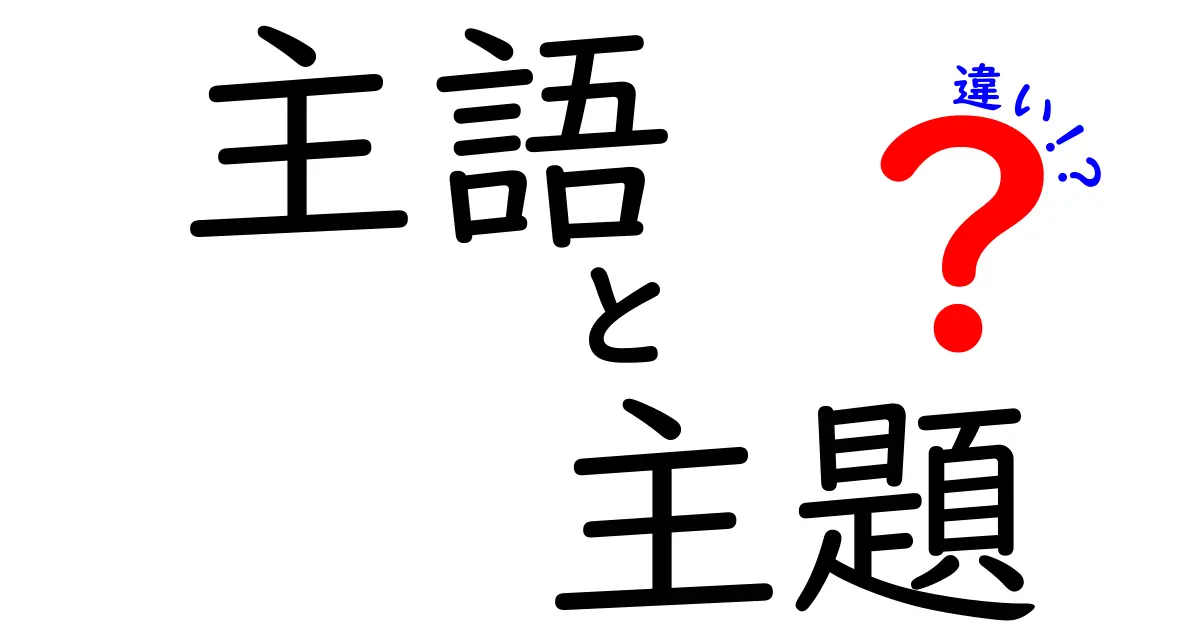

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
意味が変わる!? 主語と主題の違いを中学生にもわかる言い回しで徹底解説
文章を読むとき、しばしば「この文の主語は誰?」と「この文の主題は何?」が混同されがちです。実はこの2つの概念は似ているようで、役割が異なります。
本稿では、主語がどういうものか、主題がどういうものかを、実例とやさしい説明で丁寧に解説します。中学生にも理解しやすい言い回しを心がけ、
段落ごとに要点を整理し、読み終わったときには『この文はどちらが主語で、どちらが主題か』を自分で判断できる力を身につけられるようにします。
まずは定義の違いを確認し、次に具体的な文章での役割、最後に誤用を避けるコツを紹介します。
この理解を深めると、作文や読解、プレゼンテーションの準備がぐんと楽になります。
主語とは何か
主語とは、文の中で動作を行う人やもの、あるいは存在を指す語です。日本語の基本的な特徴として、主語は助詞「が」や「は」で示されますが、実際には省略されることも多いです。例えば『私はリンゴを食べる』では『私』が主語で、動詞『食べる』の主体を示します。
このとき、主語は誰が・何がという質問に答える役割を持ちます。日常の会話では、主語が明示されないことも多く、その場合は文脈から推測します。文の構造を理解する第一歩として、主語を見つける練習を日ごろからしておくと、長い文章でも意味の流れをつかみやすくなります。
また、図や表現方法を使う場面では、主語を明確にすることが読み手や聞き手の理解を助けます。
さらに、作文の過程で主語を工夫することで、読み手に伝えたい情報の焦点を正しく伝えられるようになります。例えば、説明的な文と感情的な文を並べるとき、主語の取り扱いを変えるだけでニュニュアンスが大きく変化します。
このような観点から、日常の会話だけでなく、作文やプレゼンの準備にも役立つ基本スキルです。
主題とは何か
主題とは、文や話が中心に扱おうとするテーマ・論点のことです。英語の“topic”にも近い意味で、文の焦点を決める大事な要素です。例えば『この物語の主題は友情だ』という場合、話の中軸となる意味やメッセージを指します。
主題は必ずしも一語で表される必要はなく、複数の語で表現されることもあります。文章全体の目的や伝えたい思いを支える核となる考えです。作文のときには、主題を決めてから導入・展開・結論を組み立てると、読み手に伝わりやすい文章になります。学校の国語の授業では、主題を見つける演習が多く行われ、読解の精度を高めるための練習が重要です。
また、主題と主語の関係を混同すると、読解で「この文が何を伝えたいのか」が分かりづらくなります。主題は文章全体の核を指すのに対し、主語はその核をどう表現するかの手段として動くことが多いです。ここを正しく掴むと、長文読解での誤解がぐんと減ります。
主語と主題の違いを見分けるコツ
違いを見分けるコツは、文を“何について”見るかと“誰が”見るかの2つの視点を切り替えることから始まります。
コツ1: 文を読んだら、まず動詞の前後にある語を探し、誰が動作をするのかを確認します。これが主語のヒントになります。
コツ2: その文が何を伝えようとしているのか、文全体を読んで“話題・論点”を探します。このとき主題は名詞句や動名詞、あるいは長い説明になって現れます。
コツ3: 置き換えテストをしてみるのも有効です。例文『私が本を読む』を『本を読むことは私にとって楽しい』と置き換えると、主題の変化が見えるはずです。
コツ4: 論説文や説明文では、主題を最初に提示して以降は主題を支える情報を述べる構成が多いです。
最後に、練習問題を解く習慣をつけると、日常の文章にも応用しやすくなります。
このコツを身につければ、短い文章でも主語と主題の違いを整理して読み解くことができ、より深く内容を理解できます。
ねえ、今日の記事を読んで思ったんだけど、主語と主題の違いって実は日常会話でも結構混乱するよね。友達と『この映画は面白い』って話すとき、主題は“映画そのものの良さ”だけど、誰が話しているかを決めるのは主語の役割。僕がメモを書くときは、まず主題を決めてから、誰がそのことを伝えるのかを決めるようにしている。そうすると、文章の焦点がぶれず、読み手にも伝わりやすくなるんだ。主語と主題を分けて考える癖をつけると、日記、作文、発表など、表現の幅がぐんと広がる。日々の練習次第で、言葉の力は確実に上達するよ。
次の記事: 主題と命題の違いが1分でわかる!中学生にも伝わるやさしい解説 »





















