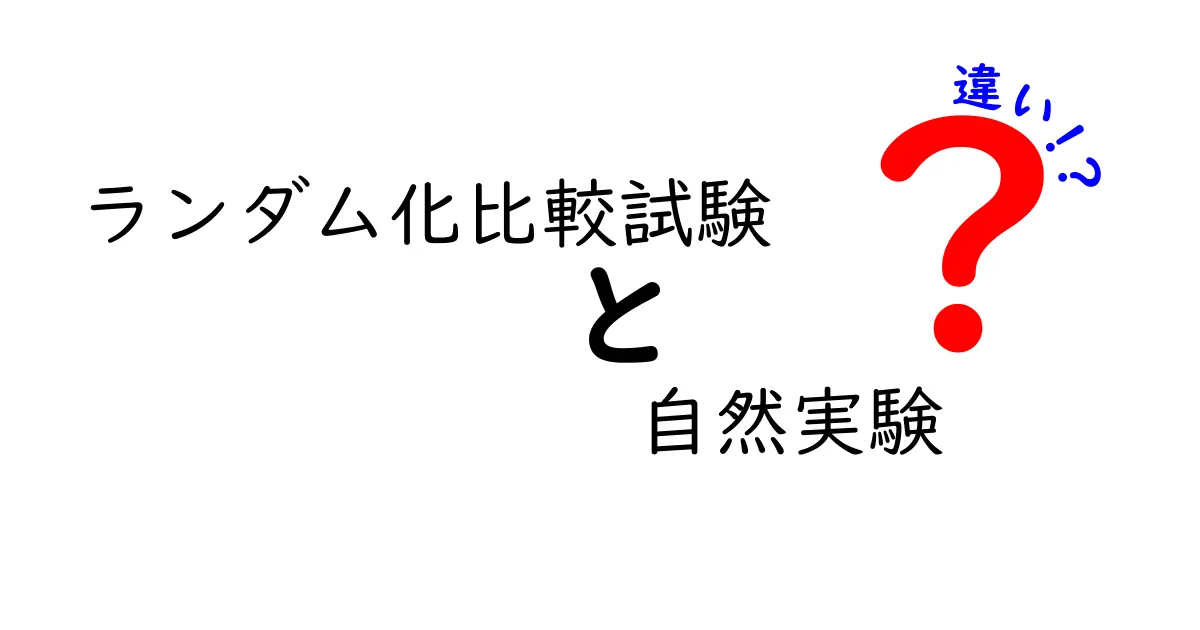

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:ランダム化比較試験と自然実験の基本
ランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial、RCT)は、研究対象を無作為に「介入群」と「対照群」に分け、介入の影響を厳密に測定します。
無作為化によって、年齢や性別、既往歴などの差を偶然に均等化し、介入が結果に与える純粋な影響を見つけやすくします。
このためRCTは医療や公衆衛生など、因果関係を正確に知りたい分野で金の標準と呼ばれることが多いのです。
一方、自然実験は研究者が介入を人為的に決めない状況を利用して因果効果を推定します。
自然現象や政策の変化などにより、介入の割り当てがほぼランダムに近い状況が生まれると仮定する方法です。
自然実験の代表的な手法には差分の差分法、回帰不連続設計、時系列を使った変化の検出などがあります。
例として教育政策の導入が地域によって異なる場合を挙げると、介入を受けた地域と受けていない地域を比較して効果を推定します。
違いを生む仕組みと現場での使い分け
両者の大きな違いは介入の決定とデータの制約です。
RCTでは研究者が介入の有無をランダムに割り当てるため、偏りが生じにくく因果関係を厳密に推定しやすいという利点があります。
一方、自然実験は現実の世界のデータを使うため、実際の政策や環境変化の影響を観察できる点が魅力です。
ただし介入の割り当てがランダムではないため、効果を特定するには厳格な前提条件や統計的工夫が必要になります。
研究デザインの選択は研究課題や倫理的制約、データの入手しやすさ、時間の制約などと密接に絡んでいます。
以下の表と例を参考に、どちらを使うべきか判断するとよいでしょう。
結論として、研究の目的と現実的な制約を見極めて設計を選ぶことが大切です。
実務ではこの二つを組み合わせた「準実験デザイン」が用いられることも多く、データ解析のスキルと倫理的配慮が問われます。
表で見るポイントとよくある誤解
このセクションでは、読み手がよく勘違いする点を丁寧に解説します。
まず、因果関係と相関関係の区別をはっきりさせることが重要です。
観察データには相関が見えることが多いですが、それが必ずしも因果を意味するわけではありません。
次に、ランダム化が必ずしも外部妥当性を保証するわけではない点にも注意が必要です。試験が特定の集団で行われた場合、その結果を別の集団へ単純に一般化することは難しいことがあります。
さらに、自然実験でも前提条件を満たしていないと偏りが生じ、誤った結論に導かれる危険があります。
倫理面では、介入を人為的に割り当てるRCTは参加者の同意や安全性を厳しく守る必要があります。
こうした点を踏まえ、研究デザインを選ぶことが大切です。
友達と喫茶店で自然実験の話をしているとき、自然実験は現実の出来事を使って因果を解く探検みたいだねと誰かが言いました。政策の変化や地域のイベントが、私たちの行動にどう影響するかを、ランダムに割り当てられなくても推定できる点が魅力です。研究者は前提条件を丁寧に確認し、データの質をそろえ、結果の解釈に慎重になります。つまり、現場の偶然の出来事を味方にして、信頼できる結論を引き出す作業です。もし友だち同士で「この変化は本当に影響したのか」と話すとき、彼らの観察力とデータの読み方が問われます。
次の記事: 記入例と記載例の違いを徹底解説|日常で使える使い分けのコツ »





















