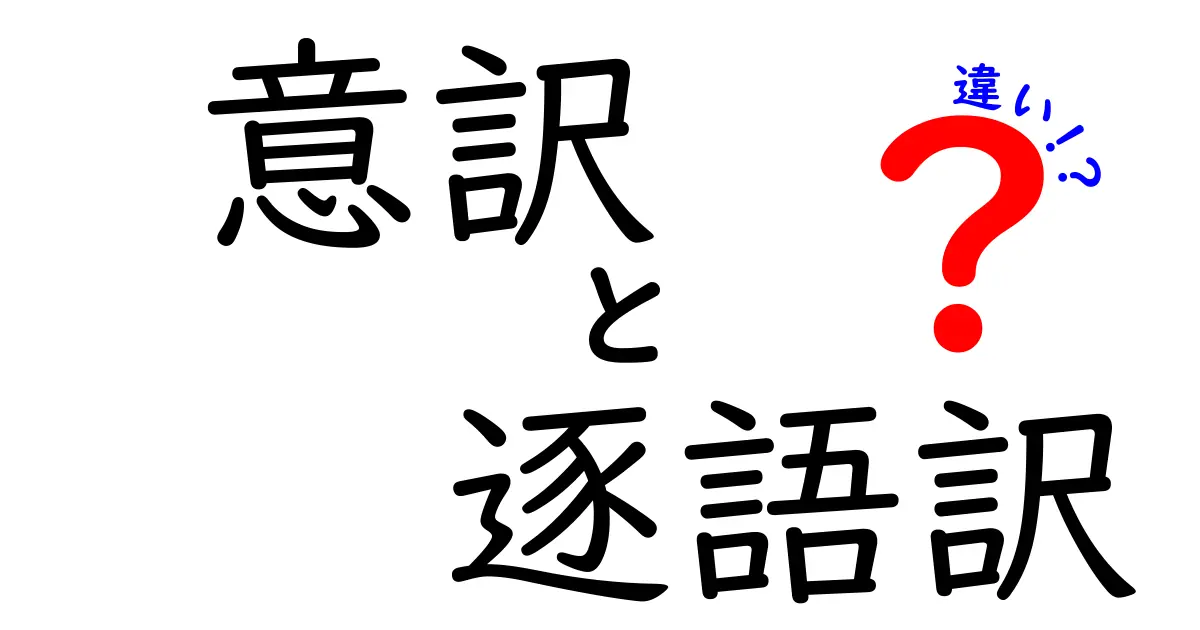

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
意訳と逐語訳の違いを知っておくと得をする理由
外国語の文章を日本語に訳すとき、文字どおりの言葉を並べるだけでは伝わらないことが多いです。そこで登場するのが“意訳”と“逐語訳”の2つの考え方です。意訳は意味を重視して、話の流れや場面の雰囲気を壊さないように日本語として自然な形に整えます。これに対して逐語訳は、原文の語順や言葉をできるだけそのまま日本語に写そうとする方法です。どちらを選ぶかは、読者の期待や翻訳の目的によって決まります。読書教材やニュース記事、文学作品など、場面ごとに使い分けるコツを覚えるととても便利です。
例えば、英語の“It’s raining cats and dogs.”を直訳すると“それは猫と犬を降らせている”のようになってしまいます。これは意味が通じません。意訳では“土砂降りだ”や“大雨だ”といった自然な日本語に置き換え、読者が意図をすぐ理解できるようにします。一方、逐語訳では“It’s raining cats and dogs.”を“それは猫と犬が降っている”のように直訳します。語順や比喩のニュアンスが崩れやすく、解釈が分かれる場合もあります。
翻訳の現場では、情報の正確さと文体の調和の両立が求められます。学校の教材では意味を重視する意訳が多く、ニュースや報告書では正確さを保つ逐語訳が使われることが多いです。ただし実務では“意味を崩さず、読みやすい日本語にする”という共通の目標があります。文章の目的を意識して、どちらを優先するべきか判断する癖をつけましょう。
次に、実務の現場での判断基準をざっくり押さえておくとよいです。読み手の期待が「理解のしやすさ」なら意訳を選ぶべき場面が多く、情報の正確さや原文の構造を保つ必要がある場合には逐語訳が適しています。いずれも完璧な答えはなく、状況に応じて使い分ける柔軟性が大切です。翻訳の世界では、“意味を崩さず、読者にとっての自然さ”を両立させることを目標にします。
このように、意訳と逐語訳はそれぞれ長所と短所を持っています。意味を伝えることを最優先する意訳と原文の語順や表現を保つ逐語訳、この両者を使い分ける力をつけると、さまざまな文章に対応できるようになります。読書教材、ニュース、映画の字幕、英語の授業ノート作成など、場面ごとに適した方法を選ぶ練習をぜひ続けてください。
意訳の特徴と使い方
意訳は読者に伝わる意味を最優先します。語順が原文と違っても、文脈が崩れず、話の流れが自然になるように日本語として整えます。子ども向けの教材やドラマの字幕、観光ガイドのように“分かりやすさ”が目的の場面でよく使われます。文章のニュアンスを大切にし、比喩や慣用句も日本語の慣用表現に置き換えることが多いです。
ただし、意味を伝えることを優先するあまり、原文に含まれる細かい表現のニュアンスがぼやける危険もあります。翻訳者はこの点に注意して、読者にとっての最適な意味を選ぶ作業をします。
使い方のコツとしては、原文の目的を理解してから訳を作ることです。例えば情報を伝える資料なら“事実の正確さ”を最優先に、物語性が大切な文章なら“感情の流れ”を重視します。読み手が誰かを想像し、読みやすさと自然さを兼ね備えた日本語を作る練習を繰り返すと上達します。
また、対訳を用意して比較する方法もおすすめです。原文と意訳を並べて読み比べると、どの語をどう置き換えたか、どんなニュアンスを選んだかがわかりやすくなります。強調したい部分を意味の伝達に直結させ、読者の理解を最優先に考える習慣をつけましょう。
逐語訳の特徴と使い方
逐語訳は原文にできるだけ忠実であることを目指します。語順や文法構造、特定の語の意味をできるだけそのまま再現しようとします。学術論文や法的文書、技術マニュアルなど、正確さと原文の形式を保つ場面で強みを発揮します。原文のニュアンスが微妙に色づく場合もあり、専門用語の取り扱いには特に注意が必要です。
この方法の利点は、後で別の人が翻訳を修正するときに“原文に近い状態”を保ちやすい点です。欠点は、読者にとって読みにくく、自然さが不足しがちな点です。
逐語訳を実務で活用する場面としては、速やかな初稿の作成、辞書や用語集の検証、原文の構造を分析する訓練などがあります。後続の段階で意訳を加えることで、読みやすさと意味の両方を整えるアプローチが一般的です。
実際の例を踏まえると、技術文書では“定義と条件”を厳密に示す必要があり、逐語訳の透明性が役立ちます。ここでは原典の語句を保ちつつ、専門用語の統一を意識して表現を整えることが求められます。翻訳者はこの難しさを理解し、後戻りしやすい点を最初の段階で見極めるべきです。
違いを見分けるポイント
意訳と逐語訳の違いを判断するときには、まず目的を考えましょう。読者に何を伝えたいのか、どんな場面で使われるのかが分かれば、適切な方を選びやすくなります。次に語順の直訳性や慣用表現の扱いをチェックします。原文の語順が読みづらい場合、意訳で自然な日本語に置き換える方が読者の理解が進みます。
また、比喩・慣用句・専門用語の扱い方にも注目します。比喩が重要なら意訳で置換して伝える方が伝わりやすいです。専門用語の正確さが最優先なら逐語訳のままに近づけ、必要に応じて後で注釈をつけるとよいでしょう。
最終的には“読者が読みやすく、正しく理解できるか”が判断基準になります。翻訳のプロはこの点を軸にして、意味と文体の両方をバランスよく調整します。理解の壁を取り除くことこそ、翻訳の本質的な役割なのです。
実例で学ぶ使い分け
ここでは簡単な例を使って、意訳と逐語訳の使い分けを見てみましょう。原文“The meeting was adjourned until next Monday.”を取り上げます。意訳では「会議は来週の月曜まで延長されました」となることが多いですが、これは実際には“翌週の月曜日に再開する”という意味合いを自然な日本語で伝える選択です。
逐語訳では“会議は次の月曜日まで閉じられた”のように直訳しますが、文の意味が曖昧になりやすく、読み手が混乱します。ここでは状況に応じて、意味を崩さず読みやすさを保つ意訳を選ぶのが適切です。
この例でわかるように、場面と目的が決まれば「どちらを選ぶのが適切か」が見えてきます。日常の教材やブログ記事、字幕制作など、さまざまな現場でこの使い分けを実践していくと、翻訳力はぐんと上がります。
今日は“意訳”について、友達と雑談する形でちょっとだけ深掘りしてみます。意訳は意味を大事にするから、英語の文章が伝えたい意図を日本語の感覚に合わせて言い換える力が必要です。私は中学生のとき、英語のおもしろい言い回しを直訳して先生に笑われた経験があります。だからこそ、意味を崩さずにどう伝えるかを考える癖をつけると、作文や読書にも役立つと思います。あと、外国のドラマ字幕を見ているとき、「この表現、日本語ではどう言うかな」と考えるのはすごく楽しい遊びです。





















