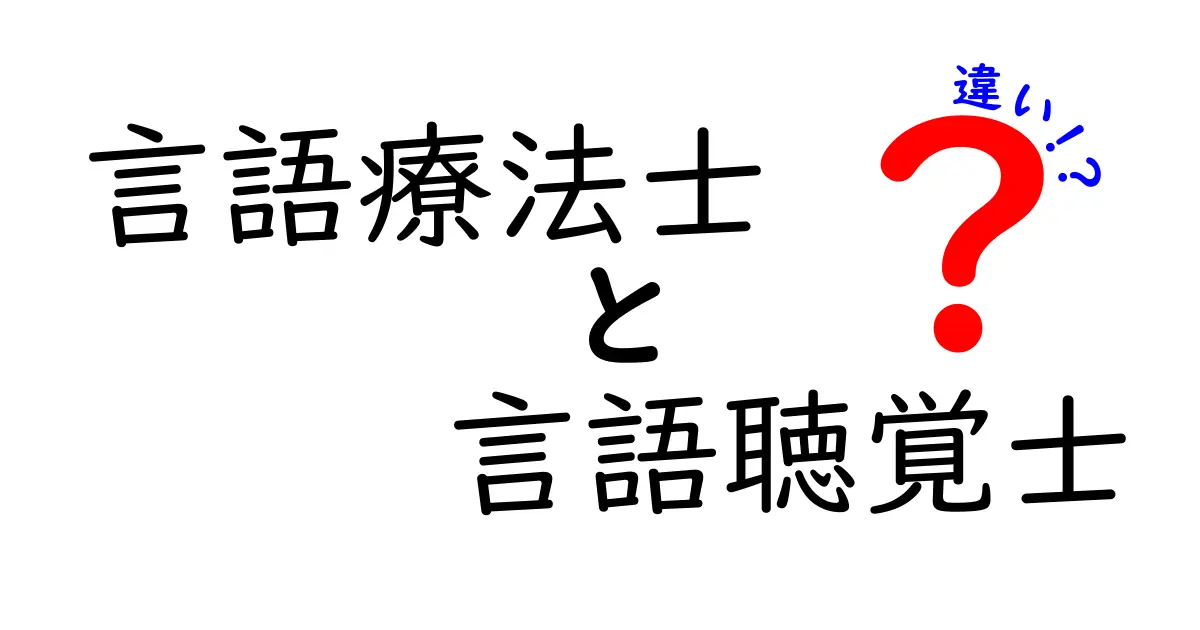

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:言語療法士と言語聴覚士の違いを正しく知ろう
この話題は学校の授業や家族の会話の中でもよく出てきますが、専門的な用語が混ざることで混乱しがちです。結論から言うと日本では正式な名称は「言語聴覚士」です。言語療法士という言い方も耳にしますが、実務的には同じ分野を指すことが多く、呼び方の違いは地域や場面によって異なります。つまり大事なのは「何を支援する職種なのか」という点であって、名称そのものが全てを決めるわけではありません。ここでは、言語聴覚士と言語療法士の違いを、誰がどんな人をどんな場で支援するのかという視点から、できること・教育・現場の呼称まで分かりやすく解説します。
読み進めるほど、学校や病院・クリニックなどの現場での理解が深まるはずです。
さて、まずは呼び方の背景や成り立ちから確認していきましょう。
1. 職種の成り立ちと呼ばれ方の背景
言語聴覚士という名称は、日本の医療・福祉の枠組みの中で正式に定義された職業名です。国家資格として公的な位置づけがあり、養成課程を修了して国家試験に合格することで免許が与えられます。これに対して「言語療法士」という名称は、国の制度上の正式名ではなく、海外での呼称や臨床現場の通称として使われることが多い言い方です。海外ではSpeech-Language PathologistやSpeech Therapistと表現され、国や地域によって細かな役割分担や資格要件が異なります。日本ではどちらも言語認知・言語発達・発音・吃音・嚥下を含む広い領域の支援を指すことがありますが、公式の文書や資格名としては「言語聴覚士」が用いられます。
この違いを知っておくと、海外の情報を調べるときにも混乱を避けやすくなります。
要するに、背景と呼称の一致を意識するのが第一歩です。
2. できること・対象となる人
言語聴覚士は、言語・コミュニケーション・嚥下機能の3つを中心に支援します。具体的には、発達障害の子どもから高齢者の認知機能・言語機能の訓練、吃音(どもり)の改善、発音の矯正、声の安定、文章理解の訓練、飲み込みの機能改善など、多岐にわたる領域を扱います。対象は子どもだけでなく成人・高齢者まで幅広く、病院・クリニック・リハビリテーションセンター・学校など、場所もさまざまです。
また、特定の場面での介入は個別支援計画に沿って行われ、家族や他職種と連携して長期的な支援を提供します。言語聴覚士は臨床現場での実務に強く、耳の聞こえの検査や聴覚訓練の補助を行う専門職と混同されがちですが、本来は言語・嚥下・コミュニケーションの総合的なケアを担います。
3. 教育と資格の違い
教育面では、言語聴覚士になるには専門学校・大学・大学院などの養成課程を修了し、所定の科目・実習を経て国家試験を受ける必要があります。合格すると国家資格として免許が交付され、臨床現場での活動が正式に認められます。後述の現場での呼称と並行して、学習内容は発達心理・言語発達・音声・聴覚・嚥下・認知機能など幅広い領域を含み、実技と理論の両方を学びます。一方で「言語療法士」という表現は、学習の一部を指す際や海外情報を参照するときに使われることが多く、資格名としては正式ではありません。つまり、日本国内での適切な表現は言語聴覚士であることを理解しておくと、医療機関の説明や資料の読み解きがスムーズです。今後の国際的な情報交換を考えると、正式名称と役割の一致を意識しておくと安心です。
実務での違いと現場の呼称
実務面での違いは、患者さんやクライアントのニーズに合わせた「支援の中身」と「呼称の使い方」に現れます。日本の医療現場では、言語聴覚士が中心となって言語・吃音・発音・読み書きの支援を行い、嚥下訓練や高次機能障害のリハビリも担当します。病院では医師と連携して診断を受けたうえで、個別のリハビリ計画を立て、定期的に効果を評価します。クリニックや学校では、保護者や教員と情報共有を密にし、日常生活の場面での適切な練習を家庭でも継続できるようサポートします。
このように現場では「言語聴覚士」という正式な名称を使い分けつつ、実務内容は日常の会話支援から嚥下リハビリまで幅広く展開します。実務の現場でよくある混同を避けるコツとしては、相談時に「対象となる年齢層」「扱う障害の範囲」「具体的な介入内容」を先に確認することです。これにより、適切な専門家へつながる確率が高まります。
また、以下の表は「言語療法士」と「言語聴覚士」の一般的な違いを簡潔に整理したものです。
この表を見れば、正式名称と実務のギャップが分かりやすくなります。結局のところ、読者・患者さん・保護者の方が知りたいのは「誰が何をしてくれるのか」という点です。強調すべきポイントは、言語聴覚士は日本国内の正式な職名であり、臨床現場で広く使われているということ、そして海外情報と日本の制度を結ぶ架け橋として理解することです。
この理解が進むと、学校の授業や病院の説明、あるいは地域の相談窓口での問い合わせ時にもスムーズに進みます。
今日は友人のミカさんと放課後に言語聴覚士について雑談しました。ミカさんは海外のドラマをよく見るので、言語療法士という言い方は耳にしたことがあると言います。そこで私は実際の現場で何をするのかを思い出しつつ、こう話しました。「言語聴覚士は、言葉の練習だけをする人だと思われがちだけど、実はいろんな場面を支える専門家なんだよ。発音や吃音はもちろん、飲み込みの訓練や高齢になってからのコミュニケーションの改善も担当することがある。だから学校ではクラスの発音指導だけでなく、訓練の計画づくりや家庭でのサポート法も教えるんだ。」ミカさんは驚きつつも「なるほど、言葉の“道案内役”みたいな感じね」と言いました。私は続けて「呼び方の違いは地域差もあるけど、正式には言語聴覚士。海外情報を探すときは名称の違いに注意すると楽になるよ」と伝えました。雑談の中で、私たちは今後の学習や将来の進路選択にも役立つヒントを得た気がしました。





















