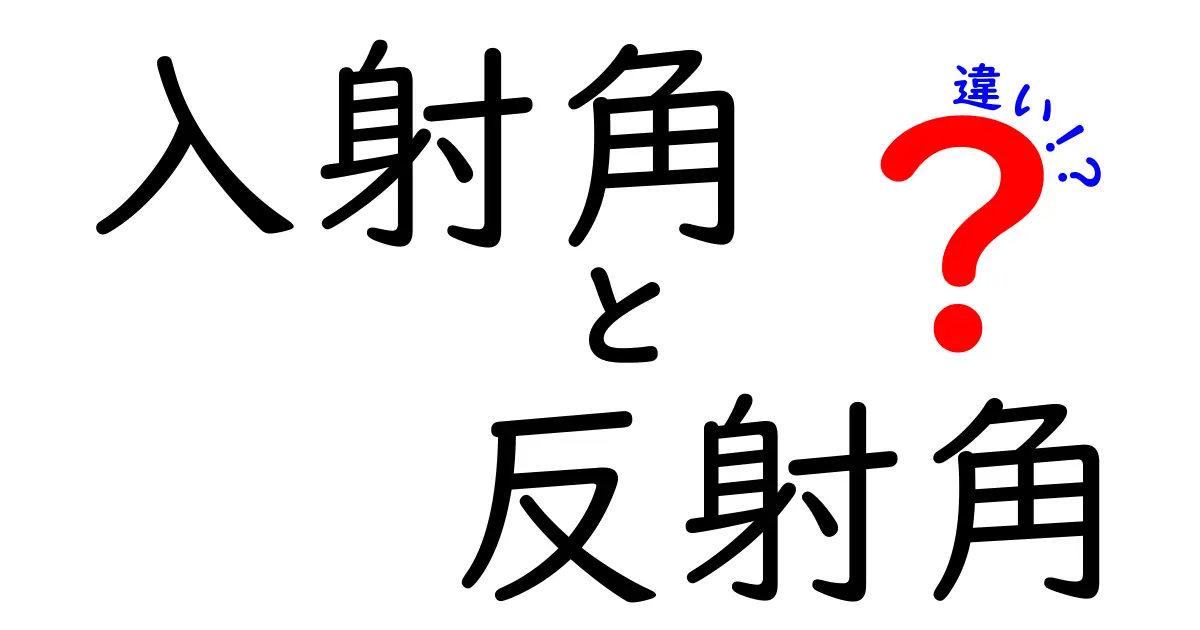

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
入射角と反射角の違いを押さえる基本ガイド
光の世界では、入射角と反射角が出会う場所は鏡の前です。入射角とは、光が平面に当たるときに、光線と法線という垂直な線との間にできる角度のことを指します。法線は鏡の表面に垂直に立つ仮想の線で、実際には見えませんが角度を測るときの基準になります。例えば鏡にライトを当てると、光の進む方向を少しずらしたときに鏡の表面から跳ね返る光の角度が決まります。
この角度は度数で表され、普通は0度から180度の範囲で扱います。実際には水平や垂直の方向を基準にして測るので、観察する場所や角度の取り方次第で見え方が変わります。
重要ポイントは、入射角は「光が鏡の法線と作る角度」であり、測る位置によって同じ光でも角度が変わることはない、ということです。つまり、同じ鏡と同じ光であれば、入射角は常に一定です。これが次に説明する反射角と深く結びつく理由です。
入射角とは何か?
入射角は、光が物体の表面に入ってくるときに、光線と法線との間にできる角度のことです。定義はシンプルですが、実際には測定の仕方で結果が変わりません。学校の実験では、鏡の表面に光を当てて法線を引き、その法線と光の進む方向の間の角度を θ_i として表します。
さらに、入射角には次のような特徴があります。
・法線は表面に対して垂直、見えない仮想の線であること
・入射角は平面内で測定され、鏡の向きや光源の位置で変えられること
・日常生活の中でも、懐中電灯を壁に向けるときの光線の角度を把握する際に役立つこと
このように、入射角は光が物体に「どう当たるか」を決める第一歩であり、後述の反射角との関係性を理解する鍵となります。
反射角とは何か?
反射角は、光が物体の表面で跳ね返るとき、反射後の光線と法線との間にできる角度のことです。重要なのは反射角も法線を基準に測る点で、入射角と同じ法線を使います。実験で鏡に光を当て、反射した光を観察すると、反射角は通常入射角と等しくなることが多いです。これは法則として「反射の法則」と呼ばれ、IoT機器のセンサーの角度設定や建築の設計にも使われます。
しかし現実には全てが鏡のように滑らかではなく、表面がざらざらしていると反射は分散します。鏡のように滑らかで平坦な表面では反射角は等しいのに対し、マットな壁や布地の場合は、反射角がばらつく“拡散反射”となり、見える角度が分散します。日常の光の見え方の違いは、ここに大きく影響します。
入射角と反射角の違いを整理する
次のポイントを意識すると、二つの角度の違いが見えやすくなります。
1) 定義の違い: 入射角は光が法線と作る角度、反射角は反射光と法線の角度である。
2) 測定の基準: どちらも法線を基準に測るが、入射は光線の進む方向、反射は跳ね返る方向を基準にする。
3) 理想的な関係: 理想的な鏡面では、入射角と反射角は等しくなる。
4) 表面の影響: 表面が荒いと反射角は拡散し、映り方が変わる。
理解のコツは、身の回りの光の角度を意識して観察することです。例えば窓ガラス越しに自分を見るとき、ライトの位置と鏡の角度で反射の角度がどう変わるかを想像してみてください。
下の表は、二つの角度の要点を短くまとめたものです。
この表を読み解くと、入射角と反射角がどう動くかを日常の場面で予測しやすくなります。たとえば、部屋の隅で光がどの方向に跳ね返るかを考えるとき、入射角と反射角を思い出すだけで、光の進路をある程度想像できます。これが、反射の基本的な考え方を身につける第一歩です。
koneta: 放課後、友達と鏡の前で実験していたとき、反射角がなぜ同じに見えるのかを話していた。私は角度を紙に丸写しして法線を指さすと、友達が『入射角と反射角は水を注ぐと同じ高さに水が跳ね返るみたいな対称性だね』と言った。つまり、光は転がるボールのように角度を対称に返すのだ。日常の中にも、それを示す例がたくさんある。窓ガラスに映る自分の姿の角度、道路の白線に反射する車のライト、さらには体育館の天井に投影される影の角度まで、角度の対称性を意識するだけで光の動きが見えてくる。
次の記事: クロームと鏡面の違いを徹底解説!勘違いを解消する3つのポイント »





















