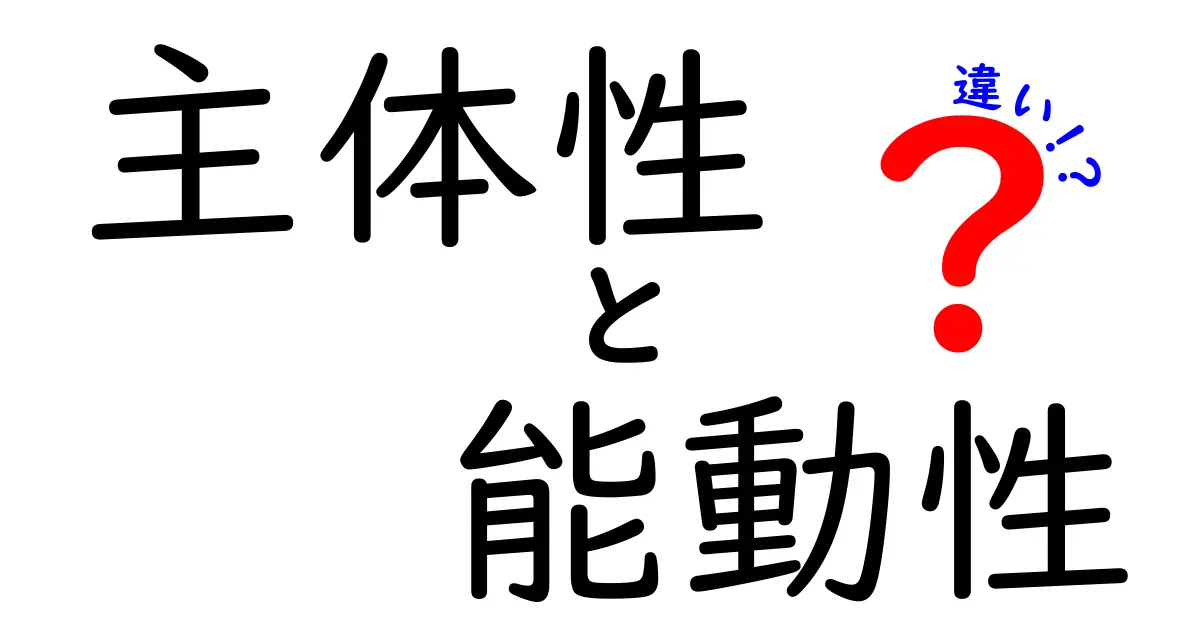

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
主体性と能動性の違いを知ろう
この二つの言葉は似ているようで、実は別の意味を持ち、生活のあらゆる場面で役立つヒントになる。まず、主体性とは自分の考え方や価値観をもとに、物事に向かう姿勢のことです。自分はどうしたいのか、何を大切にするのか、その答えを内側に持ち続ける力です。
つまり、自分の中にある軸や目的を見失わずに、選択や判断を自分で決める力といえます。これが“主体性の核”です。
一方、能動性はその軸を使って現実の世界で動く力を指します。指示を待つのではなく、進んで手を挙げ、動き始め、結果を出す行動力です。
要するに、主体性は「心のあり方」、能動性は「動く行動そのもの」です。これらは密接に関係していて、良い組み合わせを作ると、困難な課題も前向きに解決できる力になります。
日常生活を例に考えると、クラスでの話し合いで「自分はこう思う」と自分の意見をはっきり伝えるのが主体性です。次に、それを受けて友だちと協力して、提案を形にして動くのが能動性です。
この連携ができれば、学習の深さが増し、友だちとの信頼関係も強くなります。
ここから先は、具体的な育て方や、認め方、評価のしかたについて詳しく見ていきましょう。
主体性とは何かを日常の例で整理する
主体性は“自分の内側にある動機や価値観を軸に行動を選ぶ力”と整理できます。学校生活での例を挙げると、先生が出した課題に対して「なぜこの課題をやるのか」を自分なりに考え、最適な進め方を自分で決めていく行動が主体性の発露です。たとえば、提出期限に間に合うだけでなく、事前に計画を立て、必要な準備を自分で調べて進めるような振る舞いです。こうした内的な動機づけが強いほど、外部の指示が少なくても自分で道筋を描けるようになります。
主体性を育てるには信頼できる環境と、間違いを恐れず挑戦できる雰囲気が必要です。先生や家族が「失敗してもいいから挑戦してみよう」と声をかけ、やってみた結果に対して建設的なフィードバックをくれると、子どもは自分の価値観を大事にしながら成長します。
また、日常の小さな決定から自分で選ぶ経験を積むことも有効です。食事のメニューを選ぶ、週末の計画を立てる、班の役割を自分で提案する、などの場面で「自分はどうあるべきか」を考える力が養われます。これらはすべて、後に難しい課題に直面したときの土台になります。
このように主体性は、内面的な動機づけと外的な動作の橋渡しをする役割を果たす概念です。自分の価値観を大切にしつつ、状況に応じて適切に動く力を育てることが大切です。
能動性とは何かを日常の例で整理する
能動性は、言い換えると「自ら進んで動く力」です。先生の指示を待つのではなく、必要だと感じれば自分から動く、友だちが困っていれば手を差し伸べる、という行動様式を指します。能動性はしばしば「能動的な姿勢」とも呼ばれ、プロジェクトを先に進めるときに欠かせない要素です。ここで大切なのは、能動性が単なる行動量ではなく、意味のある行動へ繋がることです。
例えば、授業で新しい実験を任されたとき、ただやるのではなく「どの方法で効率よく、正確に進められるか」を自分で考え、必要な道具や順序を自ら整える。失敗しても修正し、次につなげる姿勢が能動性の真髄です。
また、能動性は協働の場面でも大きな力を発揮します。仲間の意見を取り入れつつ、自分が担える部分を先に手を挙げて進むことで、チーム全体の動きがスムーズになります。能動性のよい実例は、ただ前に出ることだけではなく、周囲を見渡して必要な行動を的確に選ぶ判断力とセットになっている点です。
強調しておきたいのは、能動性は「行動の連続性と意味のある選択」こそが大事だという点です。動く理由が明確で、結果に責任を持てること、それが能動性の本質です。
ねえ、主体性って難しそうに見えるけど、実はとても身近な力なんだ。私がある日、グループ作業で『この案を自分で動かそう』と提案した瞬間、仲間が『いいね、それなら私がこの部分をやるよ』と自発的に分担してくれた。つまり、主体性は他人と協力するための第一歩でもある。自分の価値観をもう一度確かめて、行動に結びつける、それが日常の小さな選択から始まる。最初は小さな決定かもしれないけれど、積み重ねると自分の芯が太くなる。





















