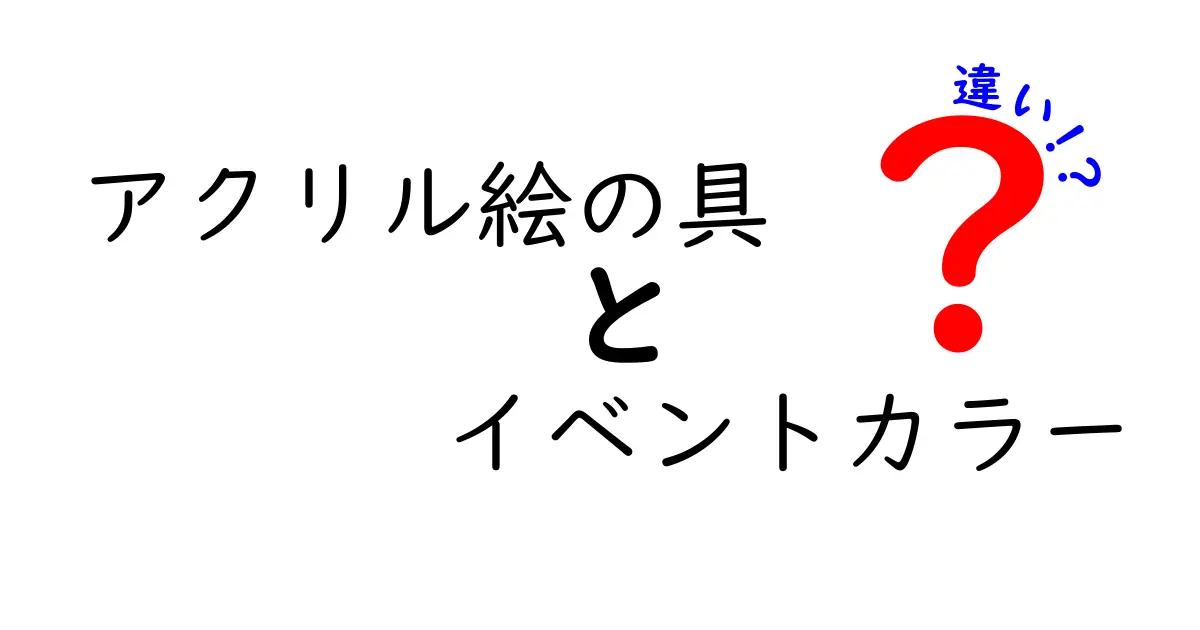

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アクリル絵の具とイベントカラーの違いを知る
アクリル絵の具にはいろいろな種類があり、同じ「アクリル絵の具」という名前でも用途や性質が異なります。中でも「イベントカラー」と呼ばれるものは、特別な場面で使われることを前提に作られています。この記事では、イベントカラーと通常のアクリル絵の具の違いを、初心者にも分かりやすく解説します。まずは結論から言うと、イベントカラーは発色の安定性や耐水性、価格帯、パッケージの設計が通常品と異なることが多いという点が大きな違いです。
イベントカラーはイベント会場の大きな作品展示やフェスティバルで使うことを想定しているため、色が見やすく、剥がれにくく、運搬・保管がしやすい設計になっていることが多いのが特徴です。具体的には、日光や蛍光灯の下での見え方、乾燥後の表面のコーティングの違い、そして長期保管時の色の安定性などが通常の絵の具と比べて考慮されているのです。さらに、イベントカラーは塗膜のつやや質感にも特徴があり、写真映えを意識した色味設計がされていることが多いのも見逃せません。
以下では、イベントカラーと通常カラーの具体的な違いを、実用的な観点から整理していきます。
イベントカラーとは何か
イベントカラーとは、主に展示やパフォーマンス、ワークショップなどのイベント現場で使われることを前提に作られたアクリル絵の具のことです。通常カラーとの大きな違いは、色味の再現性・乾燥時間・塗膜の耐久性・輸送時の取り扱いのしやすさにあります。イベント会場では天候や照明の影響を受けやすく、作品の色が意図通りに見えることが重要です。そのためイベントカラーでは、以下のような特徴を持つことが多いです。
・色が蛍光灯の下でもくすまずはっきり見える設計
・乾燥後の膜の厚みを一定に保つ処方
・水分やアルコール等の接触に対する耐性を高めた配合
・大容量パックや持ち運びやすい容器形状
などが挙げられます。これらは「イベント用に最適化された成分構成」と言え、作品の完成度をイベント会場の光環境下で安定させる狙いがあります。さらに、イベントカラーは混色の際の色味変化が通常カラーより分かりやすく設計されていることが多いため、色の組み合わせを学ぶ学習教材としても活用しやすい一面があります。
実際の使用例と選び方のコツ
学校の美術イベントや地域のアート展で作品を展示する際、どの色を選ぶべきか迷う場面は多いです。この記事では実際の使い方を想定して、コツをいくつか挙げます。まず第一に、目的を明確にすることです。写真映えを狙うのか、長期展示を想定するのか、屋外展示があるのかなどで選ぶべき種類が変わります。次に、色味の確認は現物で行うことをおすすめします。画面上と実物では見え方が異なるため、できればサンプルを数色試して、色の深さ・明るさ・ツヤを実際の照明でチェックしましょう。最後に、取り回しの良さを重視することです。イベント用パックは50ml〜1500mlと容量が幅広く設定されています。大きな作品を塗る場合は大容量の方が経済的で、旅行や搬入の際には軽量・丈夫な容器を選ぶと良いです。以上のポイントを押さえれば、イベントカラーは発色の安定性と操作性の高さを両立させる優れた選択肢になります。
イベントカラーの話題を友達と雑談しているときの体験談。私は最初、イベントカラーはただ派手な色が多いだけなのかと思っていました。しかし実際には、イベント会場の明るさや照明の影響を前提に設計された成分が多く、色が飛ばず長時間美しく保てる点が大きな違いだと気づきました。搬入時の扱いやすさ、現場での実演にも適する耐久性、写真映えを意識した仕上げなど、現場のプロが求める要素がギュッと詰まっています。私自身は、現場で色味を確認するためにサンプルをいくつか用意して照明下で比べる方法を取り入れています。友人にもすすめるときは、目的と展示環境をはっきりさせてから色を選ぶと、後から後悔しにくいと伝えています。
結局のところ、イベントカラーは通常の絵具より“現場適応力”が高いアイテムだと感じます。だからこそ、イベントを意識した練習やワークショップでは、最初にイベントカラーの扱い方を覚えると作品の完成度が格段に上がるのです。





















