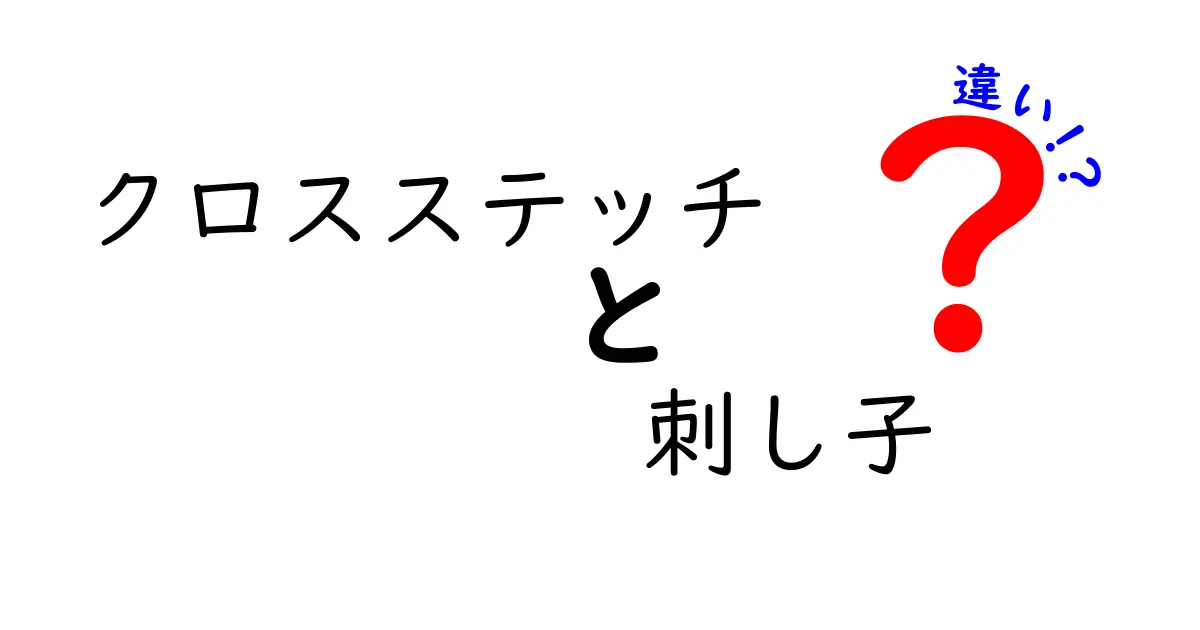

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クロスステッチと刺し子の違いを徹底解説:初心者にも分かる選び方と作り方
1. 基本の違いを押さえる
クロスステッチ(cross stitch)と刺し子(sashiko)は、同じ「布に針を刺して模様を作る」という点では共通していますが、実際には「どのように刺すか」「どんな布・糸を使うか」「目的は何か」で大きく異なります。クロスステッチは、布目に合わせて十字形のステッチを並べて模様を作る方法で、アイーダ布やオフホワイトのキャンバス布が定番です。糸は通常、色鮮やかな糸を使い、作品の色の組み合わせを楽しみます。初心者でも取り組みやすく、完成までの道のりが比較的短いのも特徴です。また、デザインの自由度が高く、洋風・和風を問わず、カードやタペストリー、刺繍枠のないポーチなど、さまざまなアイテムに応用できます。
一方、刺し子は日本の伝統技法で、走り刺しのような直線的な模様が多く、布地は厚手で耐久性の高い素材(晒・木綿・デニムなど)を使います。布地の目を揃える必要があるというより、布の強度を高め、縫い目を美しく揃えることを重視します。模様は幾何学的・縦横の連続性を持つデザインが多く、縫い終わった後の風合いは素朴で味わい深いです。材料費も比較的安価で、実用性の高さが魅力ですが、初期の練習には針運びのリズムを覚えるまで少し時間がかかるかもしれません。これらのポイントを押さえると、どちらを選ぶべきかの判断材料が見えてきます。
まとめ:クロスステッチは色とデザインの自由度が高く、作品の完成までの時間が短め。刺し子は布地の強度と伝統的な美を重視し、日常の道具を丁寧に作る感覚を楽しむ手法です。
2. 作品作りのアプローチの違い
クロスステッチと刺し子では、作品を完成させるための思考プロセスも異なります。クロスステッチはまずデザインを決め、図案を布に転写し、糸の色を決め、各目の数を数えながら刺していくのが基本です。デザインの組み合わせ次第で和風・洋風・抽象的な柄まで幅広く対応でき、完成写真のビジュアル的な満足感を得やすいのが特徴です。作業のテンポはゆっくりでも、計画性を持って進めれば、短期間で一枚の完成品にたどり着くことができます。
一方、刺し子は、布地の補強・耐久性向上を目的とした実用品寄りの制作が多く、模様よりも実用性が優先される場面が多いです。針運びはリズム感と力の配分が大切で、長時間作業を続けると手首や指の疲労が出やすい点に注意が必要です。デザインは伝統的な模様を踏襲するか、オリジナルのパターンを刺すかで選択肢が分かれ、日常用品を作る過程そのものを楽しむ人が多いです。どちらも「完成したときの達成感」は大きいですが、目標が実用性か美観かで作業の流れが少し変わってきます。
実践例として、クロスステッチで小さな額装を作る場合は、布目の数え間違いを避けるための下準備と、色数の管理が重要です。刺し子でポーチの補強部分を作る場合は、縫い目の間隔を均一に保つ練習と布の伸縮を考慮した糸の選択がポイントになります。
3. 道具と材料の比較
道具と材料について、それぞれの方法の基本的な揃え方を見ていきましょう。クロスステッチは通常、以下が基本セットです。アイーダ布、専用の刺繍針、刺繍糸(多色)、はさみ、裁ちばさみ、刺繍枠またはフープ、デザインの図案、そして練習用の布。糸の色数は作品の雰囲気を大きく左右します。初級者は手頃な色数のキットから始めると失敗が少ないです。
刺し子は、布の補強を目的とした実用品寄りの道具が中心です。用意するのは、刺し子糸、専用の針(刺し子針は長さや針穴の大きさが重要)、デニムや晒などの布、裁ちばさみ、定規、糸と布を結ぶための基本的な結び方の練習、そして模様の型紙です。特有の道具としては、布の上で刺し子糸を引っ張るときにズレを防ぐための布端処理用品や、伝統的な indigo dye の布との相性を考えた素材選びが挙げられます。
ここで覚えておきたいポイントは、道具は「作品を楽しく作るための相棒」であり、初期投資を抑えることも可能だということです。キットを活用すれば、材料選びで迷う時間を短縮できます。
さらに、表を使って比較すると、次のようになります。
この表を見れば、道具と材料の違いがはっきり分かります。
どちらを選ぶにしても、まずは安全な作業スペースと適切な照明を確保することが大切です。良い環境が整えば、練習も習慣化しやすくなります。
最近友達と話していて、刺し子の話題になりました。刺し子は地味で堅苦しいイメージを持つ人もいますが、実は布を補強しつつ美しく仕上げる現代的なクラフトです。私が感じた魅力は、手元の作業を通じて心の落ち着きを取り戻せる点と、材料が手頃なこと。デニムのポーチに刺し子を施したとき、布の硬さと糸の色合わせが生み出す変化に驚きました。基本的な針運びを練習すれば、長期間使える実用品を作れるのが嬉しい点です。日常の中に「少しの時間」を刺し子に割くと、学業の合間の気分転換にもなります。これから挑戦するみなさんには、最初は小さな模様から始め、布地と糸の相性を確かめることをおすすめします。
前の記事: « ココナッツオイルとヤシ油の違いを徹底解説!どっちを選ぶべき?





















