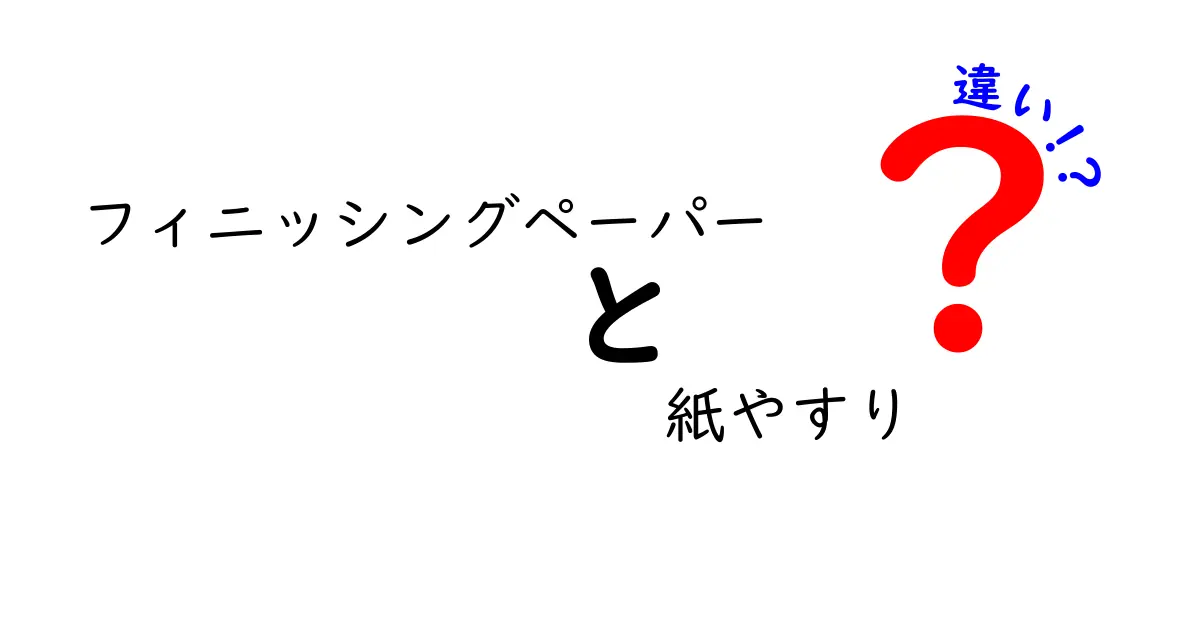

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:違いを知るメリットと基本概念
この二つの用語はDIYや職人の現場で混同されやすい言葉です。フィニッシングペーパーは、名のとおり「仕上げ」を目的とした粒度の細かい紙やすりで、主に塗装前の最終段階で表面をととのえる役割を担います。反対に、紙やすりは木材・金属・プラスチックなどの表面を削ったり整えたりする、広い用途を持つ道具の総称です。粒度が小さくても等級の違いによっては塗装の密着性を高める一方、粗い粒度は素材を速く削って形を整えるのに向いています。では、どういう点が違うのかを、具体的な場面と粒度の目安で見ていきましょう。
違いを理解するには、いくつかの要素を押さえると良いです。まず、粒度の範囲です。フィニッシングペーパーはおおむね320~800番台、あるいはそれ以上の高番手を指します。これに対して紙やすりは40番前後の粗さから、600番以上の中~細目まで幅広く使われます。次に、使う目的です。塗装前の下地作りなら、最初は粗めの紙やすりで形を整え、段階的に細かくしていくのが基本です。塗装仕上げの直前には、表面を滑らかに整えるための高番手のフィニッシングペーパーを用います。さらに、貼り方と裏地の違いも影響します。紙を使う場合は紙地が薄くて破れやすい場面もあるため、クレーム現場での長時間の作業や湿度の高い環境では丈夫な表地の紙やすりを選ぶことが大切です。こうした違いを理解しておくと、後で「この道具はこの作業に合っているのか」という疑問を減らせます。
フィニッシングペーパーとは何か
ここでは、フィニッシングペーパーがどんな道具かを詳しく見ていきます。フィニッシングペーパーは最終的な仕上げに特化した粒度の細かい紙やすりです。素材は木材、プラスチック、金属の表面など、さまざまな素材で使われますが、共通して目的は“表面を均一で滑らかにすること”です。
塗装前の下地を整える段階では、400番前後から800番、場合によっては1000番以上といった高番手を選ぶのが一般的です。
魅力は、微細な傷や畝を均す能力と、塗装密着性を高める性質にあります。ここでのコツは、力を入れすぎずに、一定の圧力で表面を滑らかになるように磨くことです。
材料の違いにも注意が必要です。フィニッシングペーパーの背地は紙、布、あるいは特殊な粘着剤が使われることがあります。布地のフィニッシングペーパーは耐久性が高く、湿気の多い環境でも安定して使えることがあります。また、砥粒の素材としてはアルミナやシリコンカーバイドが代表的で、金属面にも使用可能です。適切な粒度と背地の組み合わせを選べば、木材のオイル仕上げやラッカー・塗装前の下地処理で優れた結果を得られます。
紙やすり(サンドペーパー)とは何かと用途
一方、紙やすりはより広い目的に使われる道具です。粗削りから細かな仕上げまで幅広いグリットレンジを持ち、木材の粗削り、金属のエッジの丸め、プラスチックの成形など、作業の出発点となる場面で活躍します。特に木工では、最初の段階で40番〜80番程度の粗さで板目を整え、次に120番〜180番程度で形を出し、最後に320番〜400番程度で表面を滑らかにします。金属やプラスチックでは、酸化物の除去やダストの除去、さらには傷の除去にも使われます。
紙やすりは使い分け方が重要で、湿式と乾式の違い、バックの耐久性、砥粒の保持力などが作業時間と仕上がりを左右します。材料や作業条件に応じて適切なグリットを選ぶことが、失敗を防ぐコツです。
使い分けのコツと具体例
実際の現場では、まず粗削り/中削り/仕上げの順にグリットを変えるのが基本です。木材の仕上げを想定した場合、最初は100番前後、中盤は180番、仕上げは320番〜600番程度を使い分けると良いでしょう。
塗装前の最終仕上げには、400番〜800番のフィニッシングペーパーを用いて表面の微細な傷を取り除きます。
実はこの段階が味の分かれ目で、ここでの滑らかさが塗装の密着とツヤの出方を大きく左右します。ダメな例として、粗めの紙やすりを塗装前に使い続けると、表面が荒れ、塗料の密着性が低下します。逆に、あまりに高番手だけを使いすぎると、作業効率が落ち、時間とコストが増えることもあるので、適切なバランスを保つことが重要です。
最後に、現場の実践的なコツとしては、軽い圧力で均一な動きを心がけ、磨く方向を木目に合わせると仕上がりが安定します。
また、湿式と乾式の使い分けを理解し、湿式は塗装後のボンドの密着性を高める場合に有用です。表面保護のためにマスキングテープや粘着剤が残らないよう、磨き終えた後の清掃を忘れずに行いましょう。
フィニッシングペーパーは、最終仕上げの要。友人とDIYの話をしていて、私は木材の箱作りで320番で下地を整えた後、800番で仕上げる工程をシェアしました。細かな傷を消してツヤを出すには、粒度のバランスが重要で、力を入れすぎると木目が潰れ、力を抜くと均一さが欠けます。フィニッシングペーパーは粒度のバランスと背地の材質、砥粒の粘りが大切だと気づきました。今度の休日には、家具の引き出しの仕上げに使って、滑らかな肌合いと均一なツヤを目指します。





















