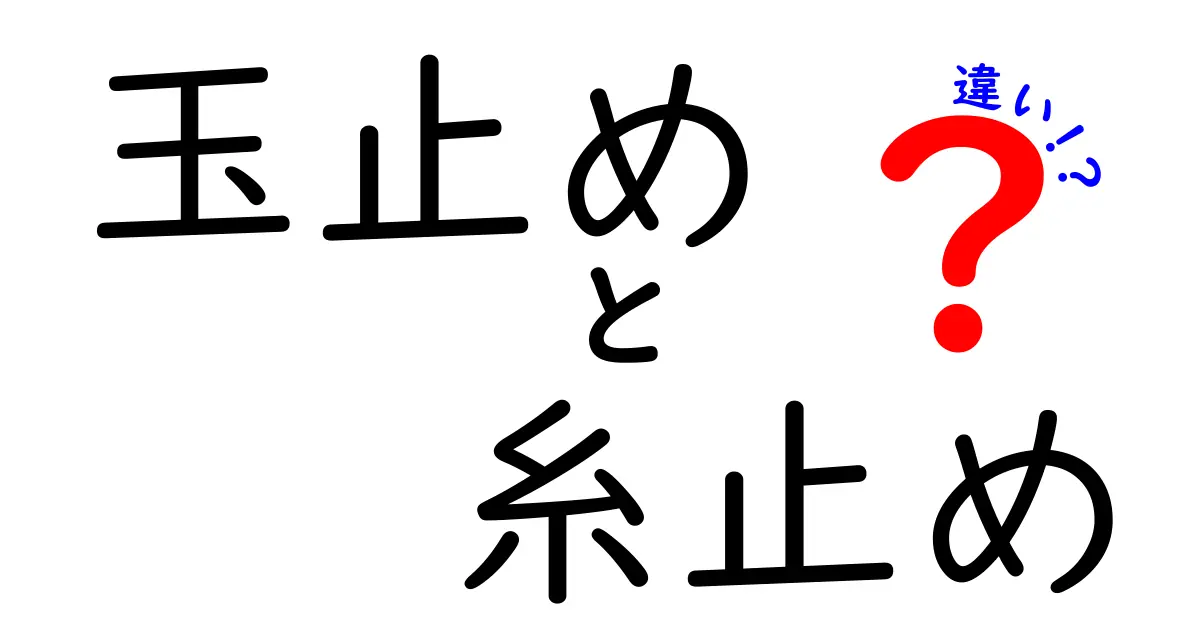

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
玉止めと糸止めの基本を解く
玉止めは、布の端を固定する最も基本的な結び目です。手芸では糸がほどけると作品の仕上がりが一気に崩れてしまうため、末端をしっかり止める技術を覚えることが大切です。玉止めの作り方はとてもシンプルで、糸を二、三回小さく巻いてから結ぶだけ。ただし玉の大きさを抑えるコツがあり、強く引きすぎると玉が大きくなります。反対に弱すぎると結び目が緩んでしまうため、指先の感覚を使って糸のテンションを調整する訓練が必要です。玉止めは主に端の処理に使われ、布の表面を傷つけずに仕上げることが重要です。布の種類によっては玉の見え方が違うので、綿糸と化学繊維では引く力の入れ方を微妙に変えると良い結果が出ます。なお糸止めと併用する場合もあり、作品のデザインや縫い方に応じて使い分けることが大切です。
もう少し詳しく見ると、玉止めは“末端の糸を確実に固定すること”が最も重要な目的です。末端がほどけると縫い目全体の強度が落ち、最悪の場合は縫い目の間から布地がほつれてしまうこともあります。そこで現場では玉止めを布の表面に出すかどうかを作風で決めることがあり、作品の雰囲気によっては玉止めを目立たせずに隠す工夫も必要です。こうした技術は最初は難しく感じますが、練習を積むうちに玉の大きさと結び目の位置をコントロールできるようになります。特に薄手の生地や伸縮性のある糸を使うと、玉の表情が変わるため、違う糸・布の組み合わせで小さな実験を繰り返すと理解が深まります。
使い分けと練習のコツ
糸止めは縫い目の終わりを確実に固定する技術で、玉止めより表に糸の結び目が目立ちにくい利点があります。実際の練習では、末端の糸を裏側に数回戻す戻し縫いを基本とし、最後に短い結びを作って固定する方法を覚えると良いでしょう。玉止めと糸止めを組み合わせる場面もあり、デザインの意図や布の種類に合わせて使い分けることが大切です。
練習のコツとしては、まず布の表側と裏側で糸の張り具合を均等に保つことです。片側だけ力を入れすぎると結び目が歪んだり、裏側の糸が布の下を傷つけてしまうことがあります。次に、針の角度と糸の出る位置を一定に保つこと。玉止めを行うときは玉の大きさを小さく抑える練習をし、糸止めを行うときは裏側での固定を徹底する練習を重ねます。最後に、手元のリズムを崩さないこと。テンポよく縫うと均一な仕上がりになり、時間をかけて練習しても手が疲れにくくなります。
この2つの技術は、手芸を長く続けるほど“補助的な相棒”のような役割を果たします。玉止めで端をしっかり固定できていれば縫い目全体の安定感が増し、糸止めで裏面まで丁寧に固定すれば耐久性が高まります。結局のところ、作品の目的と布の種類に合わせて最適な終わり方を選ぶ力を身につけることが、手芸の楽しさと完成度を高めるコツです。
koneta: 学校の授業で玉止めと糸止めを学んだときの雑談を思い出します。友だちのAは「玉止めは小さく、末端をしっかり固定するコツが大事」と言い、友だちのBは「糸止めは裏側の固定を丁寧にするのが基本」と教えてくれました。私が初めは玉止めの玉が大きくなってしまって恥ずかしかった話をすると、二人は笑いながら「焦らず、玉の大きさを意識して練習を重ねれば必ず上手になる」と励ましてくれました。その日以来、玉止めと糸止めを別々の場面で使い分ける練習を続け、布の厚さや糸の太さによる変化にも敏感になりました。結局、技術は科目のような正解があるわけではなく、実践で体に染み込ませるものだと感じています。
前の記事: « 上絵と下絵の違いを完全ガイド|初心者にも分かる描法と用途の違い





















