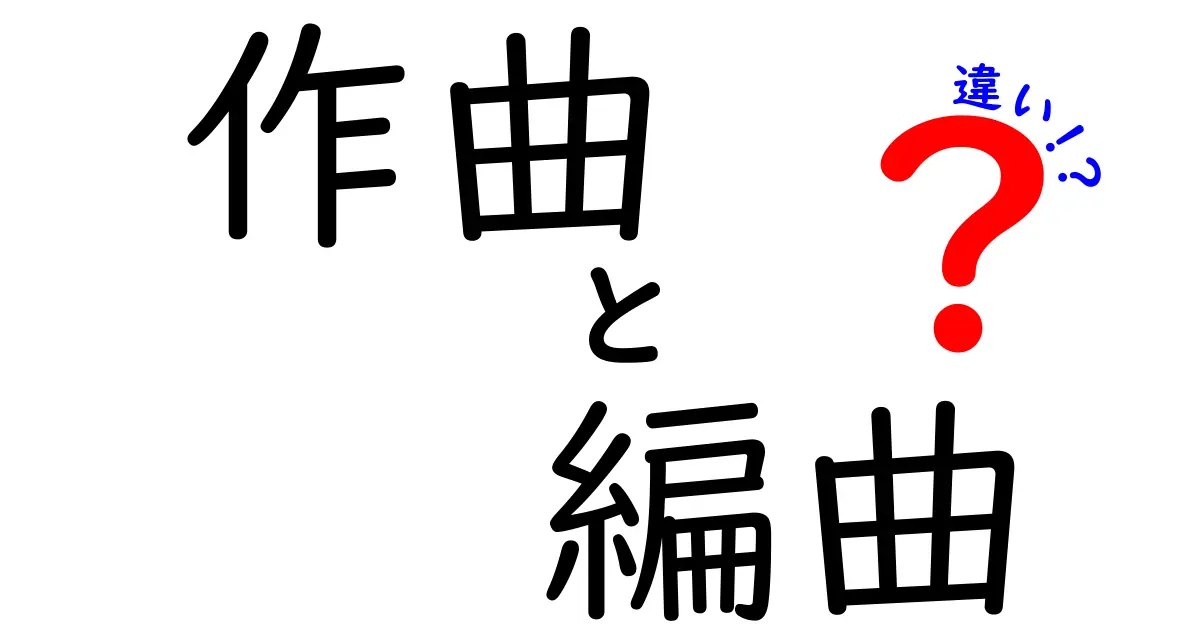

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
作曲とは何か—新しい音楽を生み出す創造の作業
音楽にはよく 作曲 と 編曲 という言葉が出てきます。違いがわかりにくい人も多いですが、実は役割がはっきりと分かれており、音楽ができあがる過程で別の仕事をします。ここでは中学生にも分かるように、作曲と編曲の違いを丁寧に解説します。まず作曲とは、新しい曲のアイデアを生み出す作業です。メロディや和音、リズム、曲の雰囲気など、曲の核となる要素を一から考え出します。作曲には創造性が大きく影響し、聴く人の心に響く新しい音楽を生むための発想力や感性が問われます。
このセクションでは、作曲の基本プロセスを順を追って見ていきます。まず、どんな曲にしたいのかという“意図”を決めます。童謡のような明るい曲、学校の合唱コンクール用の力強い曲、映画のワンシーンを盛り上げるサウンドトラックのような雰囲気――こうした意図を固めるところから作曲は始まります。次に“主旋律”となるメロディを作ります。メロディは音の高さと長さを組み合わせて、耳に残るフレーズを作る作業です。メロディができたら和音の組み合わせを決め、曲のハーモニーをどう支えるかを考えます。和音は音の色のようなもの。明るい響き、切ない響き、力強い響きなど、曲の物語をどう表現するかが鍵になります。これらを決めることで、曲の“骨格”ができあがります。最終的には楽譜に起こして、演奏者が読むことができる形に整えます。ここまでが作曲の基本的な流れです。
次に、実際の音を形にする作業として、主旋律を作ります。主旋律は聴く人の耳に最初に触れる部分で、語り口のように流れる長い線、あるいは短い連続のフレーズとして楽器にのせます。続いて和音の組み合わせ、つまり曲全体の和声を考えます。和音の選び方ひとつで、曲の印象は大きく変わります。明るく軽快な曲には跳ねるリズムと短い和音、悲しく深い曲には長い音価と重い和音が似合います。ここまでの作業は、音楽の“身体”を作る段階です。
最後に、曲の構成を決めていきます。イントロ・Aメロ・サビ・ブリッジなど、曲の流れを考え、聴く人が自然と話を追えるように設計します。テンポや調性の変化も計画します。描いたアイデアを楽譜に正確に書き起こせば、演奏者が理解できる形になります。作曲は、頭の中のイメージを音として表現する作業なので、何度も試しては直し、いい音の関係性を見つける過程が長くなりがちです。
このように、作曲は新しい音楽の「設計」となり、編曲はその設計を楽器や演奏家に合わせて「形」にする作業です。次のセクションでは、編曲の役割と具体的な作業内容について詳しく見ていきます。
作曲と編曲の違いを理解することで、音楽の制作過程が見えてきます。
編曲とは何か—音を形にする作業
編曲は、すでにできている曲を“別の人が演奏してもその曲らしく聴こえるよう”に整える作業です。例えば、ピアノだけで弾く曲を、ギターとベース、ドラムスと管楽器でも聴けるようにアレンジすることを指します。編曲には、楽器の音域、音色、ダイナミクス、テンポの変更、リズムの微調整、パートの割り当てといったさまざまな技術的要素が含まれます。
演奏する楽団や歌手の人数、音楽ジャンル、聴く人の年齢層に合わせて、最適な編成を決めます。編曲を上手に行うと、同じ曲がまったく違う印象になります。例えば、同じ童謡をオーケストラ風にすると壮大で感動的になり、小編成のポップスにすると軽快で現代的な感じになります。これを理解すると、音楽制作の幅がぐっと広がります。
編曲の具体的な作業は以下のように分かれます。まず楽曲の“目的”を再確認します。次に楽器編成を決め、各楽器にどのパートを割り当てるかを決定します。これにより、誰が何を演奏するかが決まります。続いて、各パートの音量バランスを設計します。どの楽器を強調するべきか、どの楽器を控えめにするかを決め、全体のサウンドのイメージを整えます。音色の選択も重要です。例えばアコースティックギターとチェロは暖かい響きを作り、シンセサイザーは未来感を出すことができます。テンポの微調整や、曲の途中でのダイナミクスの変化を追加することもあります。最後に、実際の演奏に合わせて楽譜を更新し、演奏者が読みやすい形に整えます。
- ポイント1: 編曲は曲の“現代性”や“実用性”を決める仕事です。
- ポイント2: 関係する楽器の特性を理解することが、良い編曲のコツです。
- ポイント3: もとの曲の雰囲気を壊さず、別の形で伝える工夫が求められます。
編曲は作曲の成果物を“現場で生きる音”にする技術です。この理解が深まると、演奏会での表現力が大きく変わります。
編曲についての小ネタをひとつ。たとえば同じ曲を雰囲気だけ変えたいとき、編曲は魔法のように働きます。前は軽快でポップな感じだった曲を、ギターとドラムだけのアレンジにすると、同じ歌詞でも聴く人は新鮮さを感じ、時には子ども向けの楽しい印象から大人向けの落ち着いた雰囲気へと変わります。友だちと雑談するように考えると分かりやすいです。どの楽器をどのように強調するか、どのパートを削ってどう組み合わせるか。編曲は“音の設計図”を現場の演奏に適合させる作業で、作曲のアイデアを生きた音楽へとつなぐキーパーソンです。





















