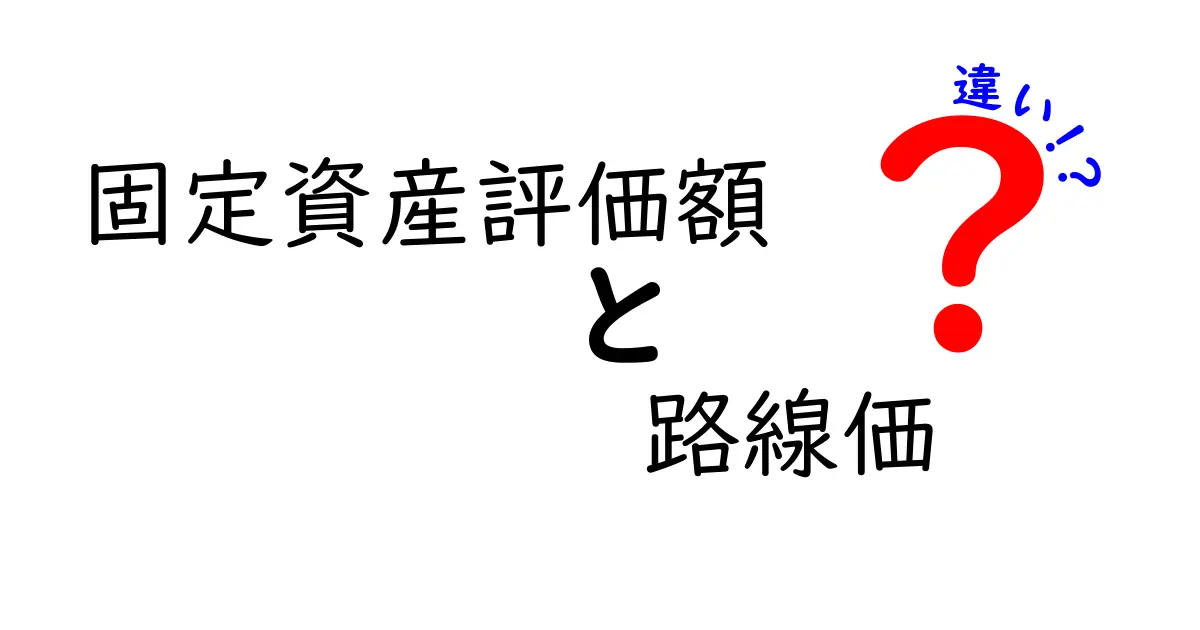

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
固定資産評価額と路線価の基本的な違いとは?
固定資産評価額と路線価は、どちらも土地や建物の価値を示す数字ですが、使われる目的や計算方法が異なります。
まず、固定資産評価額は主に固定資産税や都市計画税などの税金を計算するときに使われる評価額です。これは市区町村の役所が決める評価額で、現時点の土地や建物の価値を元に算出されます。
一方、路線価は主に相続税や贈与税の計算の基準になる土地の価格です。国税庁が毎年発表し、道路ごとに価格がつけられているため「路線価」と呼ばれます。
このように、どちらも土地の価値を示しますが、税金の種類や評価方法が違うのがポイントです。
固定資産評価額の特徴と計算方法
固定資産評価額は、市町村の担当者が現地調査や周辺の取引事例を参考にして決めています。土地だけでなく建物も評価対象です。
具体的には、その土地が持つ面積や場所、利用状況などを考慮して実勢価格の70%程度を目安に評価されることが多いです。
この評価額は3年ごとに見直されるため、毎年同じとは限りません。
固定資産税はこの評価額に税率をかけて計算されます。つまり、評価額が高いと納める税金も多くなる仕組みです。
使いみちは主に地方自治体への税金計算で、国の税金計算には使われません。
路線価の特徴と計算方法
路線価は、国税庁が道路ごとに定める1平方メートルあたりの土地価格です。
主に相続税や贈与税の基準となり、土地の相続や贈与が発生したときの課税対象金額を算出するために使われます。
路線価は周辺の取引価格や地価公示価格を元に決まっており、一般に実勢価格の80%程度となることが多いです。
路線価は毎年発表され、道路ごとに細かく設定されています。
また、路線価が設定されていない地域では固定資産評価額を基準に計算されることもあります。
固定資産評価額と路線価の違いを比較表でまとめると
| 項目 | 固定資産評価額 | 路線価 |
|---|---|---|
| 目的 | 固定資産税・都市計画税の計算 | 相続税・贈与税の計算 |
| 評価者 | 市区町村の職員 | 国税庁 |
| 評価基準 | 実勢価格の約70% | 実勢価格の約80% |
| 更新頻度 | 3年ごと | 毎年 |
| 適用地域 | 全国 | 主に路線価が設定されている地域 |
このように、同じ土地でも固定資産評価額と路線価は金額が異なり、使う目的も違うことがよく分かります。
そのため、税金の計算をするときは用途に応じた数字を使うことが大切です。
路線価の面白いところは、毎年道路ごとに価格が決まっていることです。つまり、同じ町の中でも道によって土地の値段が違うので、
その道に面しているかどうかで土地の評価が変わります。
これは不動産の価格を公平に評価するためにとても便利な方法ですが、一方で道の価値が土地の価値に大きく影響するということも意味しています。
道路のアクセス状況や賑わい具合が評価に直結する、まさに都市計画の視点も反映された数字なんです。
路線価をみるときは、『土地の場所だけでなく道路の価値も加味されている』と考えると面白いですよ。
前の記事: « 「所有権者」と「所有者」の違いとは?わかりやすく解説!





















