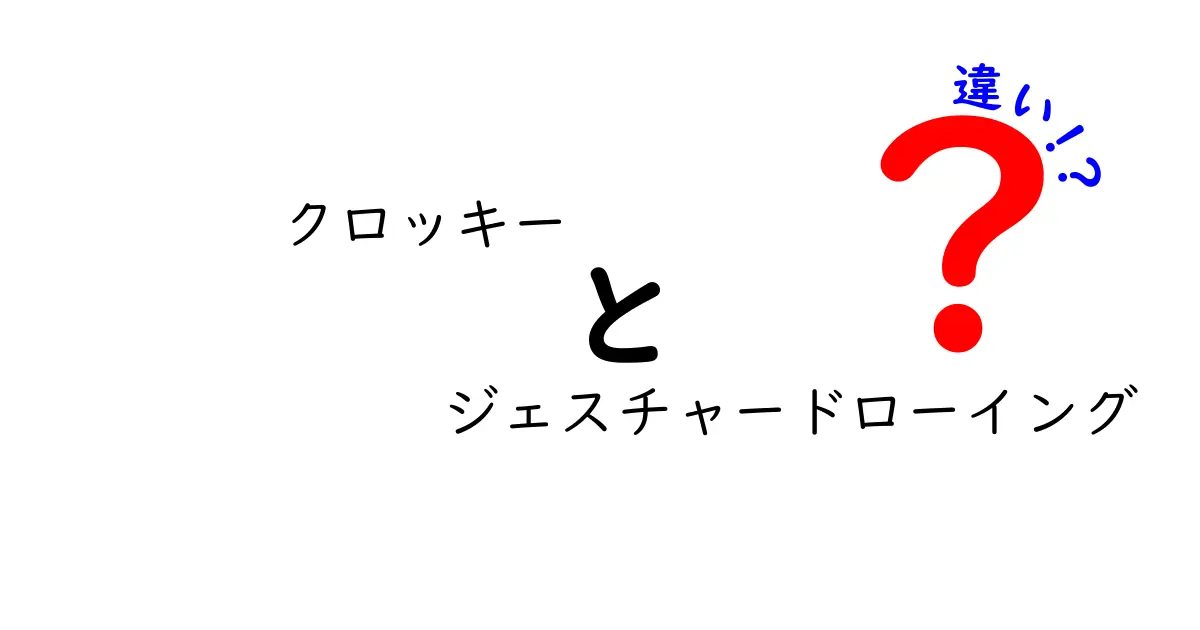

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クロッキーとジェスチャードローイングの基礎
クロッキーは、人物や物体を短時間で描く練習のことを指します。通常は1分程度の短い時間で、輪郭や大まかな姿勢だけを捉えます。目的は、対象の「形のクセ」や「動きのリズム」を把握することにあり、細部にこだわらず、全体の印象を素早く描く力を養います。ジェスチャードローイングは、同じく速く描く技法ですが、クロッキーよりも動きを強調します。線の勢い、体の重心の移動、ポーズのダイナミックさを表現することが多く、観察する点が若干広くなります。初心者はまず、鉛筆を軽く走らせ、線の太さや濃さを調整せずに、連続して動きを描く練習をします。
この二つを混同しやすい理由は、どちらも“短い時間で描くこと”を共通の軸としているからです。ですが、実際には狙っている情報の優先順位が少し違います。クロッキーは「形の連続性と安定感」、ジェスチャーは「動きとリズムの表現」を重視します。
この違いを理解すると、同じ紙と鉛筆でも、描く目的に合わせて道具の使い方を変えるだけで、仕上がりの印象が大きく変わります。最後に、実践に入る前に準備運動として、指のストレッチや腕を回す動作を3分ほど行うと、筆の動きが滑らかになります。
違いのポイントを詳しく比較
ここでは、クロッキーとジェスチャードローイングの“何を描くのか”と“どう描くのか”の違いを、具体的な例を使って説明します。まず目的の違いです。クロッキーは、人の姿勢や動きの連結を意識して形の連続性と安定感を養う練習で、動きを最小限の線でつなぐ技術を磨きます。一方ジェスチャーは、動作中のエネルギーや体のバランス、流れを重視します。描く対象は、同じ人物でも、走っている場面、跳んでいる瞬間、あるいは日常のポーズなど、動きを伝えることに適した場面が選ばれます。線の性質にも違いがあります。クロッキーは、直線と曲線を組み合わせ、ぬりつぶしではなく薄くシャープな線で輪郭をつくる練習が多いです。ジェスチャーは、勢いのある長い一筆や、連続的な動きを表すダイナミックな線を重ねることが多く、筆圧を変えながら「生きた線」を追い求めます。道具選びも簡単には終わりません。シャープな鉛筆やHB以上の硬さの多用、またはボールペンやペン系で速さを優先するか、紙質にも影響します。こうした差を理解することで、練習の目的に合わせて訓練メニューを組み立てられます。今回の表では、ポイントを分かりやすく整理しました。
表の後には、実際の練習計画を立てるためのヒントがあります。まずは、1日10分程度からスタートするのが無理なく続けられるコツです。続けるうちに、時間を逐次短くしていくか、観察する対象を変えるか、場所を変えるかで、自然と eyes-hand coordination が高まります。視点を変えることは、同じ人物でも全く違う印象を生み出すので、友達と一緒にお互いを撮影して、描いたポーズと現実のポーズを比べる遊びをするのも効果的です。最後に、日常の中で“動きの瞬間”を見逃さない習慣をつけましょう。走っている子ども、跳ねている犬、風を受ける木の葉など、動きの断片を見つけて、それを短く描く練習を繰り返すと、自然とジェスチャーの感覚が身につきます。
実践のコツと事例
実践のコツは、まず短い時間から始め、徐々に難易度を上げていくことです。練習メニューの基本は、日替わりで「観察・描画・振り返り」を繰り返す形式。観察では、対象を決めずに“印象”を掴むことを意識します。描画は、最初の数秒で体の大きなポーズを捉え、その後すぐにラインを追加します。振り返りでは、描き上がった絵と実際のポーズを比べ、どの部分が近いか、どの部分がズレていたかをノートに記すと良いです。実践例として、5分の練習を3セット、各セットで最初の1分は対象の全体像を捉え、次の2分で細部の補足をします。次の日は、別の対象にチャレンジして、同じ手順を繰り返すと、描くスピードと観察の質が自然と向上します。ポイントは「動きの連続性を意識すること」と「線の勢いを保つこと」です。若干のブレや失敗は成長の証であり、恐れず試していく姿勢が大切です。現場のリアルな体験として、学校の課題では友達とペアになり、互いの絵を批評し合う時間を作ると、他者の視点を取り込む力が高まります。こうした具体的な取り組みを習慣化すると、クロッキーとジェスチャーの両方で、描く技術が自然と深まります。
ねえ、さっきの記事を読んで気づいたんだけど、ジェスチャードローイングの“動きの表現”には、ただ速く描く技術だけでなく、観る側に“今この瞬間のエネルギー”を感じさせる工夫が必要だよね。例えば、同じポーズでも、足の位置や腰のねじれ、肩の角度をわずかに変えるだけで全然違う印象を作れる。これを小さな変化として捉えると、練習の幅がぐんと広がる。僕は、1日5分だけでも“動きの連続性”を意識して線をつなぐ時間を作るようにしている。最初は線がぶれてもいい。大事なのは“次の一線へ、前の動きをつなぐ”という感覚を体に覚えさせること。
次の記事: 数独 数解 違いを徹底解説!初心者にも分かるポイントと勘所 »





















