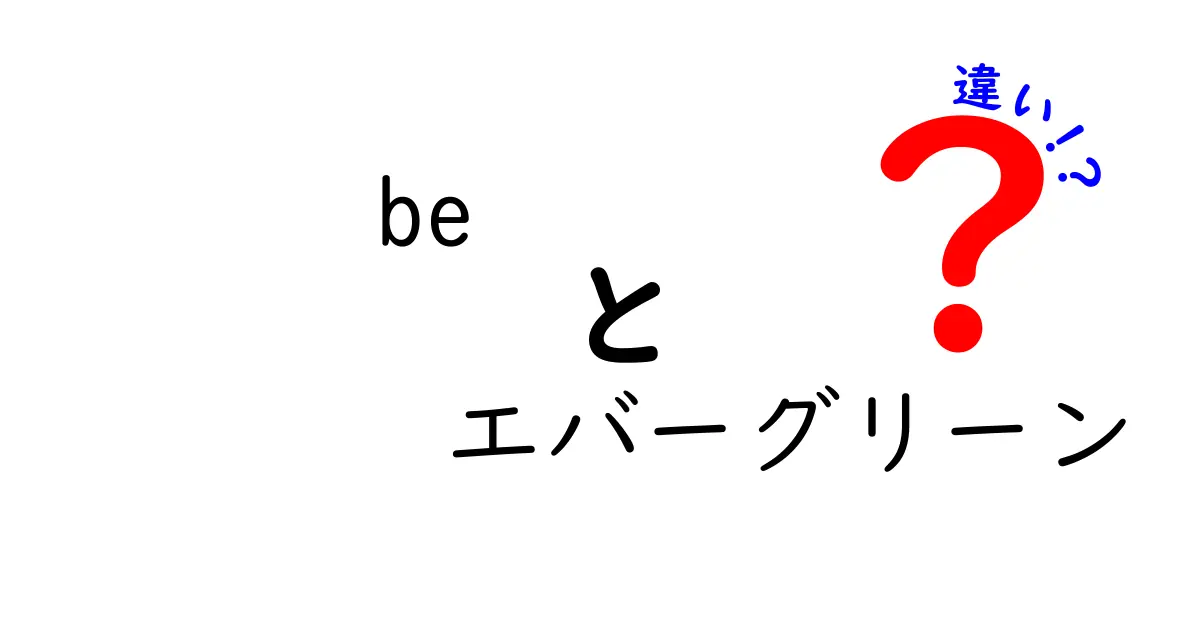

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
beとエバーグリーンの違いを理解する基本ポイント
まず初めに押さえておきたいのは、beとエバーグリーンは全く別の領域の言葉だという点です。
beは英語の基本動詞のひとつであり、存在・状態・性質を表します。日本語に直すときは「〜である」「〜にいる」といった意味として使われ、文法的な形が主に重要になります。現在形・過去形・未来形など、主語に合わせて形を変えるのが特徴です。
一方、エバーグリーンはマーケティング用語として生まれた概念で、長い時間をかけても価値が落ちにくい情報やコンテンツを指します。
この二つは使われ方・目的が違いますが、実際の文章作成や説明の場面では混同されがちです。ここからは両者の違いを具体的に整理していきます。
違いの核は「文法の要素か、情報の長寿命を示す概念か」という点です。
以下の表と例を通して、日常の文章づくりや発信の場での適切な使い分けを学びましょう。観点 be(文法) エバーグリーン(コンテンツ戦略) 役割 動詞として状態や存在を表す 長期的に価値が続く情報を指す概念 対象 文法・語形変化・時制 情報の持続性・再利用性 用途の場 英語の学習・文章の成立 ブログ・教材・Webページの長寿命化
まとめ:beは言語の基本構造を支える動詞、エバーグリーンは情報の寿命と価値を示す概念。この二つを混同せず、文法と情報設計のそれぞれの場面で適切に使い分けることが、伝わる文章と長く読まれるコンテンツづくりの鍵になります。
beとエバーグリーンを区別して考える練習として、身近な例をいくつか挙げておくと良いでしょう。例えば、会話の中で「私は学生です」という文はbe動詞を使う典型例です。一方で、学校の部活動についての説明記事を作るときには、エバーグリーン要素を取り入れて、数年後も読まれる情報になるよう構成します。
この章の要点を短く整理します。
・beは文法の基本動詞で、現在・過去・未来の表現を担う。
・エバーグリーンは情報の価値が長く続くことを意味する概念。
・文章作成では、文法と情報設計を混同せず、それぞれの目的に合わせて使い分けることが重要。
・表のような構造化された情報を活用すると、理解が深まりやすい。
・適切な例文と長期的な視点を組み合わせると、読む人に伝わりやすくなる。
日常会話と情報発信での使い分け
日常会話ではbe動詞を自然に使う場面が多く、“〜です”“〜しています”といった表現の基盤になります。反対に情報発信ではエバーグリーンの考え方を活かして、今だけの流行に頼らず、長期間価値を持つ内容を組み立てることが求められます。
例えば、日常会話でのbeの使用は「私は日本人です」「彼は先生です」といった具合に、相手へ確実に状態を伝える役割があります。一方でエバーグリーンを意識した記事作りでは、時間が経っても役立つ情報を提供することを目指します。
この差を日常の文章づくりに取り入れると、読み手にとって分かりやすく、長く役立つコンテンツへとつながります。
また、表や図を使って要点を整理すると、学習の効率が上がります。前述の table で紹介したように、beとエバーグリーンは役割が異なるため、同じセクション内で混ざらないよう区別して扱いましょう。
読み手がすぐに理解できるよう、具体例と共に、短く要点を並べる練習を重ねると良いでしょう。
このような整理は中学生でも取り組みやすく、文章力の向上にも直結します。
最後に、実践のコツとして「まず要点をリスト化 → 具体例を添える → 長期的な視点を補足」と進めると、beとエバーグリーンの両方を自然に使い分けられるようになります。
この基本を押さえておけば、日常の会話だけでなく、授業のレポートや部活動の説明文にも自信を持って臨めます。
ねえ、エバーグリーンって言葉、堅苦しく感じるかもしれないけれど、実は私たちの話し方にも深く関係しているんだ。友だちと話すとき、話題が長く続くかどうかを気にすることってあるよね。エバーグリーンの考え方を取り入れると、話題を長く引っ張るのではなく、内容を「長く使える形」で伝える練習になる。例えば、部活の紹介や学校行事の説明は、一度作っておけば何年も役立つエバーグリーン素材になりうる。逆に流行の話題は時期が過ぎると価値が落ちやすい。だから、雑談やプレゼンをする時には、エバーグリーンを意識して「普遍的な情報」を中心に据えつつ、必要に応じて時事的要素を添えると、伝わりやすさが格段に上がる。be動詞の基本を押さえつつ、エバーグリーンの発想で話の構成を考えると、相手の理解が深まり、後からでも読み直せる文章が生まれるんだ。こうした組み立ては、中学生の君たちにも日常の学習や発表で活かせる。





















