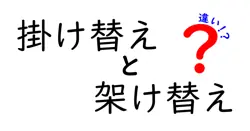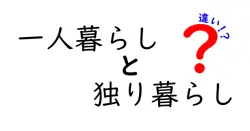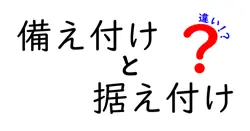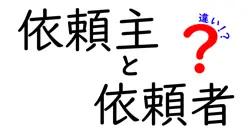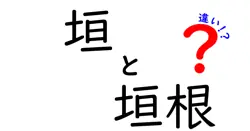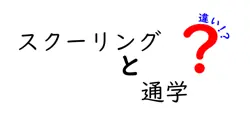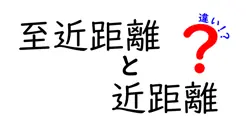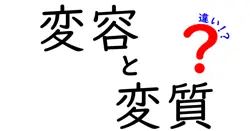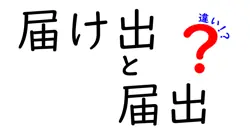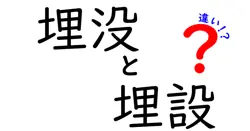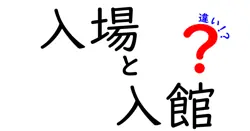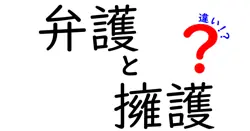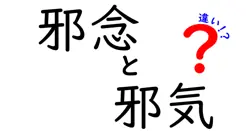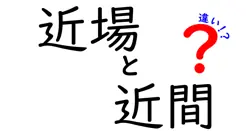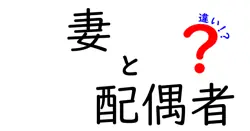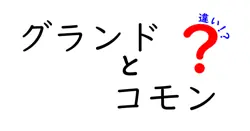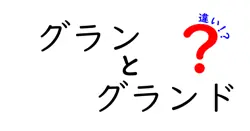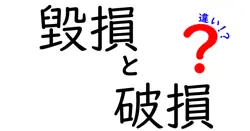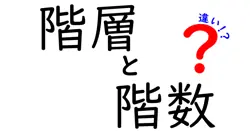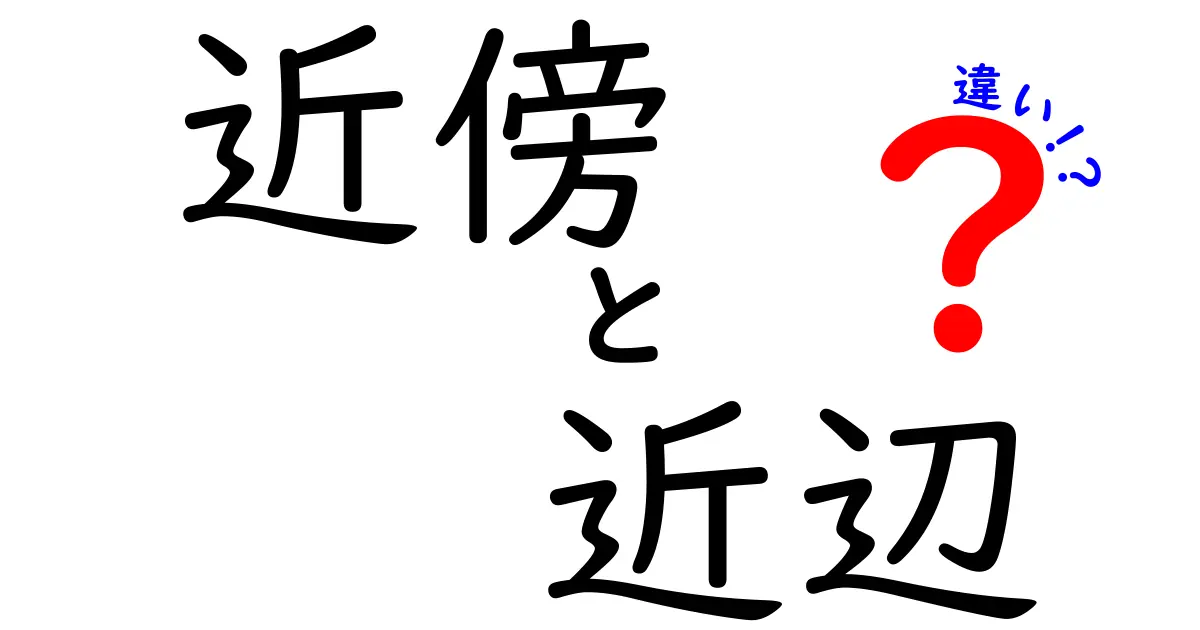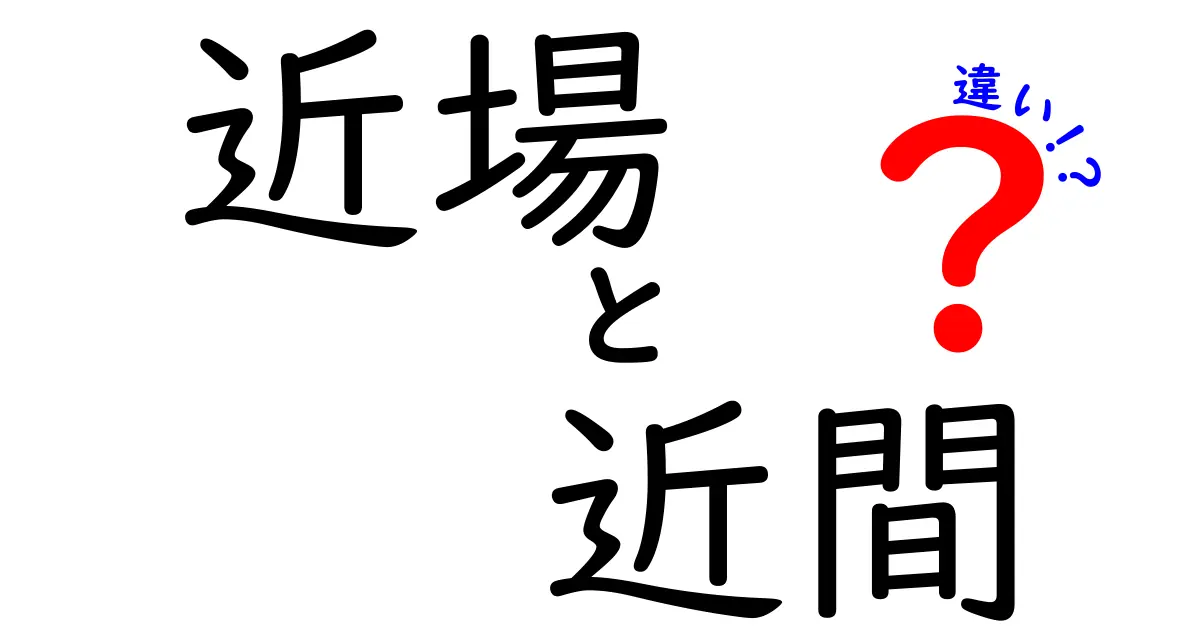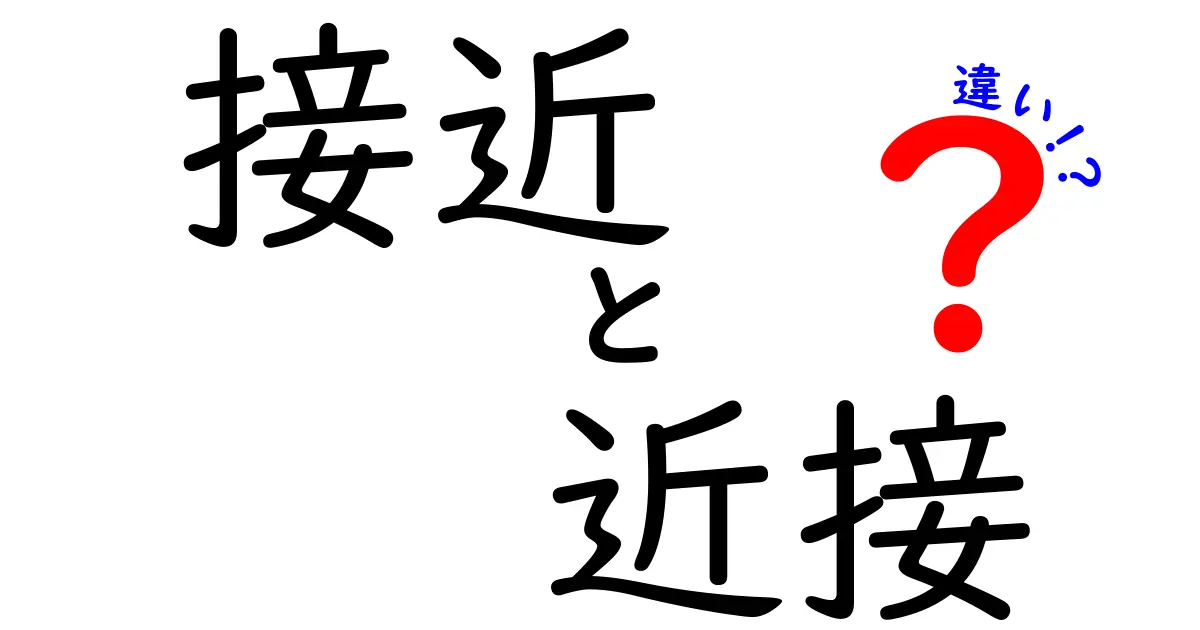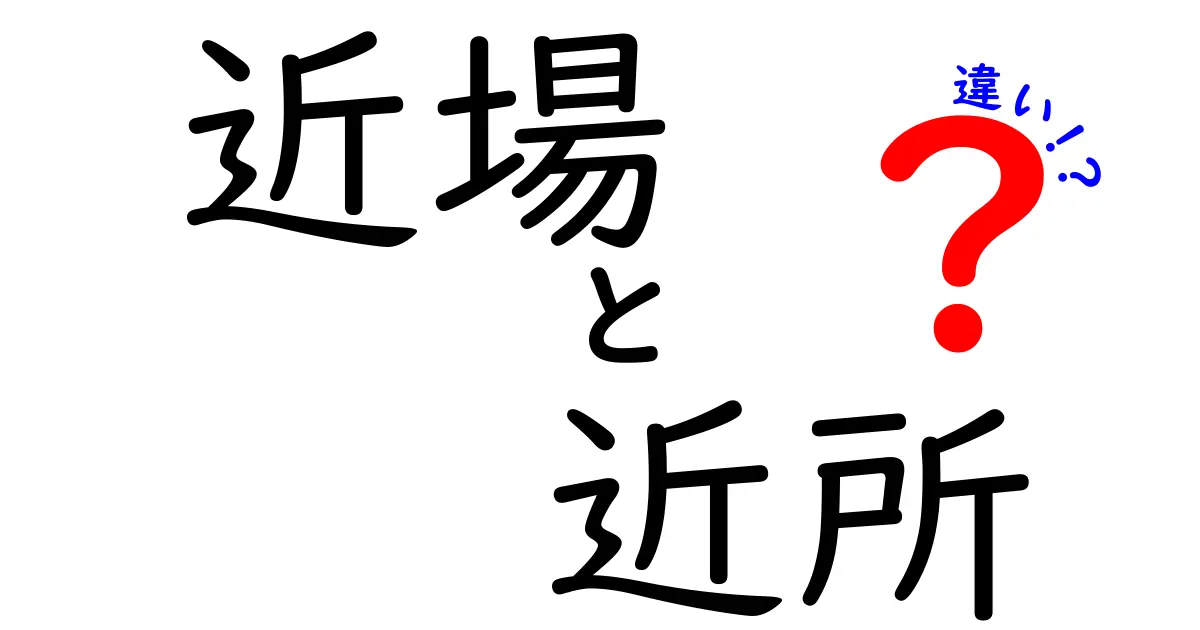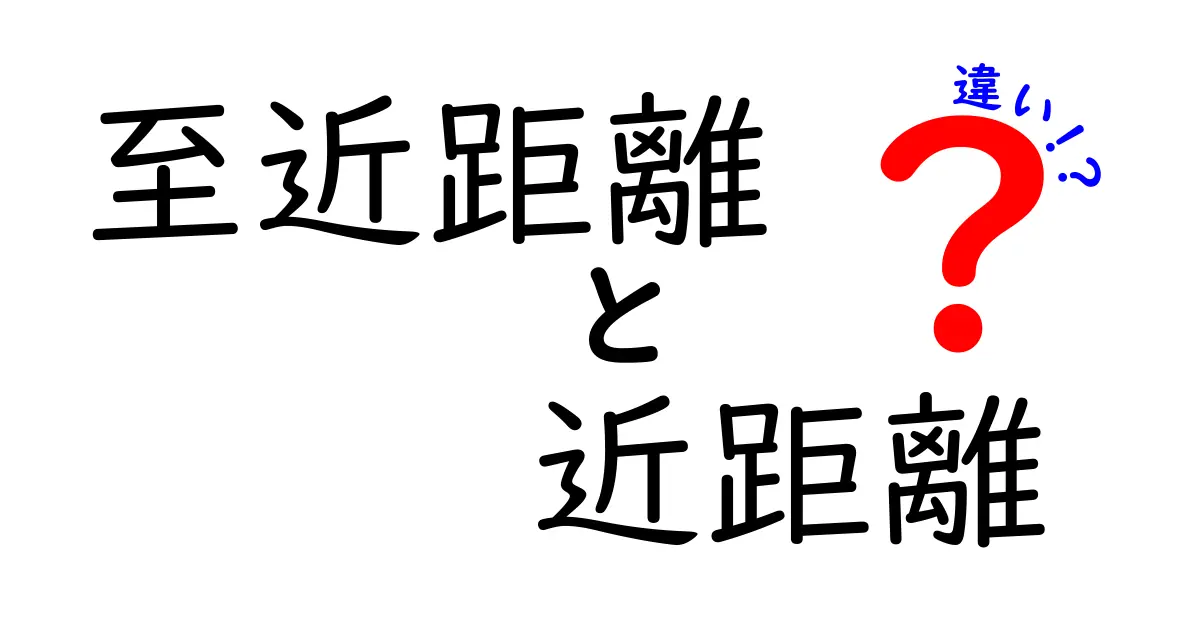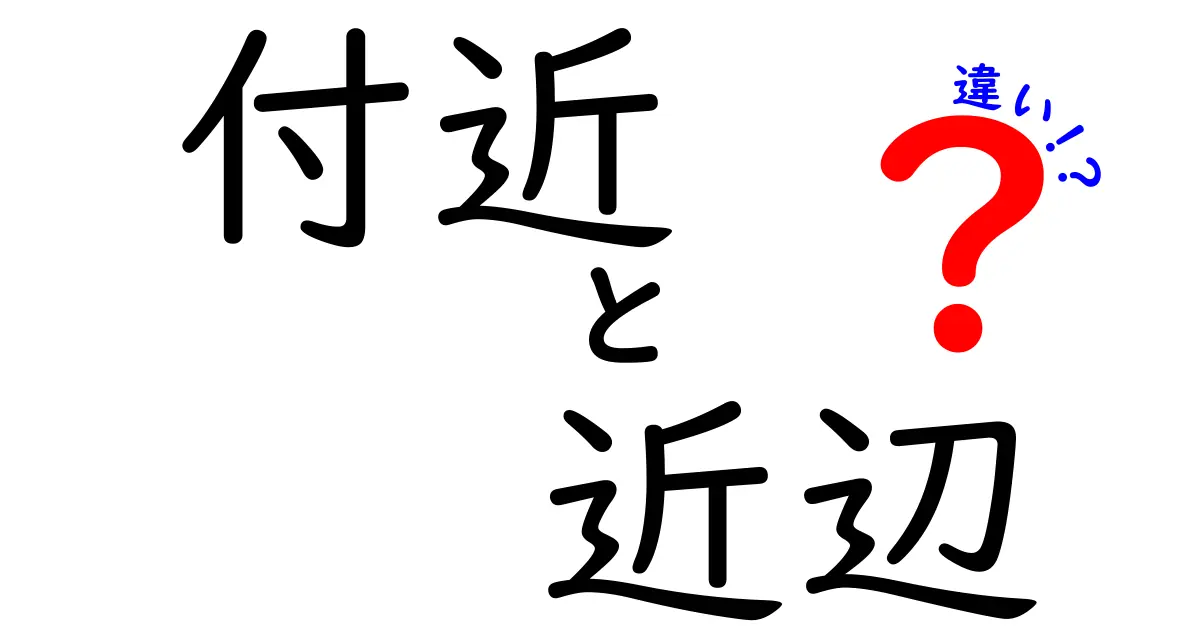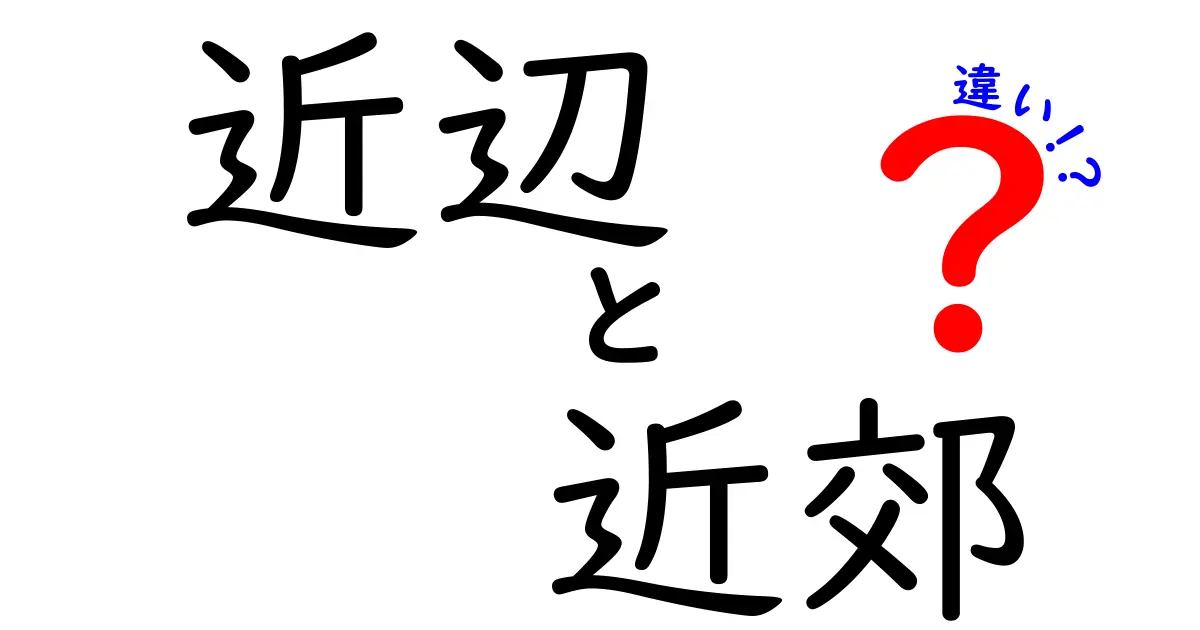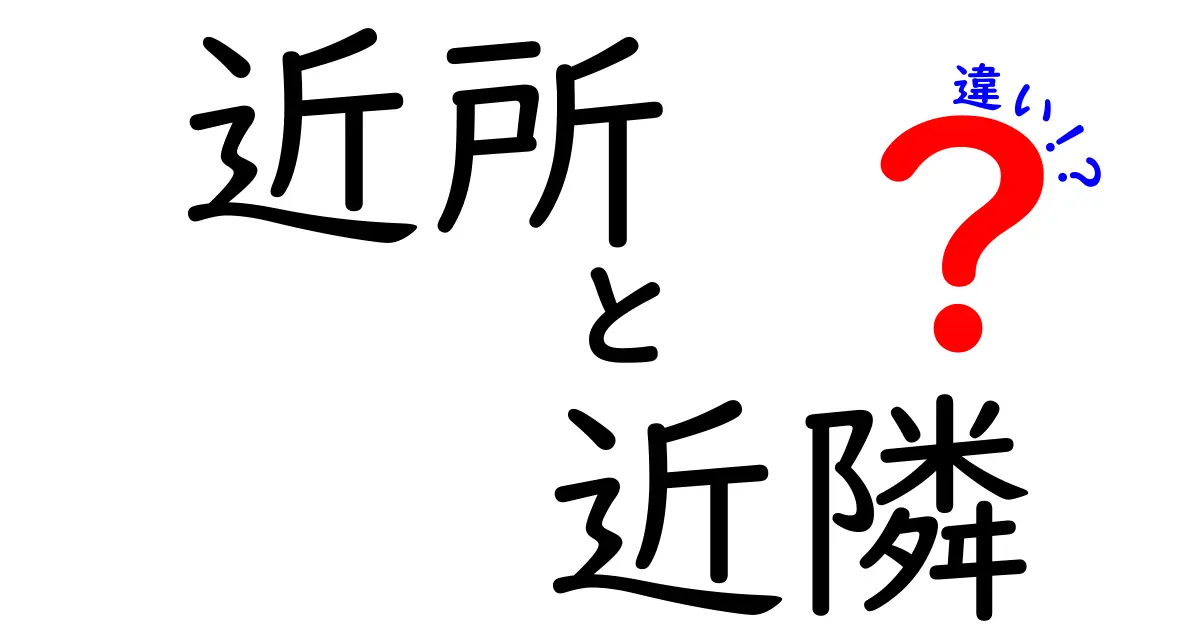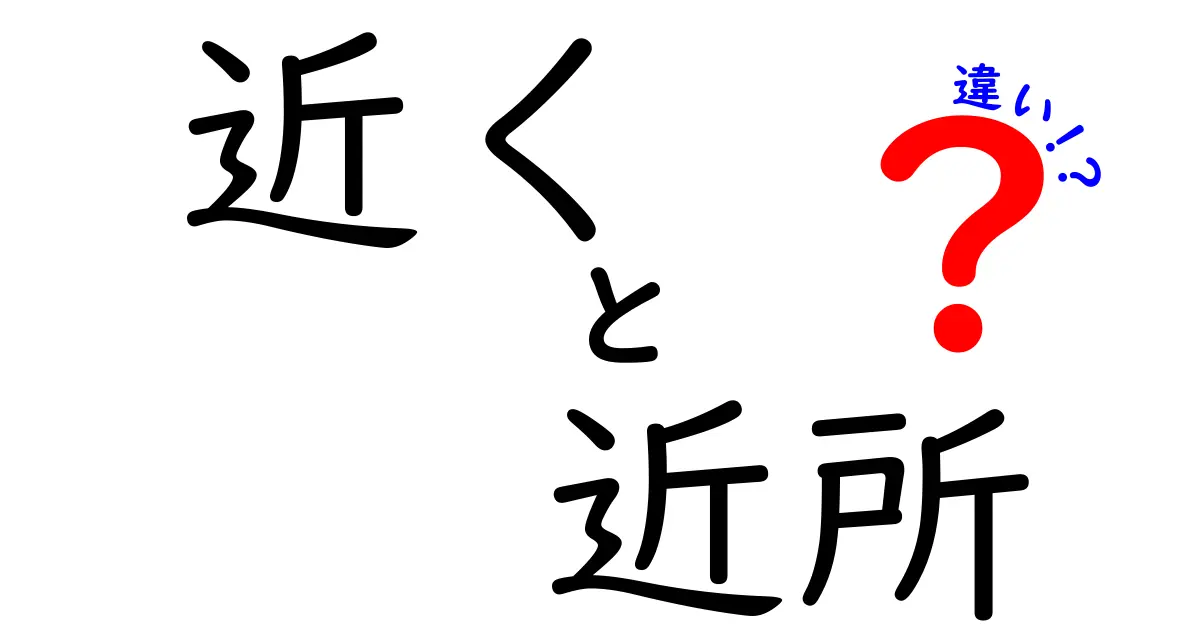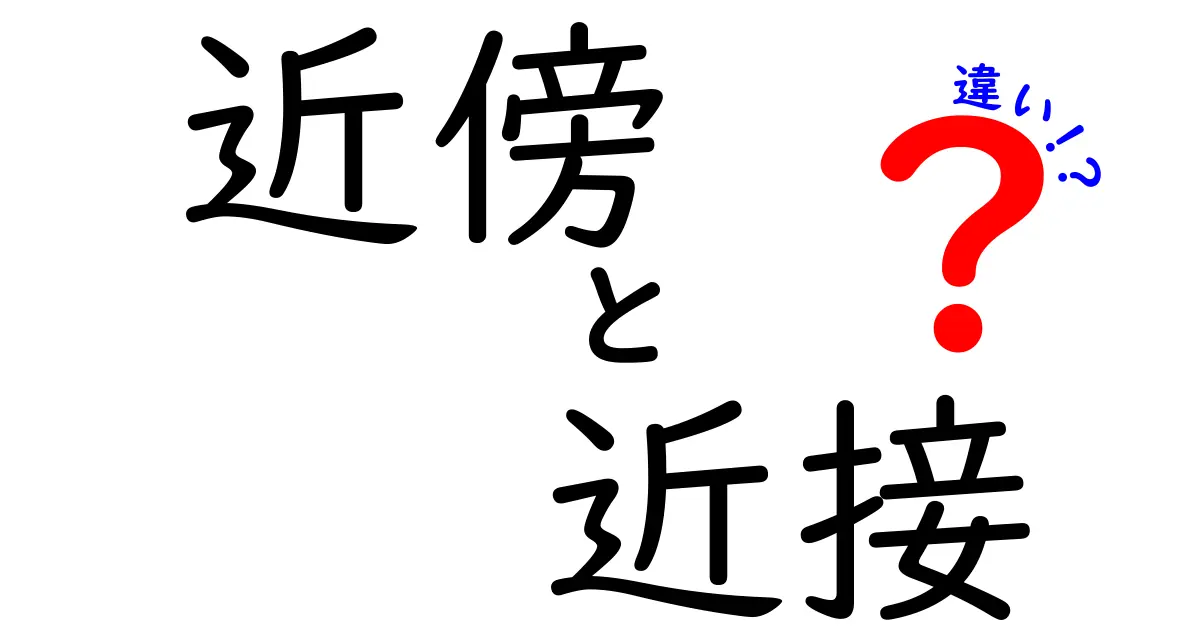
「近傍」と「近接」の意味の違いとは?
日本語には似たような言葉がたくさんありますが、その中でも「近傍(きんぼう)」と「近接(きんせつ)」はよく使われる割に意味がわかりづらい言葉の一つです。
まず、「近傍」とは「あるものの近くにある場所や物」のことを指します。数学や統計学の世界では、特定の点の周りにある範囲や集合を意味することも多いです。
一方、「近接」は「物理的に非常に近いこと」「接近していること」を表します。つまり、何かと何かがくっつきそうなくらい近い状態を示しているのです。
このように、どちらも「近い」という意味を持っていますが、「近傍」は範囲やエリアを示し、「近接」は距離や接触状態を強調しているという違いがあります。
日常生活での「近傍」と「近接」の使い分け方
日常会話では「近傍」という言葉はあまり使われず、「近く」や「周辺」といった言葉に置き換えられることが多いです。たとえば、「駅の近傍の店」というより「駅の近くの店」と言う方が自然ですね。
それに対して「近接」は、「家と学校は近接している」というように、場所と場所が物理的に非常に近いことを強調したいときに使います。
たとえば、新しくできたスーパーが学校の近接地にあると言えば、「すごく近い」と伝えたい場合です。ですが、「駅の近傍のスーパー」は「駅の周辺にある」という少し幅広い意味になります。
つまり、「近傍」は広い範囲の近く、「近接」はピンポイントで非常に近いことを示すのがポイントです。
専門分野での「近傍」と「近接」の違い
数学やIT分野においては「近傍」と「近接」はさらに使い分けられています。
「近傍」は、例えばコンピューターのアルゴリズムで「ある点を中心にした範囲」や「その範囲に入る点の集合」を表現するのに使われます。具体的には、画像処理でピクセルの近傍を調べてノイズを取り除いたりする際に使う言葉です。
一方、「近接」は通信技術などで「近接通信(NFCなど)」と呼ばれるように、端末同士が非常に近い距離で情報をやり取りすることを意味します。
「近傍」と「近接」の違いのまとめ表
| 用語 | 意味の範囲 | 使われる場面 | 強調するポイント |
|---|---|---|---|
| 近傍(きんぼう) | ある点や場所の周辺、範囲 | 数学・統計・日常での「近くの範囲」 | 場所や範囲の近さ |
| 近接(きんせつ) | 物理的に非常に近い状態 | 日常会話・通信技術など | 距離の近さや接触の可能性 |
このように、「近傍」と「近接」は似ているようで、意味や使う場面に違いがあることを覚えておくと、言葉選びがスムーズになります。
これからは「近傍」と「近接」の違いを意識して、正しい使い方を実践してみてくださいね。
「近傍」という言葉は数学の世界でよく使われますが、実は直訳すると「近くの周辺」というとても広い意味を持っています。でも面白いのは、コンピューターの画像処理では、あるピクセルの近傍だけを調べてノイズを除去したり加工したりすることができるんです。つまり、目には見えない小さな範囲での“近い領域”を扱っているんですね。身近なところで意外に応用がきく言葉なんですよ。
次の記事: 「付近」と「辺り」の違いとは?意味や使い方をわかりやすく解説! »