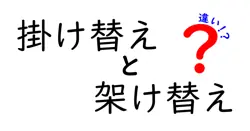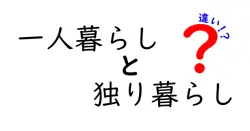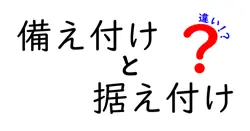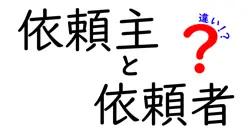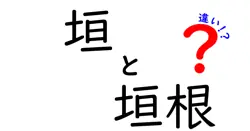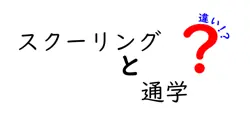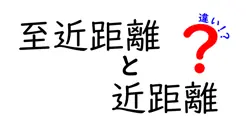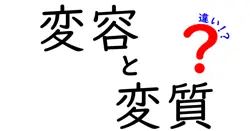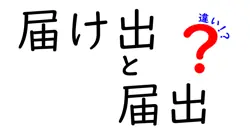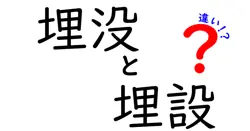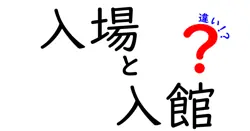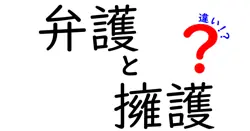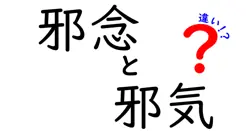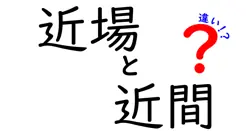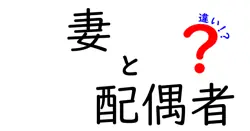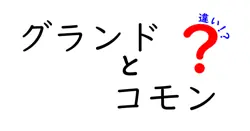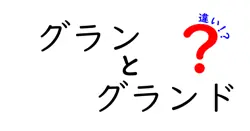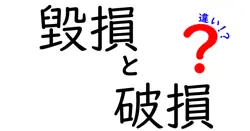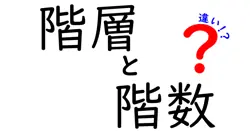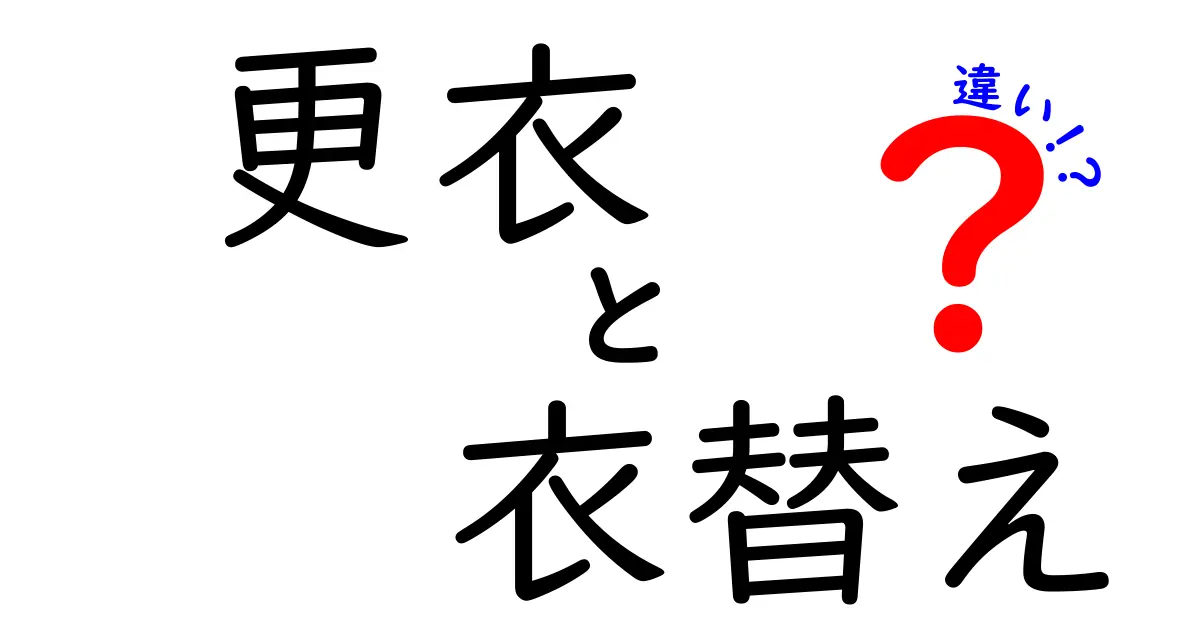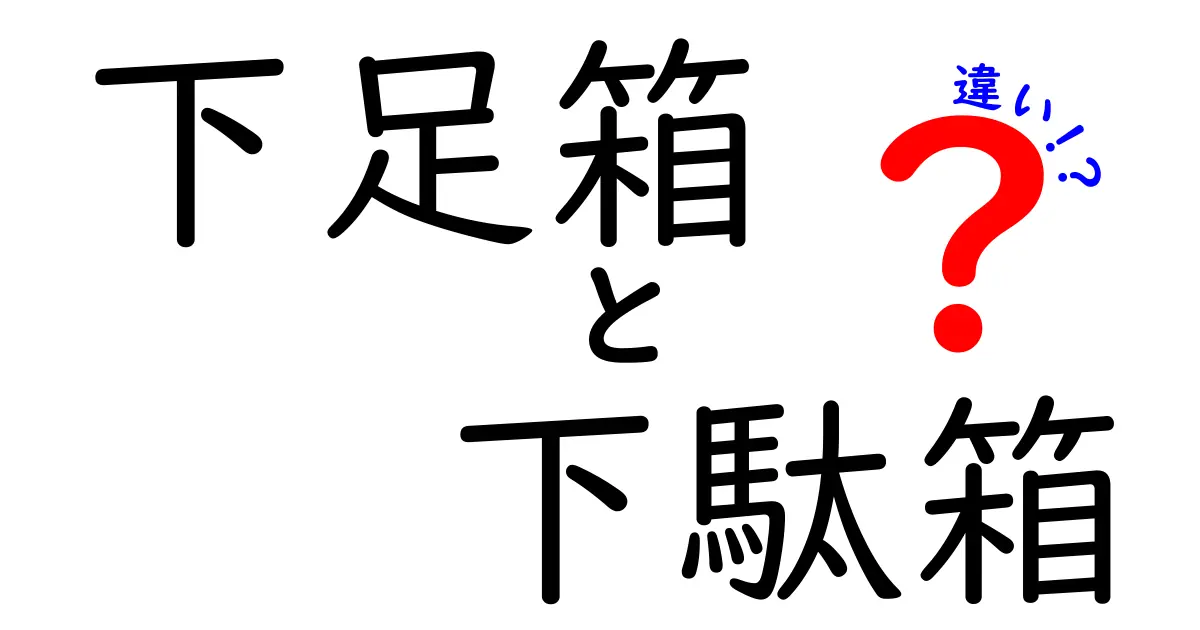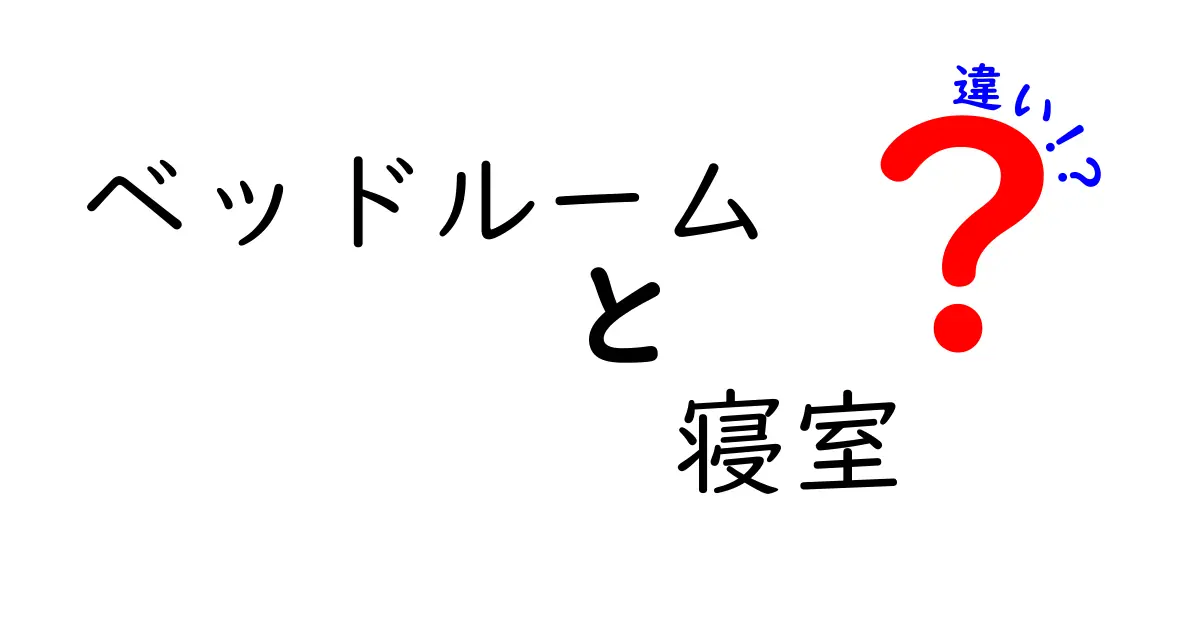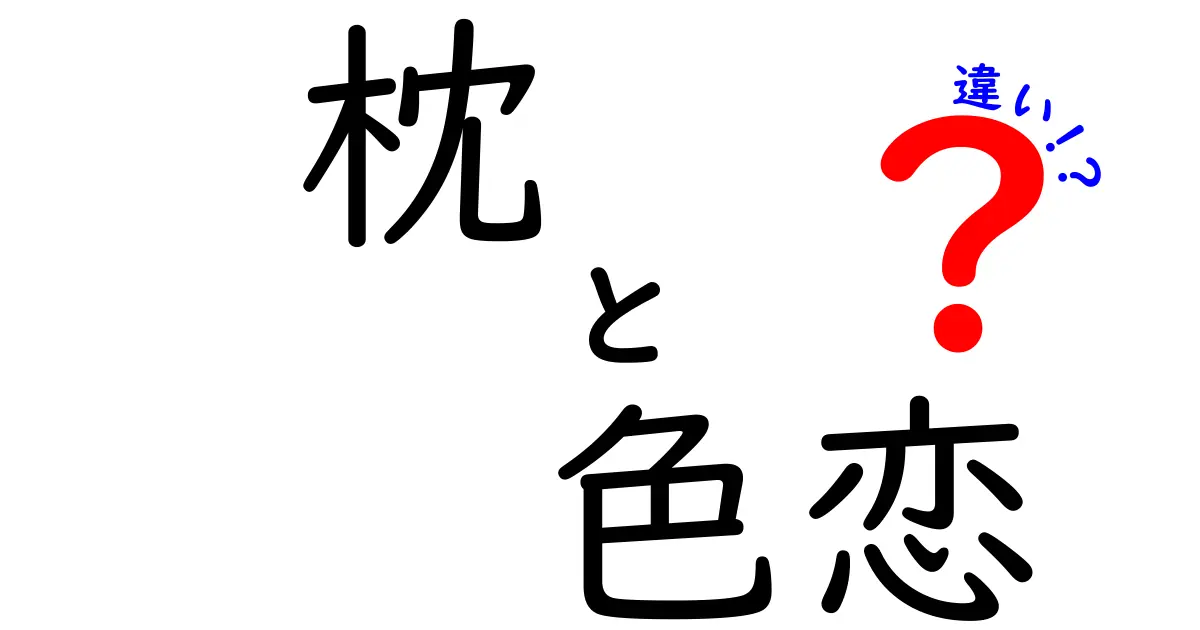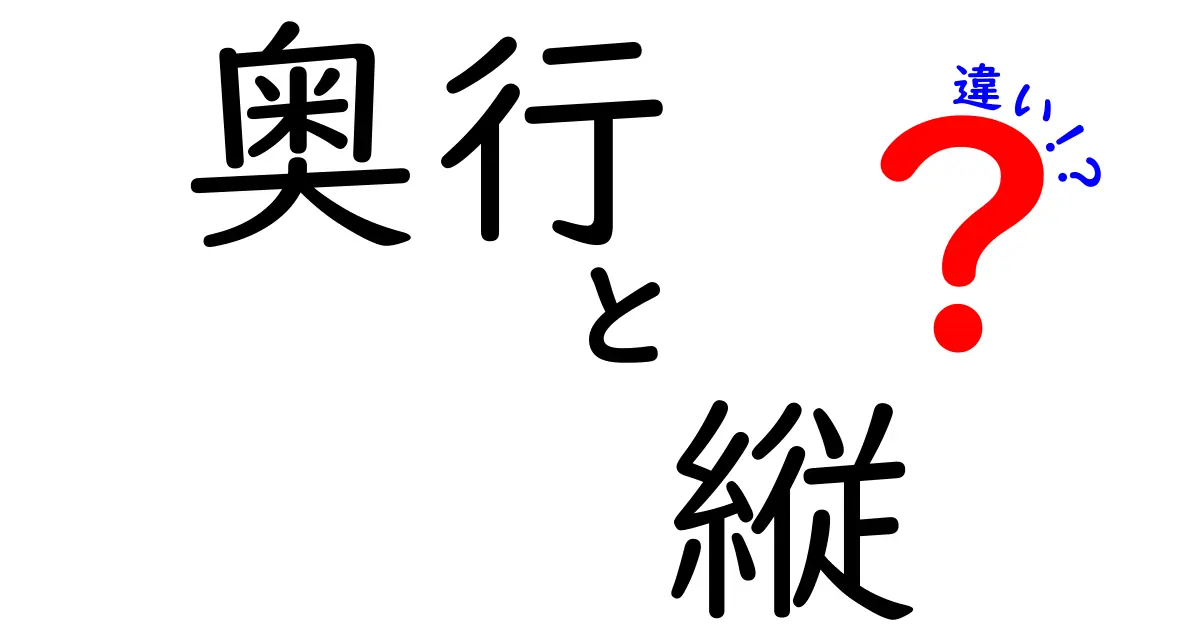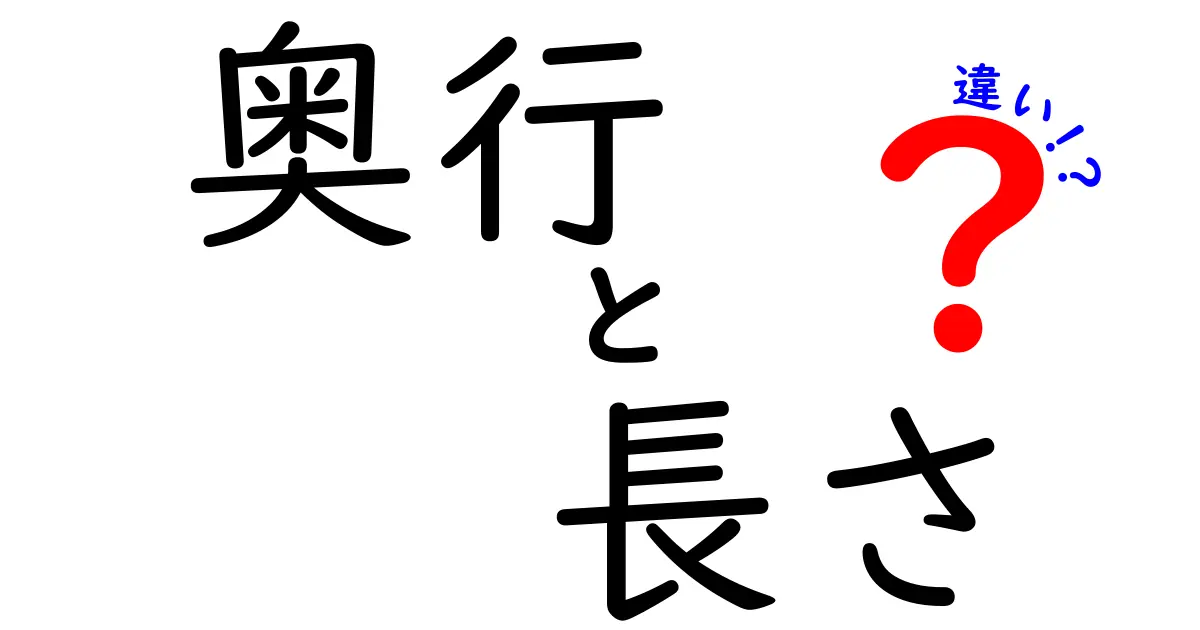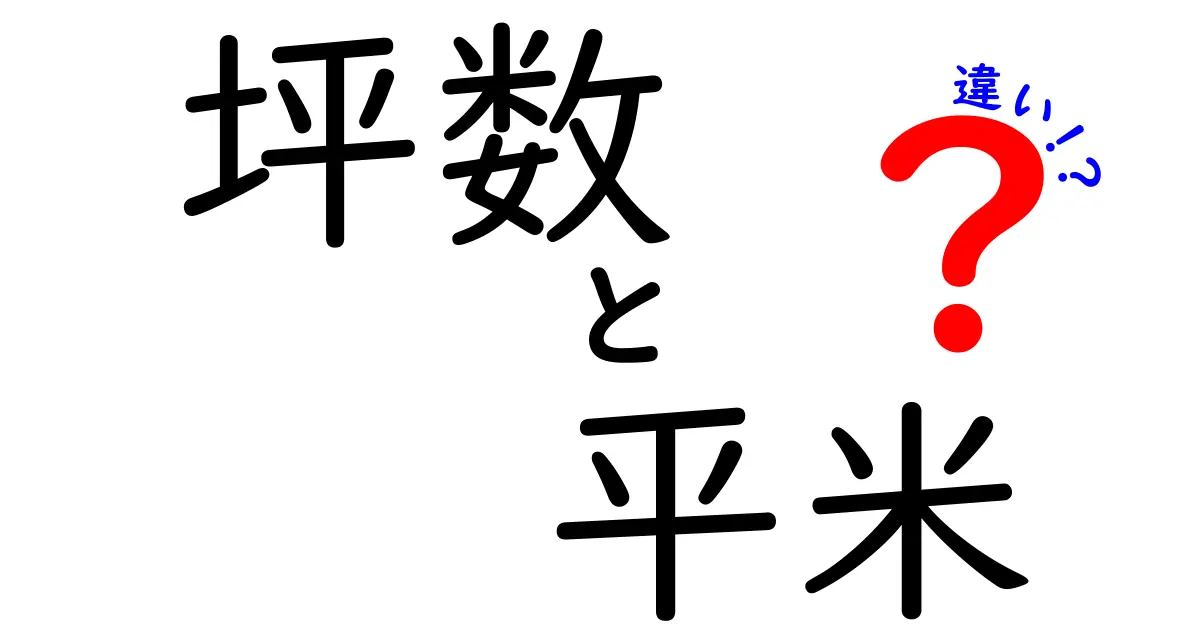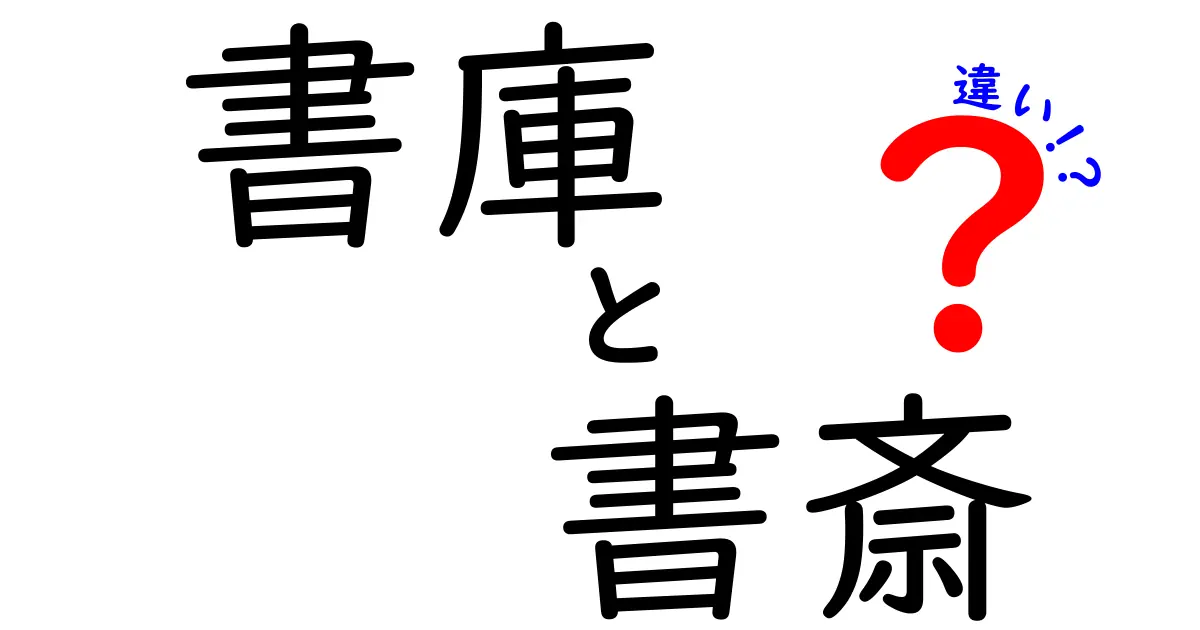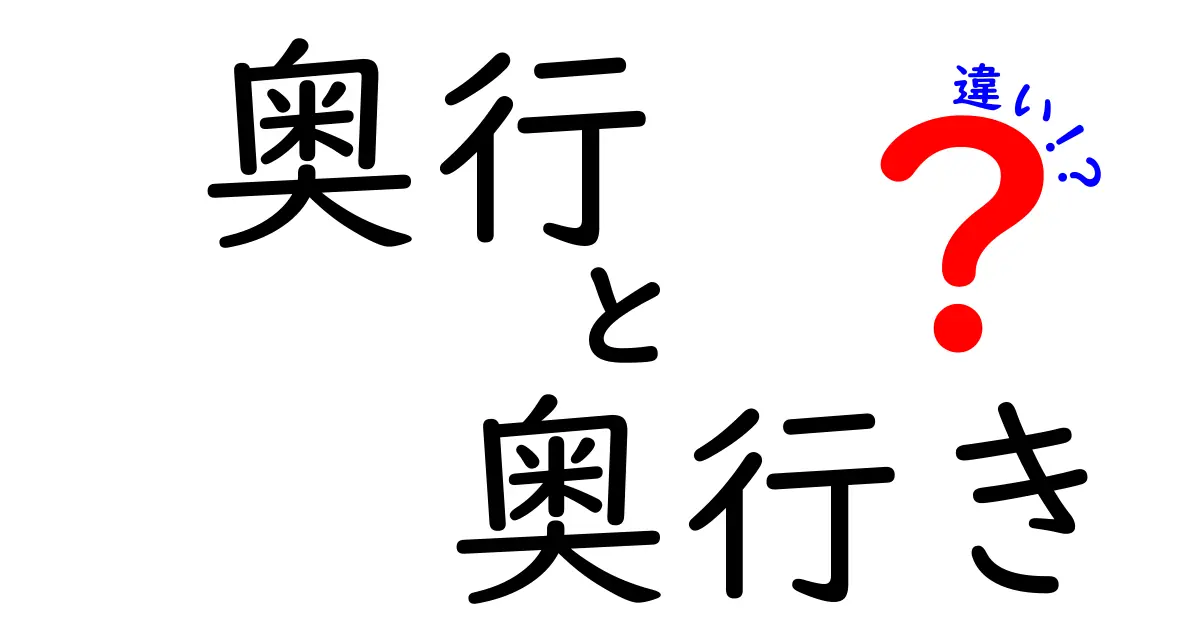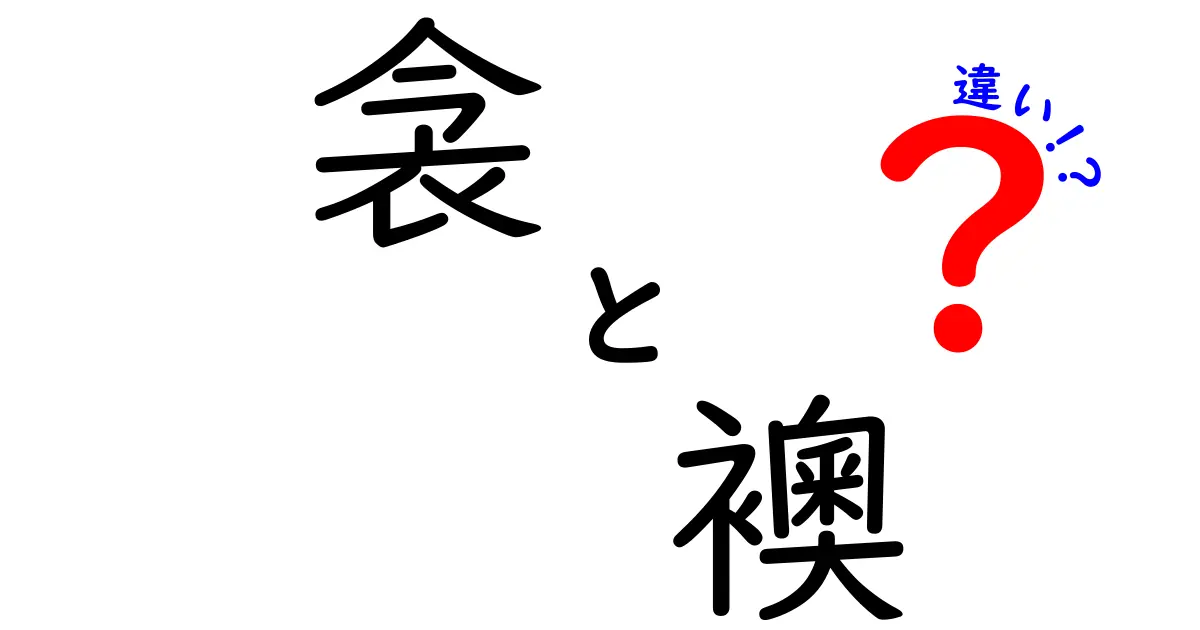
衾と襖とは何か?基本的な意味を理解しよう
まず、衾(ふすま)と襖(ふすま)という言葉は、読みも形も似ているため混同されやすいです。
しかし、この二つはまったく違うものを指します。
衾は、「布団(ふとん)」の中に入って使う掛け布団の一種で、主に暖を取るために用いられる寝具です。特に昔の日本では、羊毛や綿を用いた厚さや柔らかさのある掛け布団を指しました。
一方、襖は日本の伝統的な建具の一つで、部屋と部屋を仕切る引き戸のことです。木枠に紙や布を貼り付けた薄い仕切り板で、軽く押して開閉できるのが特徴です。
このように衾は寝具、襖は部屋の仕切りという全く異なる用途と意味を持っています。
衾(ふすま)の特徴と使い方について詳しく解説
衾は、掛け布団のことで、寒い冬に身を包み暖を取るためのアイテムです。
日本の昔の家では、冬になると厚手の衾がとても重要な役割を果たしました。
材質としては、羊毛や綿、麻を使ったものが多かったです。これは熱を逃がさず、体温を保つ効果が高いのが理由です。
厚みがあり重みがあるため、寝ている間にずれにくいのも特徴です。
また、衾は名前の由来に、日本語の「包む(つつむ)」という意味と関係していると言われており、体を包み込む暖かさを象徴しています。
現代の掛け布団とほぼ同じ役割を持つと考えてよいでしょう。
襖(ふすま)の特徴と使い方についての理解
襖は、部屋を仕切るための引き戸です。
現代の建築における壁とは異なり、紙や布を貼った薄い板でできており、軽い動きで開け閉めできます。これは日本の伝統的な住宅文化に根付いており、可変的に空間を使うのにとても便利です。
材質は、木の枠に障子紙や和紙が貼られていることが多いですが、防音や防暑のために強化されたものもあります。
襖は装飾性も重視され、多くの場合表面には絵や模様が施され、家の雰囲気を美しくしてくれます。
簡単に空間を区切ったり、大きく広げて一体化したりできることが魅力です。
衾と襖の違いがわかる比較表
| 項目 | 衾(ふすま) | 襖(ふすま) |
|---|---|---|
| 意味 | 掛け布団の一種 | 部屋を仕切る引き戸 |
| 用途 | 体を暖める寝具 | 空間を区切る建具 |
| 材質 | 羊毛や綿などの布団素材 | 木枠に紙や布を貼った引き戸 |
| 特徴 | 厚みがあり重い、保温性が高い | 軽くて開閉が簡単、装飾的 |
| 歴史的な役割 | 寒さを防ぐ重要な寝具 | 住宅の空間を調節する伝統的建具 |
まとめ:衾と襖の正しい使い分けを知ろう
衾と襖は、読みも似ていますが用途と役割は大きく異なる日本の伝統的なものです。
衾は主に寒さ対策に用いる掛け布団で、寝具の一種です。
対して襖は部屋の仕切りとして、空間を自由に区切ったり広げたりできる建具です。
日本の伝統文化や住宅様式を理解すると、これら二つの言葉の持つ意味や使い方がはっきりとイメージできるようになります。
今回で、衾と襖の違いを正しく理解し、言葉を混同しないようにしましょう。
襖について考えると意外に面白いのは、その軽さとデザイン性です。
ただの仕切り板と思われがちですが、和紙や布の表面に美しい絵や模様が描かれていることが多く、まさに動くアートのようです。
しかも、押すだけで開閉できる軽さは日本の気候管理や生活様式にぴったり。
外国の壁にはない独特の風情がありますね。