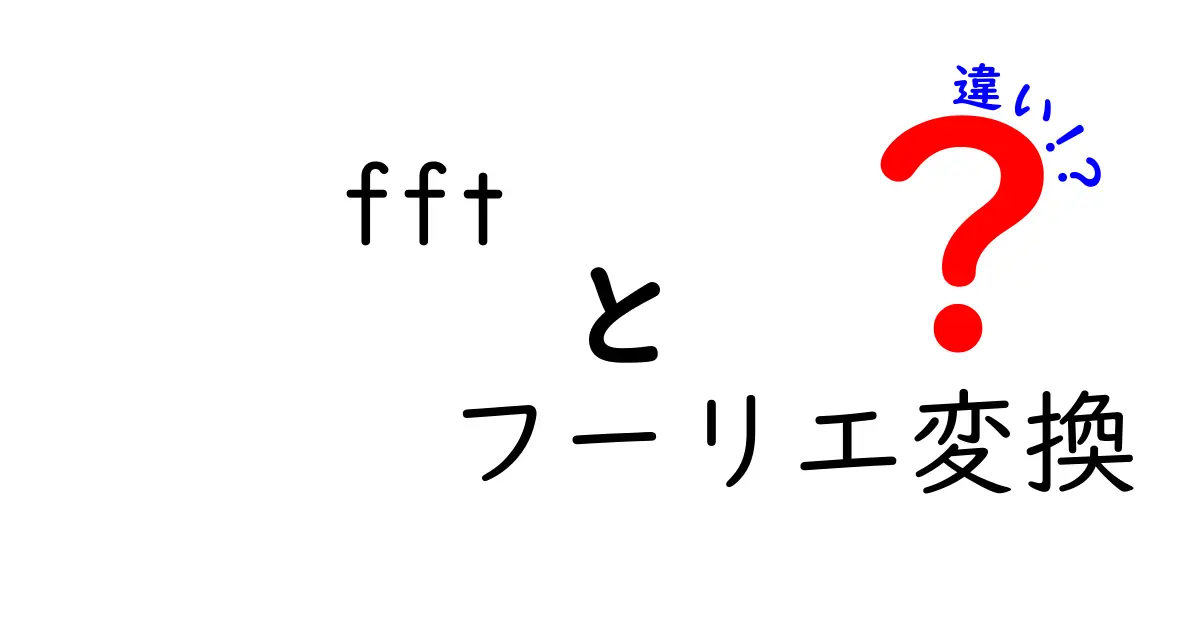

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
FFTとフーリエ変換の違いとは?
まずはフーリエ変換について説明しましょう。フーリエ変換とは、音や光、電気信号など、時間や空間で変化する信号を、異なる周波数の波の組み合わせに分解する数学的な方法です。この考え方は、複雑な波を単純な正弦波や余弦波に分けることだとイメージしてください。
一方、FFT(高速フーリエ変換)は、このフーリエ変換をコンピューターで効率よく計算するアルゴリズム(計算方法)です。フーリエ変換自体は数学の理論ですが、FFTは実際に計算する際に使われる「速く計算するためのコツ」です。
簡単に言うと、フーリエ変換は原理や方法そのもの、FFTはその方法をコンピューターで素早く行うための特別な技術という違いがあります。
フーリエ変換の基本的な仕組みと使いみち
フーリエ変換は18世紀末に数学者ジャン=バティスト・ジョゼフ・フーリエによって考案されました。
信号やデータにはいろいろな周波数成分が混ざっています。音楽の音も、いろんな音の波が重なり合ってできています。フーリエ変換はそれを分解し、どんな周波数の音がどれくらい含まれているかを調べられるのです。
このため音声認識、画像処理、通信、医学のMRIなど、多くの分野で活用されています。つまり、信号の「周波数の泉」を見つける道具と考えてください。
FFTが生まれた背景とそのメリット
フーリエ変換の計算はとても時間がかかります。特にパソコン以前の時代では、長いデータのフーリエ変換をするのはほぼ不可能でした。
そこで1965年にジェームズ・コーリーとジョン・トゥッキーが考案したのがFFTです。FFTは計算回数を劇的に減らすアルゴリズムで、コンピューターでも素早くフーリエ変換ができるようになりました。
このおかげで、リアルタイムの音声解析や動画処理、地震波の解析などが可能になり、現代のデジタル技術の基盤を支えています。計算速度の速さがFFTの最大のメリットです。
フーリエ変換とFFTの違いをわかりやすくまとめる表
まとめ
フーリエ変換とは、信号を周波数ごとに分ける数学の理論であり、FFTはその理論をコンピューターで速く計算するための技術です。
この違いを意識することで、音声解析やデジタル信号処理の話がスムーズに理解できるようになります。
もし信号処理の勉強や実際のプログラミングに興味があるなら、まずはこの二つの関係を押さえておきましょう。
FFT(高速フーリエ変換)の面白い点は、その名前の通り「高速」であることです。実は、フーリエ変換の普通の計算はものすごく時間がかかるのですが、1965年に考えられたFFTのアルゴリズムは計算量をぐっと減らしました。
これによって、スマホやパソコンでもリアルタイムで音声や画像を解析できるようになり、音楽アプリやビデオ通話など私たちの日常生活を支える技術の一部になっています。
このことを知ると、普段使っている機械やアプリに隠された数学の力をちょっとだけ感じられるかもしれませんね。





















