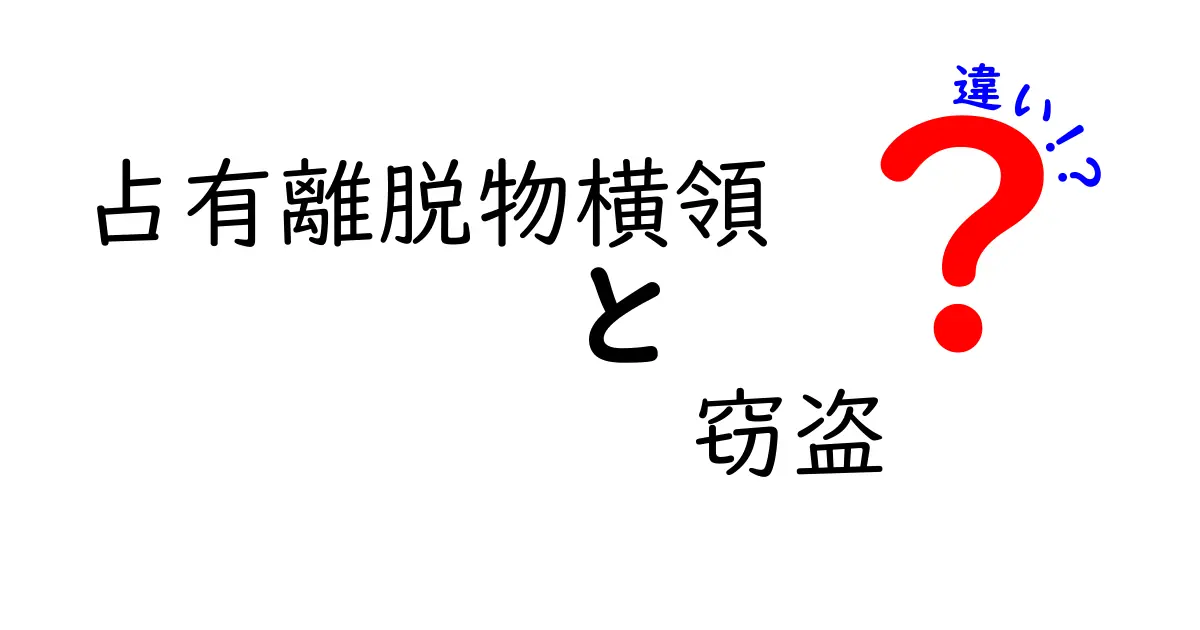

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
占有離脱物横領と窃盗の違いとは?
まずは、占有離脱物横領(せんゆうりだつぶつおうりょう)と窃盗(せっとう)の違いを正しく理解することが大切です。どちらも他人のものを不正に持ち去る犯罪ですが、法律上では明確な違いがあります。
占有離脱物横領とは、他人のものだけども誰かが占有していない物を、自分のものとして使ったり持ち去ったりする犯罪です。例えば、公園に落ちていた財布を拾って自分のものにするような場合がこれにあたります。ここでは、その物を持っている人が「占有者」となり、その占有が離れている(たとえば落としたなど)物を無断で自分のものにすることが問題です。
一方、窃盗は誰かが占有している物をその「占有者」から直接盗むことを指します。たとえば他人の家に忍び込んで物を盗む場合や、誰かの手から物を奪い取る場合などが窃盗です。
この2つの犯罪は似ていますが、ポイントは「その物の占有が離れているかどうか」という点にあります。この違いを理解することで、どちらの犯罪が成立するのかが判断しやすくなります。
法律における占有離脱物横領と窃盗の定義と適用例
次に、法律での定義と具体的な事例を見てみましょう。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。「他人の物を steal すること」であり、「不法領得の意思をもって、占有者の意に反してその物を盗む行為」とされています。例えば、他人のバッグを盗むこと、店で商品を隠して持ち帰ることなどが該当します。
一方、占有離脱物横領罪は刑法第254条に規定されています。「他人の占有を離れた物を自分のものとして横領すること」が要件です。たとえば、通りで財布を拾って警察に届けることなく自分のものにする行為が該当します。
実際の判例では、物を落とした人の占有が離れている状況や誰かが管理していない場合に占有離脱物横領罪が適用されます。
下記の表に法律上のポイントをまとめてみました。
身近な例でわかる占有離脱物横領と窃盗の違い
みなさんの生活の中で起こりうる、身近な例で違いを考えてみましょう。
例えば、学校で友達がペンを机の上に置いたまま忘れてしまったとします。そのペンをそのまま持って帰ると、それは窃盗にあたります。なぜなら「忘れた」場合でもペンは友達がそのペンの占有者だからです。占有はそのまま続いています。
一方、道で誰かが落とした財布を見つけた時に、自分のものとして使ったり隠したりすると、それは占有離脱物横領という犯罪になります。この財布はもともとの持ち主が持っていましたが、「落としてしまい占有が離れている」ため、この罪が成立するのです。
このように、「その物を誰がどんな状態で持っていたのか」を考えることが、どちらの犯罪かを見分けるポイントです。
また、警察に届けるなど正しい対応をすれば犯罪にはなりません。落とし物を見つけたら、必ず警察や交番に届けることがマナーです。
占有離脱物横領って聞くと、なんだか難しい言葉ですが、実は日常でよくある落とし物の問題なんです。たとえば、誰かが街に財布を落としたとき、それを見つけて自分のものにするのは犯罪。でも、なぜ『盗む』のではなく『横領』と呼ばれるのか?実は、物が本来の持ち主の手を離れている状態だからなんです。面白いのは、この細かい法律の違いが実際の罪を分けていること。法律は意外と優しく細かく人の行動を見ているんですね。
次の記事: 暴力と暴行の違いとは?法律と日常で使う意味をわかりやすく解説! »





















