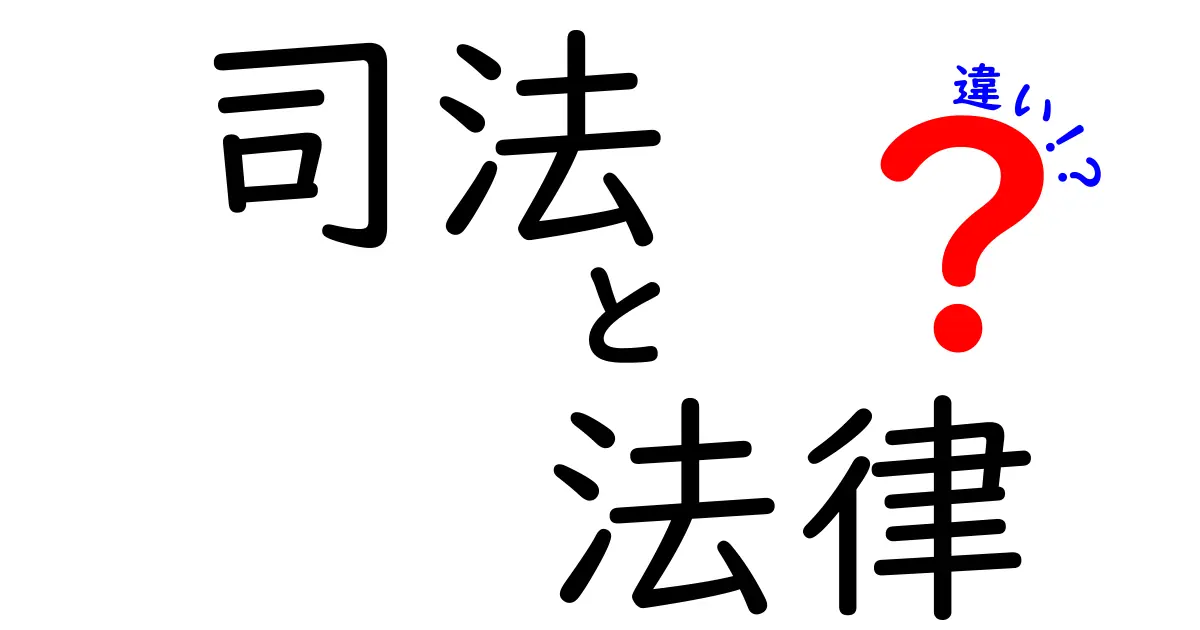

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
司法と法律の基本的な違いとは?
まず、「司法」と「法律」は日本社会でとても重要な役割を持つ言葉ですが、その意味や役割はまったく異なります。
「法律」とは、国が定めたルールや決まりごとで、国民が守らなければならない規則のことです。例えば、交通ルールや税金の支払いの仕方など、私たちの生活全般を規定しています。
一方で、「司法」とは、その法律を守らせるために争いが起きた時に判断を下す仕組みや機関のことを指します。裁判所や裁判官などがこれにあたります。法律がルール、司法はそのルールを正しく適用する役割と理解しましょう。
司法と法律の具体的な役割の違い
わかりやすく言うと、法律は「みんなが守るべき決まり」です。例えば、飲酒運転を禁止する法律があれば、みんなはそのルールを守って運転しなければなりません。
しかし、もし誰かが法律を破ってしまった場合、どうすればよいでしょうか?そこで登場するのが司法の役割です。
司法は、裁判所が事件を受けて、その法律に基づいて事実を調べたり証拠を確認したりし、裁判官が〈違反があったかどうか〉や〈どのような処罰がふさわしいか〉を判断します。
つまり、法律がボールのルールだとすると、司法はレフリー(審判)のような存在です。
司法と法律の違いを表で整理すると
| 項目 | 司法 | 法律 |
|---|---|---|
| 意味 | 法律を守らせるための判断や仕組み | 国や地方自治体が定めるルールや規則 |
| 主な役割 | 争いごとを解決し、法律の適用を判断 | 社会のルールや行動の基準を決める |
| 関係する機関 | 裁判所、裁判官、検察官 | 国会(法律を作る機関) |
| 例 | 裁判での判決や審理 | 刑法、民法、交通法規など |
まとめ:司法と法律はセットで社会を守る存在
司法と法律は混同しやすいですが、法律はみんなが守るためのルールであり、司法はそのルールを正しく守らせるための判断システムです。
もし法律がなかったら、何が正しいかがわからず社会が混乱しますし、司法がなければ誰がルールを守っているかチェックしたり、争いごとを解決したりできません。
中学生の皆さんも法律と司法の違いを知って、おとなになって社会の一員としてルールを守る意識を持つことはとても大切なことです。
「司法」という言葉を聞くと、裁判や警察をイメージしがちですが、実はかなり広い意味があります。司法は法律をもとに社会の秩序を保つ役割。例えば、裁判所で争いを解決することはもちろん、法律の解釈を提示したり、場合によっては権利を守るための判断を行なったりします。
中学生の頃は「むずかしい言葉」と感じるかもしれませんが、司法があるからこそ私たちの生活はスムーズに回っているんですね。裁判所だけでなく、検察官や弁護士も司法の重要な担い手です。司法がなければ、『ルールを守らない人は誰が咎めるの?』という社会の不安定さが生まれてしまいます。
前の記事: « 【刑法と軽犯罪法の違い】初心者でもわかるポイント別比較ガイド





















