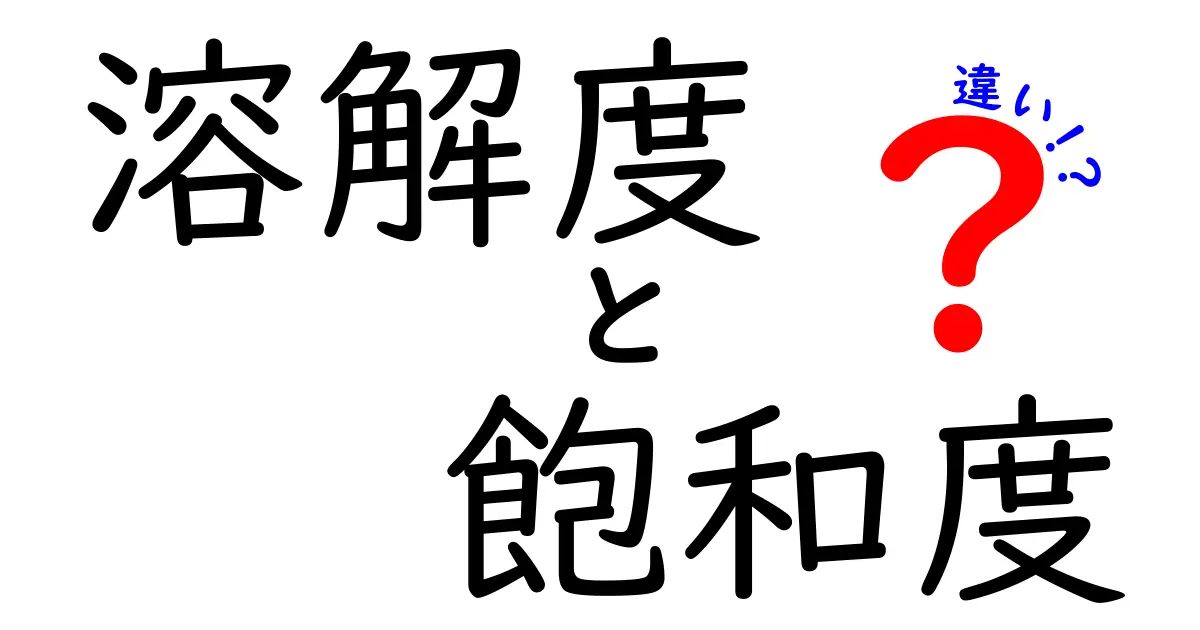

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
溶解度とは何か?その基本をわかりやすく説明!
私たちが水に砂糖や塩を入れたとき、ある程度まではその物質が水に溶けますね。この時の「どれくらい溶けるか」を示すのが溶解度です。溶解度は一定の温度で、100gの水にどれだけの物質が溶けるかを表しています。つまり、水に溶ける量の限界値のことです。
例として、砂糖の溶解度は約200g/100gの水(20度の時)です。これは100gの水に約200gの砂糖が溶けるという意味です。溶解度は温度によっても変わります。温度が上がると溶解度が高くなる場合が多いので、暖かいお湯にはたくさん砂糖が溶けるのです。
けれど、この溶解度はあくまで理論上の限度。水に完全に溶ける量がここまでという数字です。それ以上入れると水に溶けきらず、固まったまま残ってしまいます。この基本を押さえておくことが大切です。
飽和度とは?溶解度との違いに迫る!
飽和度は、溶解している物質の量がその水の溶解度に対してどれくらい満たしているかを割合で示したものです。
例えば、溶解度が100gの塩の場合、水に50gしか溶けていなければ飽和度は50%と表現します。
飽和度は実際の溶解状態を示す値で、その液体が「どれくらいの量の物質を溶かしているか」を数字で分かりやすく表現したものです。
飽和度が100%だと、その液体はもうそれ以上物質を溶かせない「飽和状態」となっています。たとえば水に塩を溶かし続けると、やがてもっと溶けなくなる瞬間が来ますね。これが飽和度100%の状態です。
ただ注意したいのは、「飽和度が100%だからといって必ず固形の物質が見えるわけではない」ことです。時には完全に均一に混ざっていて、目に見えないこともあります。溶解度が限界で飽和している、という物理的状態を表しているのが飽和度なのです。
溶解度と飽和度まとめ表
まとめ:溶解度と飽和度の違いを理解しよう!
溶解度は「物質が水に溶けられる最大量」、飽和度は「今どのくらい溶けているかの割合」だと覚えましょう。
日常生活で砂糖や塩を水に溶かすとき、溶解度を超えると固形が残るのは溶ける量の限界があるからです。飽和度100%がその状態にあたり、それ未満ならもっと溶ける余地があります。
科学や料理、または水の性質を知る上で大切な概念なので、ぜひ覚えておきましょう!
これを理解すると、なぜお湯だと砂糖がよく溶けるのかや、飽和状態の水溶液の性質もよく分かります。溶解度と飽和度の違いは、水に物質が溶ける仕組みを知る鍵なのです!
溶解度についてちょっと面白い話をしましょう。砂糖や塩が水に溶ける量は温度によって変わるんですが、実はある物質の溶解度は温度が上がるとグンと増えることが多いです。例えば冬より夏のほうがお茶やコーヒーに砂糖が溶けやすいのは、これが理由なんです。だから冷たい水で作る甘い飲み物は、甘さが控えめに感じることもありますね。この『温度と溶解度の関係』は、料理や実験で知っておくと便利ですよ!
次の記事: 相対湿度と飽和度の違いとは?簡単に理解できるポイントを徹底解説! »





















