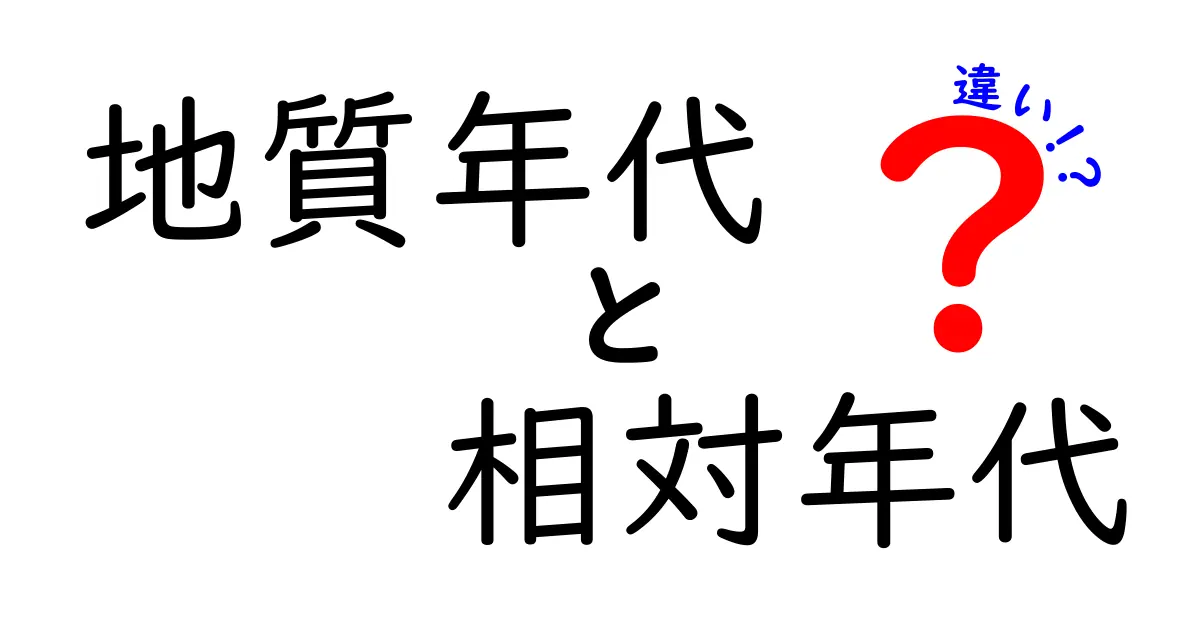

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
地質年代と相対年代って何?
地質学を学ぶときによく出てくる言葉の中に「地質年代」と「相対年代」があります。これらは地層や化石の年齢を調べるための考え方ですが、名称だけでは似ているので混乱しやすいです。
地質年代は、地球の歴史を時間で区切ったもの。たとえば「ジュラ紀」や「白亜紀」などのように、地球の長い歴史をわかりやすく区分けした期間のことを言います。
一方、相対年代は、地層や化石の前後関係を比べることで、どちらが古いか新しいかを判断する方法のこと。これは実際の年数ではなく、順番の違いだけを教えてくれます。
この記事では地質年代と相対年代の違いをくわしく解説し、地質学の基本をしっかり理解できるようにしていきます。
地質年代とは?地球の歴史の時間の区切り
地質年代は地球の長い歴史をいくつかの期間に分けたものです。たとえば、地球は約46億年の歴史がありますが、すべてをそのまま扱うのは大変です。そこで、それぞれの地質時代を区切り、特徴的な環境や生物の変化があった時期として分類します。
たとえば三大地質時代の一つである「中生代」は恐竜が生きていた時代で、さらに「ジュラ紀」や「白亜紀」に分かれます。こうした地質年代の区分は、化石の発見や地層の変化をもとに決められているので、現在でも研究が進んでいます。
地質年代の特徴は具体的な年数や時代の名前が決まっていること。だから、「約2億年前の地層だ」といった言い方ができます。
これに比べると相対年代は年数を直接扱わず、あくまで順番だけで年代を考えます。
相対年代とは?地層の前後関係からわかる年齢の順番
相対年代は、「ある地層や化石が別の地層や化石よりも古いか新しいか」という順番を比較して決める方法です。ここで使われるのは「重なりの法則」や「遺物相関」など、いくつかのルール。
たとえば、下にある地層は上にある地層より古い、という「重なりの法則」があります。これにより、地層同士の年齢の前後関係がわかるのです。
しかし、相対年代では具体的な年数を教えてくれるわけではありません。「どちらが古いか」はわかっても、その差が何万年なのかまではわからないのです。
相対年代は、化石を使う場合でも「この種類の化石はあの地層より前にいる」といった順番の判断に使われます。これは地質年代の決定や、年齢測定の補助にもなります。
地質年代と相対年代の違いを表でまとめました
まとめ: 地質年代と相対年代をうまく使い分けよう
地質年代と相対年代は、どちらも地球の歴史を知るための重要な考え方ですが、役割が違います。
地質年代は地球の歴史を時間軸で切る目安で、具体的な時代名や年数があります。
一方、相対年代は地層や化石の古さの順番を比べて、大まかな年代の関係を知る方法です。
どちらも一緒に使うことで、より正確に地球の歴史や生物の進化を解き明かせます。
地質学や自然科学に興味があるなら、ぜひこの違いを押さえておきましょう!
「相対年代」って、ただ単に古い・新しいを比べるだけと思いがちですが、実は地層の重なり方や化石の位置関係で過去の出来事の順番を読み取れるすごい方法なんです。これは、まるでタイムカプセルの内容を順番に並べる作業みたいで、年号がなくても『どれが最初に起こったか』がわかるんですよ。ちょっとしたパズル感覚で地球の歴史を楽しく学べちゃいますね。
前の記事: « 泥岩と玄武岩の違いとは?見た目・成分・でき方をわかりやすく解説!





















