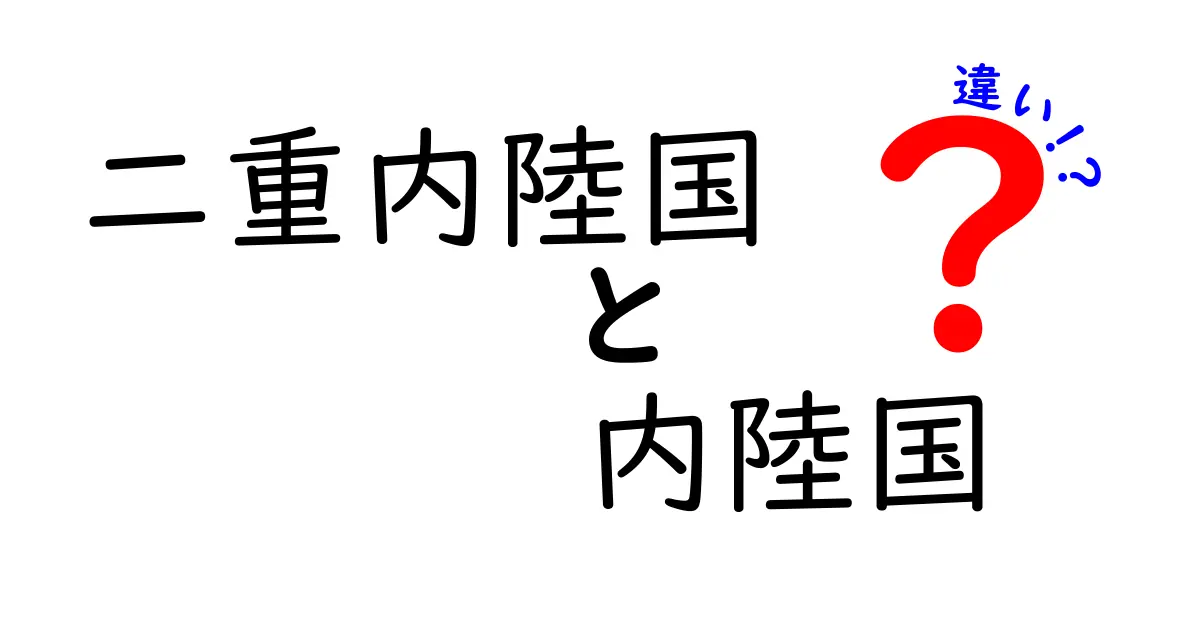

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
二重内陸国とは何か?
二重内陸国という言葉を聞いたことがありますか?聞き慣れない言葉ですが、地理学の中ではとても重要な意味を持っています。まず、内陸国とは、海に面していない国のことを指します。つまり、海に直接接していない国のことを言います。これに対して、二重内陸国は、さらに条件が限定されており、“内陸国の中でも、さらに海に面した国に接していない国”のことを指します。
具体的には、内陸国がどこかの海に面した国と国境を接しているのに対して、二重内陸国は、国境を接している相手も全て内陸国で、海に出るためには二つ以上の国を通らなければいけない状態の国のことです。
こうした地理的条件は、その国の経済や交通、貿易にも大きな影響を与えます。二重内陸国は海に出るまでに複数の国を通る必要があるため、輸送コストが高くなるなど問題が起こりやすいのです。
内陸国の特徴と問題点について
内陸国とは、海に接していない国のことで、世界には多くの内陸国があります。たとえば、スイスやオーストリア、チャドなどが代表例です。
内陸国は海がないことで、貿易など海上輸送が直接できないため、物流コストが高くなる傾向があります。また、海を利用した観光や漁業などの産業も限られてしまいます。したがって、経済活動においてハンディキャップを持つことが少なくありません。
しかし、内陸国は場合によっては陸路での交通網が発達しており、その地理的な条件を工夫して克服している国も多いです。
たとえばスイスはアルプス山脈を活かした観光資源を持ち、工業製品の輸出でも成功しています。
二重内陸国のさらに深い困難とは?
二重内陸国は内陸国の中でも特に交通と貿易で難しい問題を抱えています。
なぜなら二重内陸国は、自国から出るために他の内陸国を一つ以上通過しなければ海に出られないため、物流の障害が大きいのです。たとえば、ボリビアは内陸国ですが、ブラジルなど海に面した国と国境を持ちます。一方、二重内陸国であるボツワナやウズベキスタンは、海に出るためには複数の国を経由しなければなりません。これにより関税や通過手続きが複雑になる上、輸送時間も長くなります。
このような理由から、二重内陸国は国際貿易においてより多くの制約とハンディキャップを抱えることになります。
経済の発展において、交通・物流コストの問題を解決することが非常に重要なのです。
二重内陸国と内陸国の違いをまとめた表
二重内陸国という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、実は国際地理学でとても重要な概念です。例えばウズベキスタンは二重内陸国で、海に直接つながる国がないため、貿易や物流で大変な苦労をしています。これは一国だけの問題ではなく、周囲の国との協力や交通インフラの改善が不可欠という面白い問題なんですよ。意外とこういう地理的条件が経済に及ぼす影響は大きいんです!
前の記事: « 地理学と社会学の違いとは?わかりやすく解説!





















