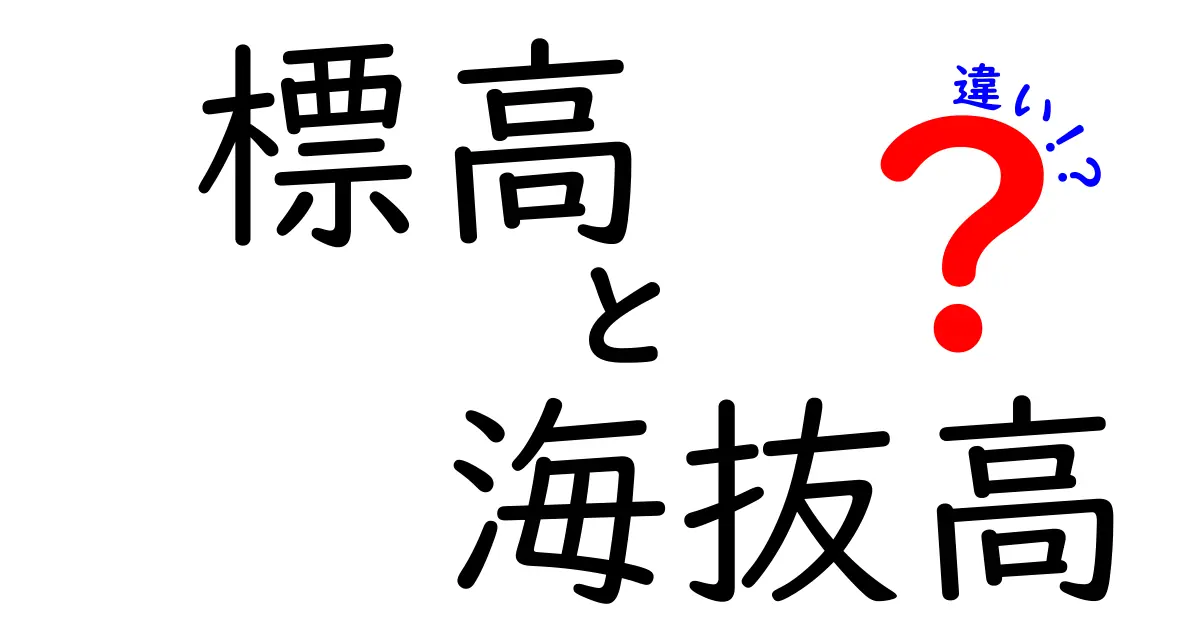

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
標高と海抜高の基本的な違いとは?
世の中には「標高」と「海抜高」という言葉があります。どちらも地面や建物などの高さを表す言葉ですが、その意味は少し違います。まずはこの2つの基本的な違いについて説明しましょう。
「標高」とは、地表上のある地点の高さを
「平均海面(一般的に定められた海の水面の高さ)」から測った高さのことです。つまり、山や丘の頂上などの高さを測る時に使います。
「海抜高」も似ていますが、通常は「海抜」を使うことが多く、「海抜」はある地点の高さを「海面からの高さ」と定義します。ですので、一般的には「標高」と「海抜高(海抜)」はほぼ同じ意味で使われることが多いです。
しかし、厳密には測量方法や基準となる海面の設定の違いから区別されることもあります。
つまり、どちらも“海の平均水面からの高さ”を指すけど、標高は特に地形の高さを示す時に使い、海抜高は建物や構造物の高さとして意味を持つ場合もあります。
標高と海抜の違いがわかりにくい理由とその使い分け
なぜ「標高」と「海抜」が混同されやすいのか?それは日常生活で両者を区別しなくても困らないことが多いからです。
しかし地理学や建築、測量の専門家は明確に区別します。
■「標高」
- 主に地形や地表の高さを表す
- 山頂や地形の高さを知りたい時に用いられる
■「海抜」または「海抜高」
- 建築物や人工構造物の高さの基準として使われることが多い
- 洪水や津波のリスク管理で重要視される
例えば、家の建築設計の場合、「この場所の海抜は100mです」と言うと、その土地が平均海面から100mの高さにあることが示され、洪水の心配が少ないことがわかります。
逆に山の高さを表すとき、「標高1500mの山」と言えば、その山の頂上が海面から1500m高いことを指します。
こうした区別が実務上役立っているのです。
標高・海抜高の具体例とわかりやすい比較表
ここで、具体的な例を挙げながら「標高」と「海抜高」について見てみましょう。
| 地点 | 標高(m) | 海抜高(m) | 用途例 |
|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 富士山頂 | 3776 | 3776 | 山の高さを表す時に使用 |
| 東京タワー | 33 | 約250 | 標高33mの土地上に建設。塔の先端は海抜約283m。|
| 地上駅 | 5 | 5 | 洪水対策などで海抜が重要|
このように標高は土地の高さを示し、海抜高は土地の高さに加えて建物の高さもふまえます。
つまり、標高は地形の高さ、海抜高は建物など人工物の高さの目安として使われることが多いのです。
まとめ:標高と海抜高の違いを理解して使い分けよう
「標高」と「海抜高」は非常に似ていますが、標高は主に地形の高さを表し、海抜高は人工物の高さなど幅広く使われる言葉です。
日常生活で混用しても大きな問題はありませんが、測量や建築、災害対策などでは正しく理解して使い分けることが重要です。
この違いを知っておくと、ニュースや資料を読む時に理解が深まります。ぜひ覚えておきましょう!
標高と海抜って、実はちょっとした言葉の違いですが、意外と奥が深いんです。
例えば、海抜は基本的に『平均海面からの高さ』のことですが、この『平均海面』っていうのも実は簡単じゃありません。
海の水面は潮の満ち引きや気候変動で変わるので、世界中で統一された基準が作られています。
だから測量士さんたちは世界測地系を使って、平均海面を計算しているんですね。
標高っていうのは、その基準から土地の高さを測ることで、だから標高と海抜は切っても切れない関係なんです。
こういう仕組みを知ると、地図を見たり山登りする時にちょっと楽しくなりますよ!
前の記事: « コーヒー豆は標高で味が変わる!その違いをわかりやすく解説
次の記事: 三角点と山頂の違いって何?意外と知らない基本ポイントを解説! »





















