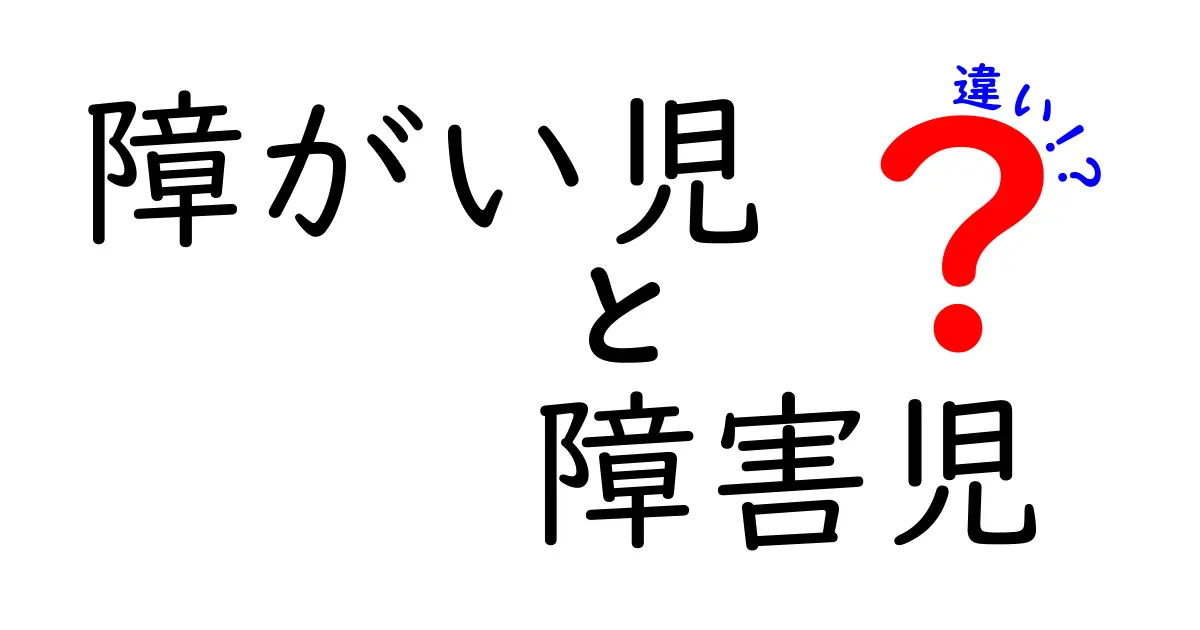

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
障がい児と障害児の言葉の違いとは?
日本語では「障がい児」と「障害児」という言葉がよく使われていますが、この二つの言葉には微妙な違いがあります。
まず、「障害児(しょうがいじ)」は、障害がある子どもを意味する言葉で、法律や医療、福祉の分野で長く使われてきました。
一方「障がい児(しょうがいじ)」は、「障害」という言葉の「害(がい)」の漢字が持つネガティブなイメージを和らげる目的で、最近使われるようになった表現です。この「がい」を「がい」と書かずに「がい」と送り仮名を使って表すことで、言葉の持つ重さや差別感を軽減しようとする工夫がされています。
つまり、両者はほぼ同じ意味を示すものの、言葉の選び方に配慮や時代の変化が反映されているわけです。
特に福祉や教育の分野では、「障がい」という表記が推奨される傾向が強くなっています。
このように、「障がい児」と「障害児」はどちらも使われますが、時代や場面によって使い方が変わることを覚えておくといいでしょう。
なぜ「障がい」という表記が増えているのか?
「障がい」という書き方が増えたのは、社会の中で障害のある人への理解と尊重が深まってきたからです。
「障害」という漢字の「害」という字には「害悪」や「害虫」など、悪いイメージを持つ言葉が多く含まれていて、障害がある人に対しても無意識に否定的な印象を与えてしまうことがあります。
そこで、厚生労働省や各地の自治体、福祉団体は「障がい」と送り仮名をつける表記を使い始めました。これは言葉を使う時の姿勢や気持ちの表れであり、差別や偏見をなくすための努力でもあります。
たとえば、学校の教材や福祉のパンフレットで「障がい」という表記が使われることが多くなっているのはそのためです。
このように、言葉の使い方を変えることは、その人の尊厳を守り、みんなが暮らしやすい社会をつくる大切な一歩となっています。
ですので、私たちも言葉を意識して使うことが求められています。
障がい児と障害児の使い分けと注意点
日常生活や文章の中で「障がい児」と「障害児」をどう使い分けるべきか?という質問も多いです。
基本的に、どちらも意味は同じなので間違いではありませんが、
- 福祉や教育の専門機関、役所の書類など、公式な場面では「障がい児」の表記を選ぶことが増えています。
- 新聞や一般的な書籍、歴史的に使われてきた文献では「障害児」と書かれることが多いです。
- 個人のブログやSNSなどでは、表記の好みや配慮の度合いで使い分けられています。
重要なのは、
その言葉を使う時にどんな気持ちでいるか、相手を尊重しているかです。
また、障がいの種類や程度によっても呼称が異なることがあったり、当事者や家族が望む呼び方を尊重する配慮も必要です。
以下は簡単に「障がい児」と「障害児」の違いをまとめた表です。
| 言葉 | 読み方 | 意味 | 使われる場面 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 障がい児 | しょうがいじ | 障害のある子ども | 福祉・教育の公式文書や支援機関 | 「害」を和らげるため送り仮名を付けた配慮の表記 |
| 障害児 | しょうがいじ | 障害のある子ども | 一般的な書籍、新聞、過去からの使用 | 昔からの正式な表記 |
このように、言葉の違いは意味そのものよりも、使う側の配慮や時代背景に関係しています。
だから、どちらを使ってもいいけれども、できるだけ相手の気持ちに寄り添う選び方や説明が望ましいのです。
「障がい」という表記の面白いポイントは、「害」という字に対する心理的な抵抗を言葉で減らそうとする工夫があることです。たとえば、「害」には『悪い』『危険』という意味があるので、障害のある子どもを指す言葉にあまり良くないイメージがついてしまうことを避けたいのです。だから、単に漢字を変えるのではなく送り仮名をつけて柔らかく見せるという表現方法が生まれました。こういう言語の変化は日本語の奥深さや社会のやさしさを感じさせますよね。
次の記事: 学習障害と知的障害の違いとは?わかりやすく解説! »





















