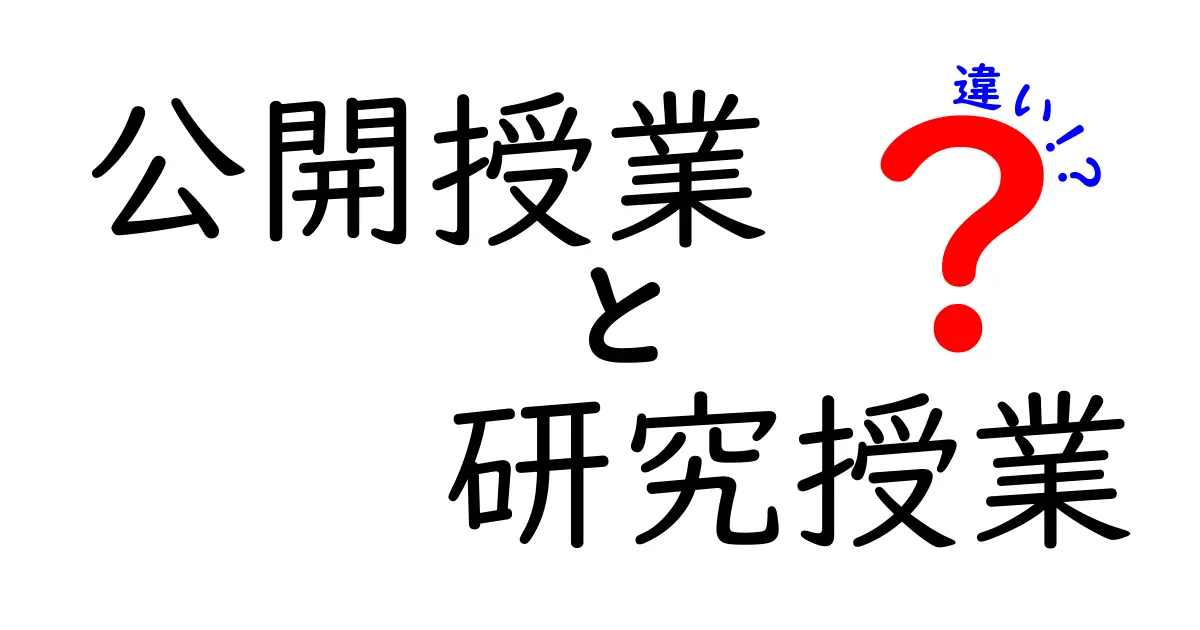

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
公開授業と研究授業とは?基礎知識を押さえよう
学校や教育現場でよく耳にする「公開授業」と「研究授業」は、似ているようで実は目的や内容に違いがあります。
公開授業は、外部の人や他校の教員、生徒の保護者など、幅広い人を招いて授業の様子を見てもらう授業のことです。学校の教育活動を知ってもらうために行われ、地域や保護者との信頼関係を深める役割もあります。
一方の研究授業は、主に教員同士が自分の授業を見せ合い、指導法や教材の使い方を研究するための授業です。授業の質を高めることが目的で、先生たちが意見交換や反省を通して成長する場となります。
二つの授業の目的と特徴を比較すると?
それぞれの授業には特徴的な目的があり、そこから授業の内容や参加者も異なります。下の表にまとめましたので参考にしてください。 このように、公開授業は外部に学校の活動を知ってもらうことが重視されるのに対して、研究授業は教員のスキルアップのための場であることがわかります。 両授業は教育の質を高めるために欠かせないものですが、運営にはいくつかのポイントや注意事項があります。 研究授業では、先生たちが自分の授業を同僚に見せることで、より良い指導方法を探ります。見られる側も見る側も緊張しますが、授業のあとに意見を交換することで、新しいアイデアが生まれやすいんです。たとえば、『もっとこうしたら生徒が理解しやすいかも』という気づきが得られるため、学校全体の授業の質アップにつながっています。教員同士のコミュニケーションの場として意外と楽しい面もありますよ。 前の記事:
« 定期試験と期末試験の違いとは?わかりやすく徹底解説! 次の記事:
学園祭と忍ミュの違いを徹底解説!どっちが楽しい?特徴と魅力を比較 »項目 公開授業 研究授業 目的 学校の教育活動を地域や保護者に公開し理解を深める 授業内容や指導法の研究・改良を目的に教員が参加 主な参加者 保護者、地域住民、他校教員など広範囲 同じ学校や近隣の教員、教育関係者 内容 普通の授業に近い形で進行し、自然な雰囲気を大切にする 授業後に指導方法や教材について詳しい話し合いや反省会が行われる 授業の雰囲気 見学者の前で緊張することもあるが、生徒の普段の様子が見やすい 専門的な議論が行われやすく、授業の工夫点がポイントとなる 実際の教育現場での活用方法と注意点
公開授業では、訪れる人たちに分かりやすく授業を見せる環境づくりが求められます。また、生徒にとってもいつもと違う環境なので緊張することもあるため、事前に説明したり準備を入念にすることが大切です。
研究授業は、授業後の話し合いが大事になります。授業のよかった点や改善点を建設的に話し合い、教員同士で学び合う風土を作ることが成功の鍵です。
どちらも生徒の成長を第一に考えた運営が重要であり、先生たちがチームとなって協力すると効果的です。
また、公開授業ではプライバシーへの配慮や学校のルールを守ることも忘れてはいけません。研究授業では評価ではなく改善を目的とした話し合いを心がけましょう。
の人気記事
新着記事
の関連記事





















