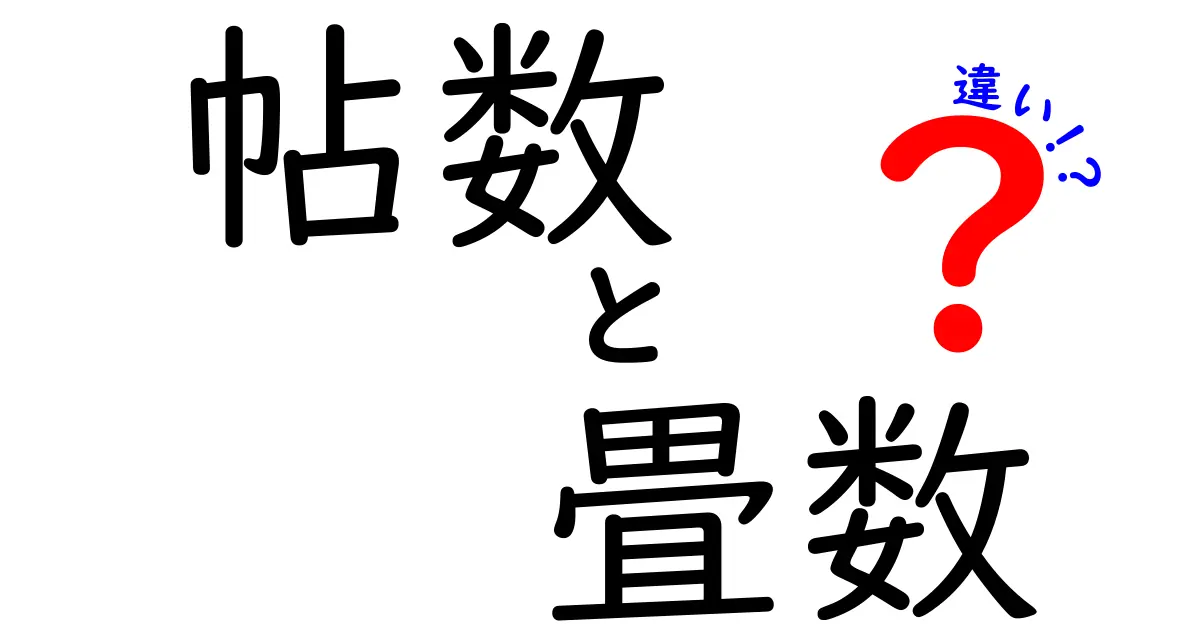

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
帖数と畳数の基本的な意味の違いについて
日本の住宅や和室の広さを表すとき、「帖数(じょうすう)」と「畳数(たたみすう)」という言葉がよく使われます。
畳数とは、実際に敷かれている畳の枚数のことを言います。つまり、部屋に敷いてある畳が何枚あるかを数えたものです。昔ながらの和室では、その畳の枚数で部屋の広さを表現してきました。
一方で帖数は、畳一枚分の広さを基準にした部屋の大きさの単位のことを意味します。つまり部屋の広さを表す際に、畳の枚数に準じた数値として使われますが、数学的単位としては面積の単位に近いものとして考えられています。
要するに、「畳数」は実物の畳の数で、「帖数」はその広さを表す単位・基準ということができます。こうした違いを理解していないと、不動産の広告や物件情報で混乱してしまうかもしれません。
帖と畳のサイズの違いと地域差、実際の広さについて
畳のサイズは全国で統一されているわけではなく、一部地域によって微妙な違いがあります。
一般的に「京間(きょうま)」と呼ばれるサイズは約95cm×191cmですが、
「中京間(ちゅうきょうま)」は約91cm×182cm、
「江戸間(えどま)」は約88cm×176cmと少しずつ小さくなります。
帖数はこの畳のサイズを基準にしているため、地域によって実際の一帖の広さも異なります。
例えば、2帖の部屋といっても、京間の2帖は約3.63㎡ですが江戸間の2帖は約3.10㎡と違いが出てきます。
このように、畳一枚のサイズは地域によって異なり、それに合わせて帖数も異なるため、実際の広さに若干の差が生じます。
帖数と畳数の違いを比べる表
| 単語 | 意味 | 基準 | 地域差 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| 帖数(じょうすう) | 部屋の広さを畳1枚分を基準に表した広さの単位 | 畳1枚の広さ | 地域差あり(京間、江戸間など) | 不動産広告、部屋の広さの目安 |
| 畳数(たたみすう) | 実際に敷かれている畳の枚数 | 実物の畳枚数 | 基本的になし(ただし畳サイズは地域差あり) | 和室の広さの実測値 |
なぜ帖数と畳数の違いを知っておくべきか?
現代の日本の住宅でも和室は根強い人気があり、生活の中で部屋の広さの目安として「帖数」がよく使われています。
しかし、一方で内見時に畳が敷かれていない部屋もあったり、フローリングの表記と混同してしまう場合もあり、 帖数と畳数の違いを覚えておくことが騙されないポイントとも言えます。
また、新築やリフォームの際に和室をどんなサイズで作るか相談するときにも、帖数の基準を理解しているとスムーズに話が進みます。
不動産情報やインテリア選びをする人は、必ずこの帖数・畳数の違いを抑えておきましょう。
「帖数」って単に畳の枚数のことかと思いがちですが、実は部屋の広さの単位として使われることが多いんです。でも面白いのが、畳の大きさって地域によって違うので、例えば東京の畳一枚の広さと京都の畳一枚の広さは違うんですよ。だから同じ『2帖』でもちょっと広さが違うということに驚きませんか?不動産の広告を見るときは、こうした地域差も覚えておくと役に立ちますよ!
前の記事: « アロマとハーブの違いをわかりやすく解説!香りと効果の秘密に迫る





















