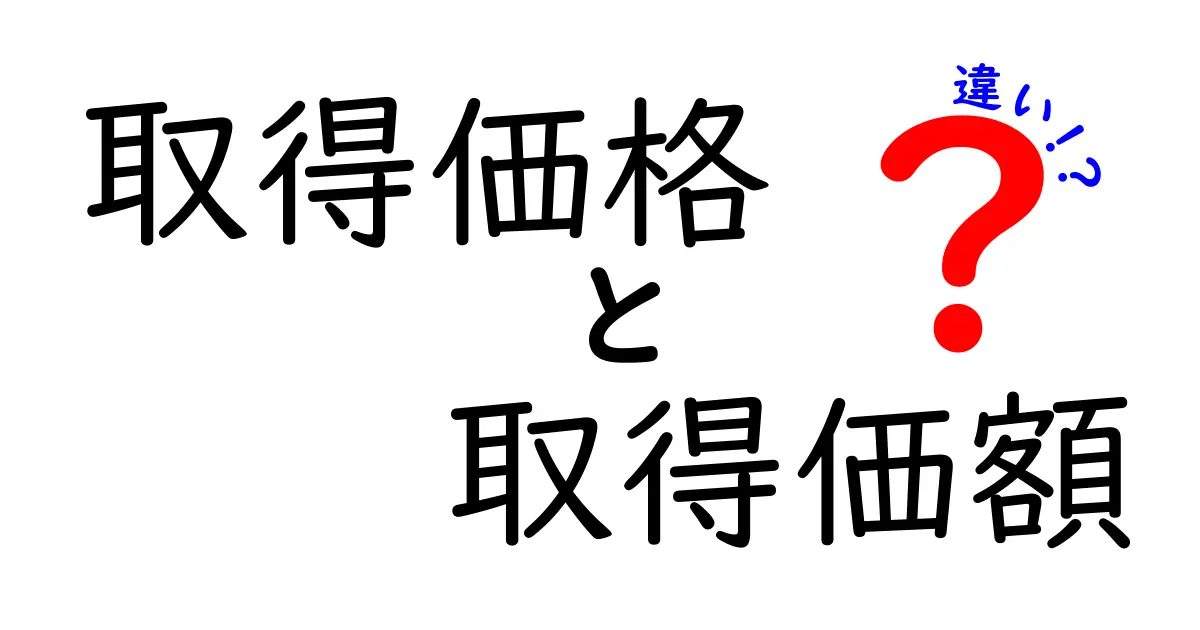

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
取得価格と取得価額の基本的な違いとは?
「取得価格」と「取得価額」は似た言葉で、どちらも物や資産を手に入れたときの値段に関わる言葉です。
でも、この二つは厳密にいうと意味が少し違います。
取得価格は、実際に買ったときに払った金額のことを指します。つまり、購入時点で支出した金額のことです。
一方、取得価額は取得価格のほかに、取得するためにかかったその他の費用も含むイメージです。
例えば、物を買うだけでなく、運送費や手数料、税金などその物を「取得するために必要な全ての費用」を含める考え方です。
この違いは会計や税法で特に重要で、数字の計算や申告を正しく行うために区別されています。
会計や税務での取得価格と取得価額の使い分け
会計や税務で両者は使い分けられ、決算書や申告書を作るときに役立ちます。
取得価格は「取得した物の原価」を示すものとして記録されます。
しかし、企業が資産を購入する際には、単に物の値段だけでなく、運搬費や設置費用、仲介手数料、関税などさまざまな費用がかかります。
これらを全部含めて「取得価額」と呼びます。
つまり、取得価額は取得価格より広い範囲の費用を含めた金額ということができます。
下記の表で違いをまとめてみました。
| 用語 | 意味 | 含まれる費用 |
|---|---|---|
| 取得価格 | 実際に支払った購入価格 | 物の値段のみ |
| 取得価額 | 取得にかかった全費用の合計金額 | 物の値段+運送費+設置費+手数料など |
なぜ取得価額の考え方が重要なの?
取得価額の考え方は資産の評価に欠かせません。
たとえば、中古品や建物、機械などを会計上で扱うとき、正しい資産価値を決めることが大切です。
購入費だけ見ると、正確なその資産の価値を反映しにくいため、取得にかかった全ての費用を足した取得価額で資産価値を示すと公平になります。
また、税法でも減価償却の計算に取得価額を使います。これにより、税金の計算が適正に行われることになり、税務トラブルを防ぐことにもつながります。
結果として企業が正しい会計処理や税務対応をするために「取得価格」と「取得価額」の違いを理解して使い分けることはとても大切なのです。
まとめ:取得価格と取得価額のポイントを押さえよう
ここまで見てきたように、
取得価格は購入した物の値段そのもの。
一方、取得価額は取得にかかる全ての費用を含めた合計額です。
この違いを理解することで、資産管理や会計処理、税務申告を正しく行えるようになります。
最後にもう一度ポイントを整理しましょう。
- 取得価格=購入価格だけの金額
- 取得価額=購入価格+関連費用全てを含んだ金額
- 会計や税法で使い分けが必要
難しく感じるかもしれませんが、生活や仕事の中でお金や資産を扱う際に役立つ知識です。
ぜひ覚えておいてくださいね。
取得価格と取得価額の違いを話すとき、意外と知られていないのが運搬費や手数料の扱いです。商品を買った値段だけ見ていると、あれっ?って思うかもしれませんが、実はこれらの費用も合算した金額が資産の価値として認められるんですよ。つまり、たとえ車を買うときの値段が同じでも、運送費や登録費用などが多ければ取得価額は高くなります。
この違いは会計上かなり大事で、見た目は似ているのに中身は違うんだなぁと感心してしまいます。
前の記事: « 付加価値税と増値税はどう違う?わかりやすく解説!
次の記事: 「卸価格」と「小売価格」の違いとは?初心者でもわかる基本解説 »





















