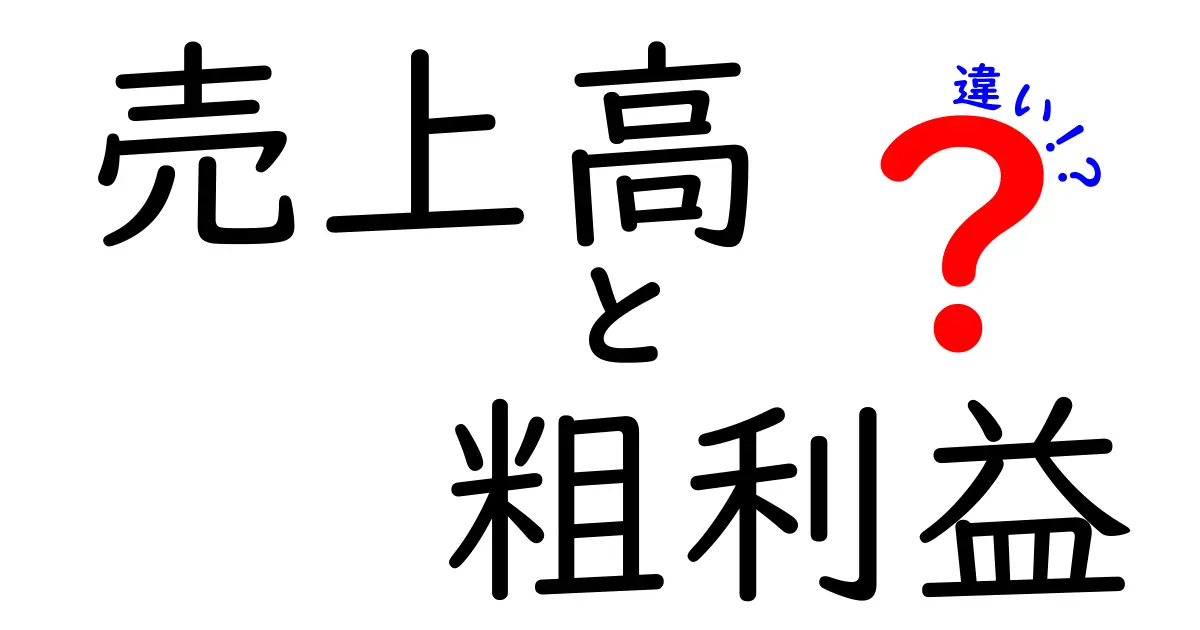

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
売上高と粗利益の違いとは?基礎から理解しよう
経営やビジネスに関わるとよく出てくる言葉に「売上高」と「粗利益」があります。どちらも会社の利益に関係する言葉ですが、実は意味が全く異なります。今回は中学生にもわかりやすいように、売上高と粗利益の違いをやさしく解説していきます。
売上高とは、会社が商品やサービスを販売して得た「全体のお金」のことです。例えば100円のりんごを10個売れば、売上高は1000円ですね。
一方で、粗利益は売上高から、その商品を作るためにかかった「原価(仕入れや製造費用)」を引いたものです。例えば、先ほどのりんごの場合、もし仕入れに50円かかったら、販売価格100円から50円を引いた50円が粗利益
つまり、売上高は売った金額の総額、粗利益は売上高から原価を引いた儲けの一部ということになります。
売上高の詳しい説明
売上高は会社やお店の収入の合計で、売れた商品やサービスの値段を全部足した数字です。特別な費用や固定費は含まれておらず、単純にお客さんからもらったお金の合計になります。
例えば、1カ月の間に合計で1,000,000円分の商品を売ったら、その期間の売上高は1,000,000円となります。
売上高は事業規模を表す大事な数字ですが、売上が多いからといって必ず儲かっているとは限らないので注意が必要です。売上が高くても、原価や経費が大きければ利益は少なくなります。
粗利益の詳しい説明
粗利益は売上高から商品を作るためにかかった費用(原価)を引いたものです。粗利益はどれだけ商品やサービスが利益を生んでいるかを見る基本の数字になります。
例えば、売上高が100万円で、商品を作るための原価が700,000円だったとします。この場合、粗利益は100万円 - 70万円 = 30万円となります。
粗利益は販売効率や商品力を判断するのに使われます。粗利益が高いということは、売上から費用を引いてもかなり利益が残っていると考えられます。
しかし、この粗利益からは、会社の家賃や人件費、広告費などの経費は引かれていません。このため、粗利益が高くても最終的な利益(純利益)とは別です。
売上高と粗利益の違いを表で比較
| 項目 | 売上高 | 粗利益 |
|---|---|---|
| 意味 | 商品やサービスの売れた合計金額(収入) | 売上高から商品の原価を引いた利益部分 |
| 計算式 | 販売価格 × 売れた数 | 売上高 - 原価(仕入れや製造費用) |
| 含まれないもの | 原価・経費 | 販売費・一般管理費などの経費 |
| 利用目的 | 会社の売上規模をはかる | 商品やサービスの利益率を評価 |
まとめ:売上高と粗利益の違いを押さえよう
売上高は会社が商品やサービスを販売して得た総収入の事であり、そこには費用は含まれません。一方、粗利益は売上高から商品を作るためにかかった費用(原価)を引いた利益です。
経営を理解する上で、単に売上が多いだけではなく、粗利益を見てどれだけ利益が残っているかを知ることが大切です。これからビジネスや経済を勉強する方は、この2つの数字の違いをしっかり覚えておきましょう。
売上高と粗利益の違いを話すと、意外と『売上が利益でしょ?』という認識の人がいます。でも実は売上高はお店のレジに入ったお金の総額だけで、そこから商品の仕入れや製造にかかった費用を引いたのが粗利益です。例えば100円のりんごを売って仕入れが50円なら粗利益は50円。商品の売れ行きだけでなく、この粗利益が高いか低いかでビジネスの体力が見えるって面白いですよね。
中学生の皆さんもお小遣い帳をつける時、入ったお金だけでなく、買ったものの値段を引くことを意識すると、売上と利益の違いが体感できるかもしれません。
次の記事: 利益構造と収益構造の違いとは?初心者でもわかる経営の基本ポイント »





















