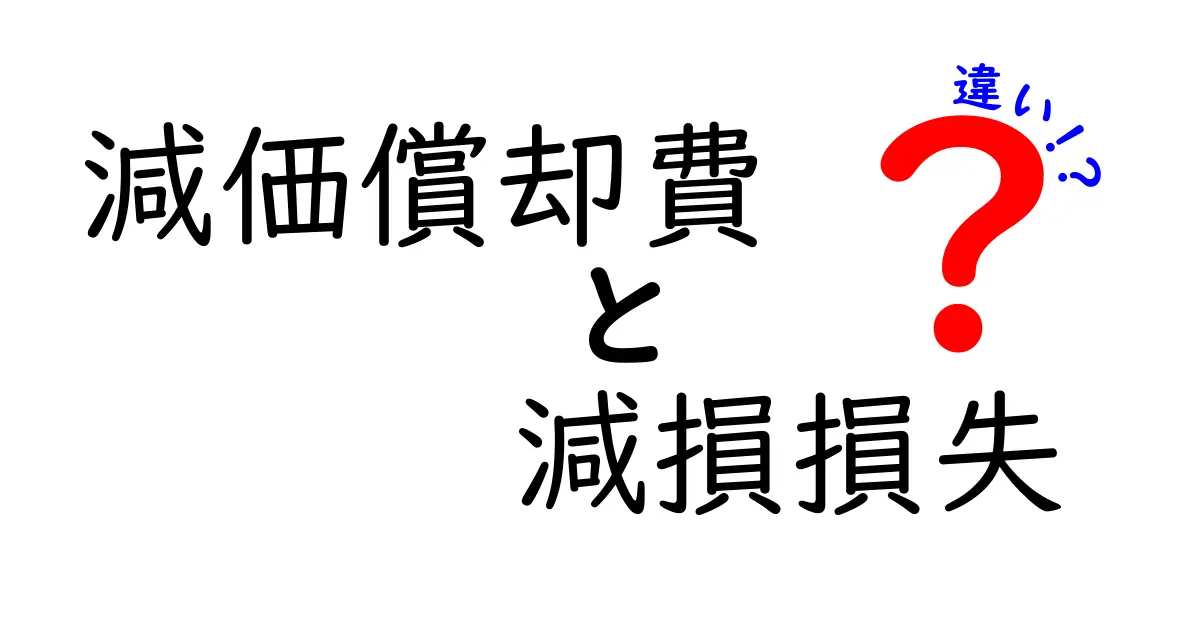

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
減価償却費とは何か?
まずは減価償却費について説明します。減価償却費とは、会社が持っている建物や機械、車などの資産が時間とともに価値を少しずつ失っていくことを会計上で表すための費用です。たとえば、10年使える機械を買ったら、その購入代金を10年間に分けて少しずつ経費として計上します。
これは現金がすぐに減るわけではありませんが、資産の価値が減っていく状況を会計上で正しく表すために必要です。
減価償却費があることで、会社の利益や税金の計算がより実際の経済状況にあったものになります。
わかりやすく言うと、大きなものを買ったときに、その値段を一度に費用にせず、少しずつ『使い古して価値が下がった』分だけ費用として計算する方法が減価償却費です。
減損損失とは?
次に減損損失についてです。減損損失とは、資産の価値が予想以上に急激に下がってしまったときに、その損失を会計上で認めることです。
たとえば、機械が壊れたり、時代遅れで価値がほとんどなくなってしまった場合、減価償却費ではまかないきれません。そんなときに一気に価値の下がった分を計上するのが減損損失です。
これは減価償却費のように時間をかけて分けて経費にするのではなく、急いで一気に損失として認める感じです。
つまり、資産の減価償却費が計画的な価値減少を表すのに対して、減損損失は予想外の大幅な価値減少を表します。
減価償却費と減損損失の違いをまとめる
ここまでで説明した2つの言葉の違いをわかりやすく表にまとめます。
| 項目 | 減価償却費 | 減損損失 |
|---|---|---|
| 意味 | 資産の価値を計画的に少しずつ費用にすること | 資産の価値が急激に大幅に下がった損失を一気に計上すること |
| 計上のタイミング | 毎年少しずつ計上 | 価値の大幅減少を発見した時点で一度に計上 |
| 対象資産の状態 | 通常の使用や時間経過 | 損傷、故障、環境変化などのための突然の価値下落 |
| 費用計上方法 | 分割して分散 | 一括で計上 |
まとめると、減価償却費は長い期間にわたって資産の価値が減っていくことを表す費用で、減損損失は急に価値が大幅に下がったときに発生する費用です。
この2つを正しく理解することは、会社の財務状態を正しく知るうえでとても重要です。
わかりやすく言うと、毎日使って古くなっていく時計の価値が少しずつ減るのが減価償却費で、時計が壊れてしまって価値が大幅に落ちたのが減損損失だとイメージしてください。
どちらも会社の資産価値を正確に表すために使われるものですが、計算方法や計上するタイミングが違うので混同しないように気をつけましょう。
減価償却費についてちょっと面白い話です。実は、この費用の計算にはいくつかの方法があって、「定額法」という毎年同じ額を費用にする方法と、使うほどに多く費用を計上する「定率法」があります。
定率法は機械や設備が新しい時ほどたくさん費用を計上し、古くなるにつれて少なくしていく方法です。使う期間や資産の性質によって選択できるので、会社ごとに少し違った会計処理をしていることもあるんですよ。
だから、同じ機械を持っていても会社によって費用が違うこともあるのが減価償却費の面白さの一つかもしれませんね。
前の記事: « その他有価証券と投資有価証券の違いとは?わかりやすく徹底解説!





















