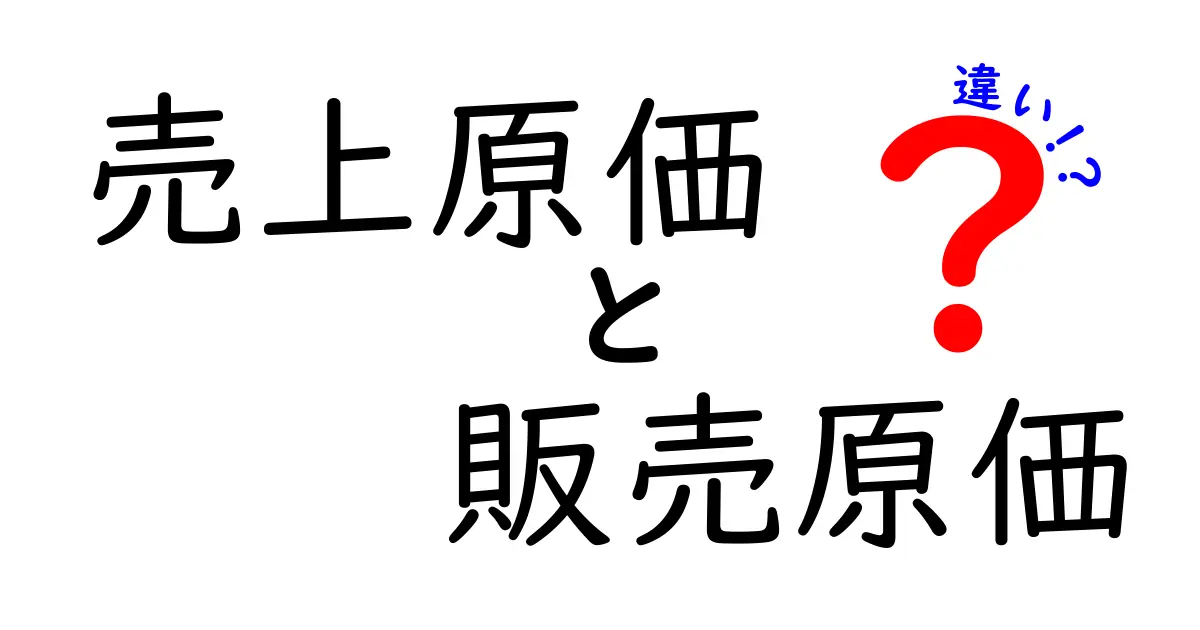

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
売上原価とは何か?基本をしっかり理解しよう
ビジネスの世界でよく耳にする「売上原価(うりあげげんか)」という言葉。
これは商品やサービスを販売するために直接かかった費用のことを指します。たとえば、製造業なら材料費や製造に必要な労働費が売上原価になります。
ポイントは直接的に商品を作るためのコストであること。売上原価は、売り上げた商品を生み出すための直接の経費なので、会社の利益を計算するときに重要な役割を持っています。
具体的には、売上原価は売上高から引くことで、粗利益を出す際に使われます。粗利益は会社の基本的な儲けの目安なので、売上原価はとても重要です。
売上原価を正確に管理することで、どれだけ効率よく商品を生産しているかがわかり、経営の改善にもつながります。
販売原価とは?売上原価との違いをチェック
一方で「販売原価(はんばいげんか)」という言葉もありますが、これが売上原価と混同されやすいポイントです。
販売原価は文字通り、商品を販売するためにかかった費用を表しますが、実は使われ方が会社や分野によって少し異なります。
基本的には、販売管理費(広告費や運搬費など販売活動の費用)を含めない「売上原価」が一般的に使われる用語として定着しています。
販売原価は売上原価とほぼ同じ意味で使われるケースもありますが、販売に関する費用を含む場合があるため、細かい使い分けが大切です。
例えば、販売活動に伴う費用まで含めるなら販売原価、原材料費や直接労務費のような製造にかかる費用だけなら売上原価、といった理解が良いでしょう。
売上原価と販売原価の違いを分かりやすくまとめた表
以上のように、売上原価と販売原価は似ているようで違いがあります。
何が直接商品を作るための費用かを理解し、どの範囲の費用を含めるかを明確にしておくことがポイントです。
経営や会計の場面で正しく用語を使い分けられるようにしっかり覚えておきましょう!
売上原価という言葉はよく使われますが、なぜこんなに大切か知っていますか?売上原価は商品を作るための直接的な費用なので、これを下げられれば会社の利益は増えます。つまり、効率よく安く商品を作ることができれば、自然と儲かる仕組みになるわけです。材料費の見直しや作業の短縮が売上原価削減のカギ。普段意識しにくいですが、会社の健康状態を知る大切な指標なんですね。
前の記事: « 原価率と限界利益率の違いとは?初心者向けにわかりやすく解説!





















