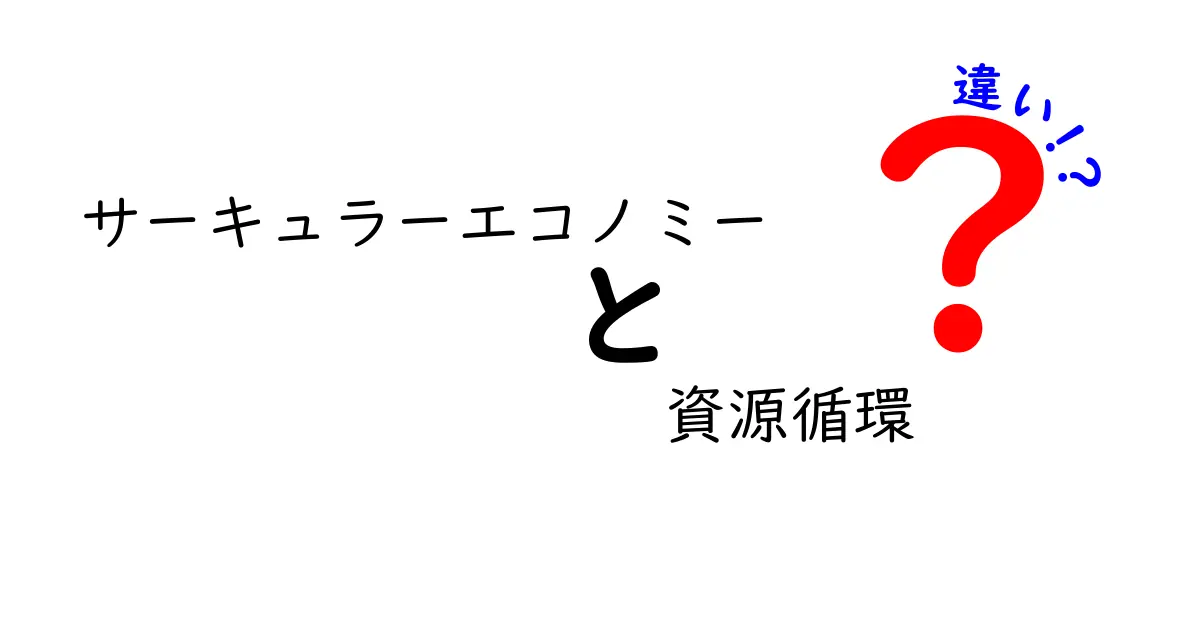

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サーキュラーエコノミーとは何か?
サーキュラーエコノミー(循環型経済)は、わかりやすく言うと“ゴミを減らして、資源を大切に使い続ける経済の仕組み”です。
たとえば、ビジネスの世界で、商品が使われ終わったらその材料を回収して再利用したり、修理して長く使ったりする方法が含まれます。
特徴は、資源を“捨てずに何度も使う”ことによって、新しい資源の消費を減らし、環境への負担を軽くする点にあります。
サーキュラーエコノミーは経済活動全体の仕組みを見直して、持続可能な社会を目指す考え方です。単にリサイクルするだけではなく、設計段階から材料の再利用を考えるなど、全体的な流れを変えていきます。
資源循環とは何か?
資源循環は、“資源が無駄なく使われて、回り回る仕組み”という意味です。
資源循環の考え方は昔からあり、リサイクルや再利用、そしてゴミの分類など、資源が使い終わった後に別の形で再び使われる流れを作ることです。
わかりやすく言うと、紙やプラスチックなどを回収して新しい製品に再生させたり、コンポストで生ごみを肥料に変えたりする活動が資源循環の一例です。
つまり資源循環は資源の“廃棄を減らして再利用を促進する”ことであり、環境を守る具体的な行動に近いものです。
サーキュラーエコノミーと資源循環の違い
「サーキュラーエコノミー」と「資源循環」は似ていますが、実は範囲や視点が違います。
以下の表で整理してみましょう。
| ポイント | サーキュラーエコノミー | 資源循環 |
|---|---|---|
| 意味 | 経済全体で資源を循環させる仕組みや考え方 | 資源を廃棄せず再利用・リサイクルする工程や活動 |
| 範囲 | 製品設計、生産、流通、消費、廃棄までの全体の仕組み | 主に資源の回収・再利用・リサイクルの場面 |
| 目的 | 持続可能な経済成長と環境保護の両立 | 環境負荷の軽減と資源の有効利用 |
| 取り組み例 | 製品設計の見直し、サービス化、再生可能素材の活用 | リサイクル工場、分別回収、廃棄物の再利用 |
簡単に言うと、サーキュラーエコノミーは経済やビジネスの大きな枠組みで、資源循環はその中の“具体的な資源を循環させる活動”です。
だから資源循環はサーキュラーエコノミーの一部と考えられます。
まとめ
サーキュラーエコノミーは、資源を捨てずに価値を長く持たせて繰り返し使うことで、経済活動全体を持続可能にする考え方です。
一方で資源循環は、資源が廃棄されるのを減らしてリサイクルや再利用を進める仕組みや活動を指します。
この二つは似ていますが、スケールや視点が違い、資源循環はサーキュラーエコノミーの重要な要素の一つとして位置づけられます。
今後、環境問題を考える上でどちらの理解も大切です。日常生活でもリサイクルを心がけることや、長く使える製品を選ぶことが、サーキュラーエコノミーの実現につながります。
ぜひこの違いを知って、環境にやさしい生活を目指しましょう!
サーキュラーエコノミーの面白いところは、ただ単に『リサイクルを増やす』というだけでなく、商品の作り方そのものを変えてしまうところなんです。例えば靴を作るときに、簡単に分解できて部品だけ交換できる設計にすることで、使い終わったあとも長く使い続けられるようになります。これは従来の『使い捨て』の考え方とは全く違い、ものづくりの段階から環境に配慮する新しい挑戦なんですね。こうした視点は中学生にもぜひ知ってほしい大切な考え方です。





















