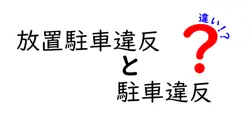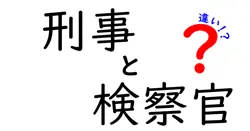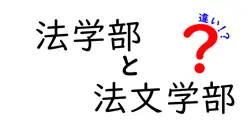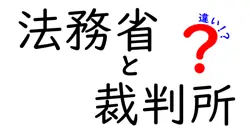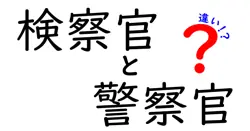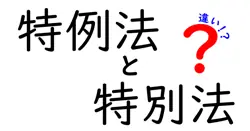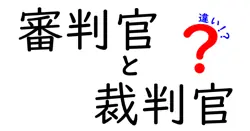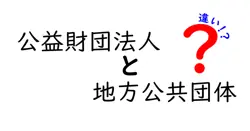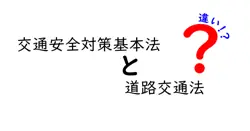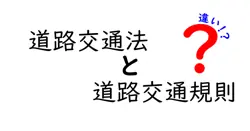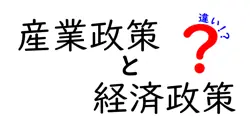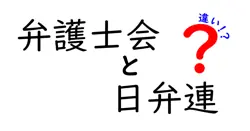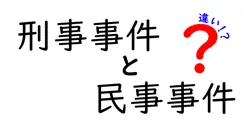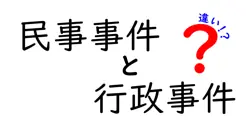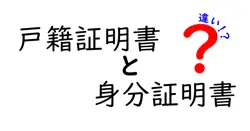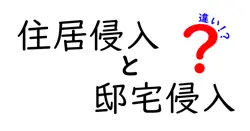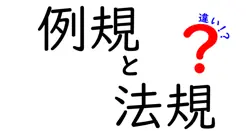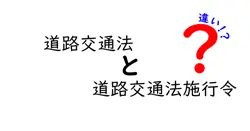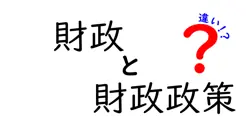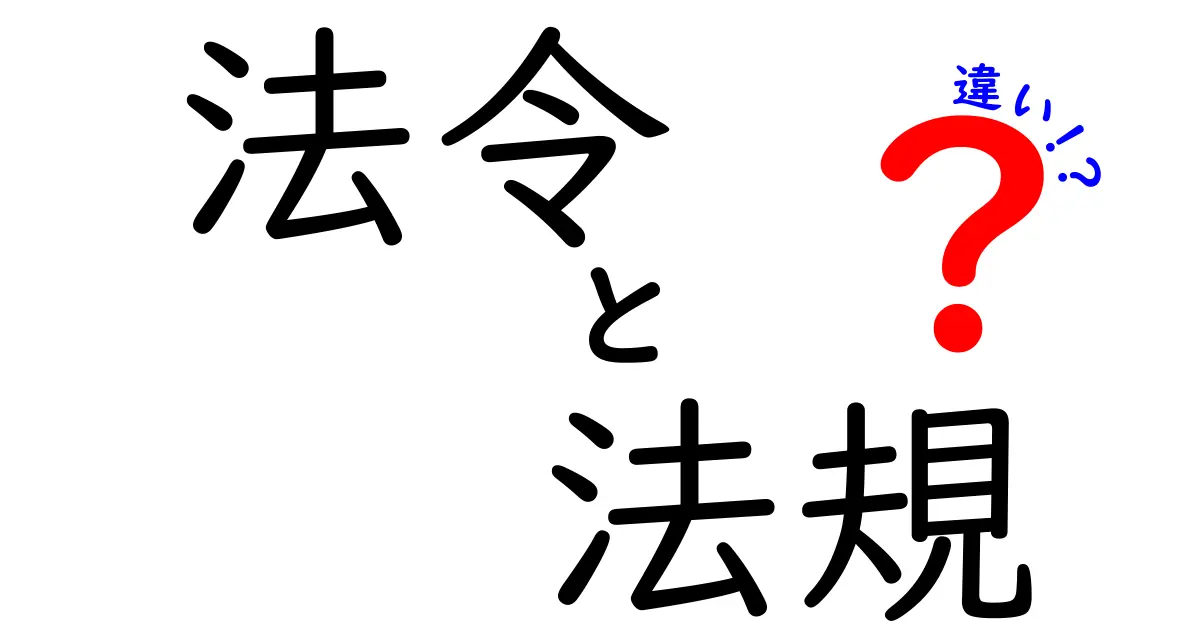
法令と法規の違いとは?基本のキホンを学ぼう
日本の法律の世界では「法令」と「法規」という言葉がよく使われます。どちらも法律のルールに関係していますが、実は意味や使い方に違いがあります。
まず「法令」は、憲法や法律、政令、省令などの全部をまとめた言葉です。つまり国がつくる公式なルールのすべてを指しているんですね。
一方で「法規」は、もっと範囲が狭く、主に法律や条例、規則などの守るべき規則やルールのことを言います。
このように、法令は法律関係の強いルール全体を示す言葉で、法規はその中の「守るべき規則」にフォーカスした言葉だと覚えておきましょう。
法令にはどんな種類がある?具体例で見てみよう
法令は実は細かく分かれていて、主に次のような種類があります。
- 憲法
国の基本ルールを書いた最も大事な法律 - 法律
国会が決める具体的なルールのこと - 政令
内閣が出す法律を実施するための細かい決まり - 省令
各省庁が専門的に定めるルール
これらが全部合わせて法令と呼ばれます。たとえば「道路交通法」や「労働基準法」も法令の一つです。
こうした法令は、法律の判断や生活のトラブル解決に欠かせないもの。「法令集」と呼ばれる冊子やネット上で誰でも見られる資料があるので、興味があれば一度見てみると良いですね。
法規は守るべきルール!具体例と法令との違い
一方「法規」は法令より範囲が狭く、簡単にいうと実際に守らなければいけない決まり事です。
例えば、法律で「高速道路は時速100キロを超えてはいけない」と定められていたら、これが「法規」です。
また、市区町村が作る条例や学校、会社で決める規則も法規の一部と捉えられます。つまり法令に書かれたルールや命令の中で、具体的に守るべきものが法規と呼ばれることが多いです。
法律用語では細かい区別があるものの、日常生活ではこのように理解すると失敗が少ないでしょう。
法令と法規を比較した表でまとめてみる
簡単に見やすいように、法令と法規の違いを表にまとめてみました。
| ポイント | 法令 | 法規 |
|---|---|---|
| 意味 | 憲法・法律・政令・省令などの正式なルール全般 | 法律や条例、規則など守るべきルール |
| 範囲 | 広い(法律関係のルール全般) | 狭い(守るべき具体的ルールに限定) |
| 制定者 | 国会・内閣・各省庁 | 国会、市町村、各団体など |
| 例 | 憲法、労働基準法、道路交通法、政令 | 交通ルール、学校の規則、市の条例 |
この表のように「法令」は公式で幅広いルールや法律全体を指し、「法規」はその中でも特に人や団体が守らなければならない細かい命令や決まりごとと言えるのです。
法令と法規は似ている言葉ですが、実はその使い方には面白い違いがあります。特に「法規」は守るべきルール自体を指すことが多く、学校の校則や交通ルールなど身近なルールも法規の範囲に含まれることがあります。
また、同じ法令の中でも「法律」と「政令」は作る機関が違い、その役割も異なります。法律は国会が決める基本のルール、政令はそれを実行するために内閣が細かく決めるルールです。
こう考えると、日本のルール作りはピラミッドのようになっていて、上に行くほど基本で広いルール、下に行くほど具体的で細かいルールになっていることがわかりますね。
身の回りのルールもこの仕組みの一部だと考えると、ルールの理解がちょっと楽しく、意味深くなりますね!