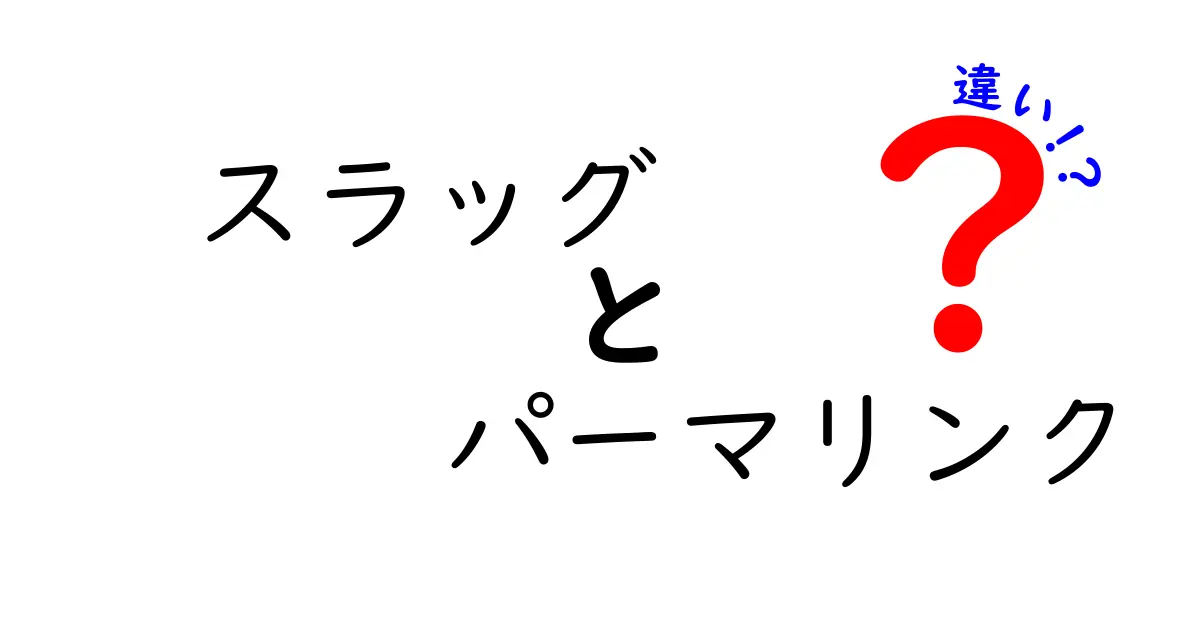

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スラッグとは何か
スラッグはURLの中で記事やページを識別する“短い語句”のことです。たとえば、https://example.com/slug-difference のように、ドメインの後ろに続く部分がスラッグです。スラッグは英数字とハイフンで構成され、読みやすさとSEOの両方を意識して作るのが基本です。スラッグは基本的に1記事につき1つ決め、重複を避けるためサイト内で一意である必要があります。
読みやすさのポイントとして、長すぎず、先頭から順に意味が伝わる語を選ぶことが大切です。特に日本語をローマ字化して slug にする場合は、単語と単語の間をハイフンでつなげ、不要な語を削る工夫をします。
例として「スラッグとパーマリンクの違いを学ぶ」と書くときには、slugは「slug-to-permalink-difference」のように英字表記にするか、あるいは「slug-to-permalink-difference」(typo)など、意味を分かりやすく短くまとめる方法を選びます。
このように slug はURLの“見た目”と“識別力”を同時に担う重要な要素であり、記事を検索結果で見つけてもらいやすくする第一歩になります。
パーマリンクとは何か
パーマリンクは、ウェブサイトの特定の記事やページへ直接つながる“永続的なリンク”のことを指します。通常はドメイン名の後ろの全体のURLを意味し、スラッグがその一部であり、パーマリンク全体としての形を作ります。パーマリンクの設計はサイト全体のSEOやユーザー体験に影響します。一般的なCMSではパーマリンクの構造を設定でき、%year%/%month%/%postname%/ のような表示形式を選ぶことがあります。
パーマリンクは読み手が一度覚えれば再訪問時にも同じURLでアクセスできる利点があり、ソーシャルシェア時にも安定して機能します。
この概念の違いを理解するには、スラッグがURLの“個別の語”であるのに対し、パーマリンクがその語を含む“URL全体の設計”であると捉えると理解が深まります。
例えば、記事タイトルがスラッグとパーマリンクの違いを解説するなら、slug は「slug-vs-permalink-difference」、permalink は全体の URL「https://example.com/2025/08/slug-vs-permalink-difference/」の形になります。これを理解しておくと、後からURLを変更する必要が出たときも対応が楽になります。
スラッグとパーマリンクの違いを押さえる3ポイント
第1ポイントは「位置と役割の違い」です。スラッグはURLの末尾にある短い語句で、記事を識別する役割を持つ一方、パーマリンクはその語句を含むう全体のURLの設計です。
第2ポイントは「変更の影響範囲」です。スラッグを変えると特定の記事のURLが変わり、旧URLへのリンクや検索結果のリンクが壊れる可能性が高くなります。
一方でパーマリンクの構造自体を変えるとサイト全体のリンクパターンが変わることがあり、広範囲に影響します。
第3ポイントは「SEOと運用」です。スラッグは適切なキーワードを選ぶと検索の手掛かりになりますが、過剰なキーワード詰めは避けるべきです。パーマリンクは安定性と読みやすさを両立させる方が長期的に有利で、短くて意味の伝わる形を目指すのが基本です。
実務での使い分けと注意点
実務での slug と permalink の設計は、最初に方針を決めておくことが結局は最も楽です。 slug は日本語をローマ字化して使うケースと、日本語そのままのケースの二択になりやすいですが、一般的には英字+ハイフンで表現するのが読みやすさ・移植性の面で安定します。 こんばんは。今日は slug の話を雑談風に深掘りします。 slug はURLの顔のようなもので、読者が検索結果で最初に目にする部分です。私が初めて slug を意識したとき、長くて難解な語を避け、短く意味が伝わる語にする大切さを痛感しました。 slug を決める基準は二つ。読みやすさと一意性です。読みやすさは英字表記にしてハイフンで単語をつなぐと、検索エンジンにも理解されやすく、外国語環境でも安定します。一意性はサイト内で他の記事とぶつからないようにすること。もし他の記事と同じ slug が出てきたら、末尾に数字を足すか別の表現に変える工夫をします。私は日常的に slug を作るとき、まず要点を3語程度に絞り、語順を自然な日本語の語順に近づける英語表現か、日本語そのままの表現かを場面で使い分けています。 slug の設計一つでサイトの第一印象が変わることを知っているので、今後も小さな改善を積み重ねるつもりです。
注意点として、記事タイトルの変更がURLに直結する場面が多いため、タイトル変更を前提に運用する場合は 301 リダイレクトの設定を忘れずに。内部リンクの修正と合わせて、外部リンクの影響も点検します。
現場では、スラッグは意味が伝わる短さと独自性の両立、パーマリンクはサイト全体の整合性と長期的な安定性を重視して設計します。例として、スラッグとパーマリンクの違いという記事であれば slug は「slug-vs-permalink-chigai」、permalink はhttps://example.com/2025/08/slug-vs-permalink-chigai/ のようになります。
また、SEO対策としては 一致するキーワードを自然に盛り込みつつ、過剰な詰め込みは避け、読者の理解を最優先にします。
最後に、実務での運用ツールとして Google Search Console や Analytics、リダイレクト管理ツールを活用し、404 の監視と定期的な見直しを行うことが大切です。項目 スラッグ パーマリンク 意味 記事識別用の短い語句 URL全体の固定リンク 位置 URLの末尾の一部 ドメイン以降の全体構造 影響 変更でURLが変わる 構造変更はサイト全体へ影響 SEOポイント キーワードを適切に 安定性と読みやすさ 実務の注意 一意性・短さ 整合性・リダイレクト
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















