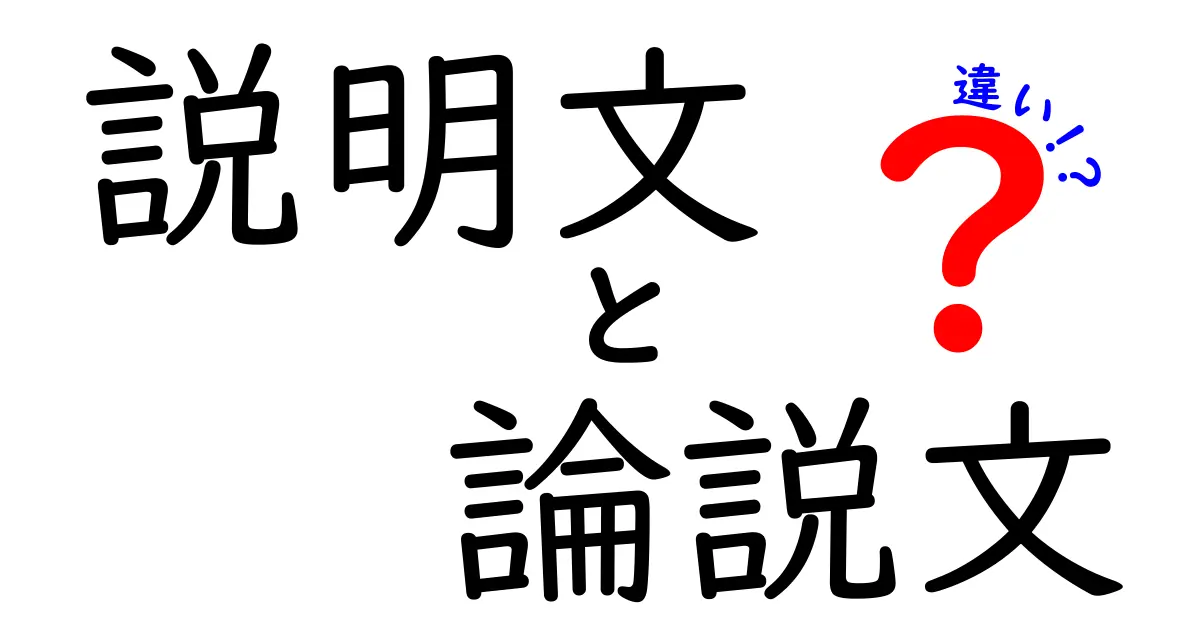

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
説明文と論説文の違いを理解するための基本ポイント
説明文と論説文は、日常の文章を理解するうえで基本となる二つの書き方です。説明文は情報の正確さと分かりやすさを重視し、読者に新しい知識を提供します。一方、論説文は自分の意見を主張し、読者の考えを動かすことを目的とします。この違いを押さえると、教科書やニュース記事、作文の課題を読むときに、どの部分が事実なのか、どの部分が筆者の主張なのかがはっきり見えるようになります。まず大事なのは「目的」です。説明文は情報を正確に伝えることを最優先にします。論説文は読者の理解を深め、賛成・反対の立場を示し、結論へと誘導します。次に「根拠と証拠」の扱いが違います。説明文はデータ、事実、定義、手順などを並べ、読み手が自分で判断できる材料を提供します。論説文は筆者が選ぶ根拠を組み合わせ、読み手の心に訴える理由づけを作ります。文章の語り口にも差が出ます。説明文はニュートラルで客観的な語調を保つことが多く、感情を控えめにします。論説文は情熱や比喩、強い語感を使い、読者の感情にも働きかけることがあります。説明文の構成は、見出しや箇条書き、図表などを取り入れて事実を整理するのが一般的です。一方、論説文の構成は、問題提起→主張 → 根拠の提示 → 反論の処理 → 結論という順序で進むことが多く、読み手に「この意見を受け入れるべきだ」と思わせる工夫が施されています。これらの要素を意識して読むと、同じ話題でも説明文と論説文の読み方が分かり、情報の真偽と主張の意味を正しく評価できるようになります。
特にニュース記事や教科書、レポートでは、説明文と論説文が混在していることもあります。読者は文中の「事実」なのか「筆者の見解」なのかを区別する練習をすると良いでしょう。見出しだけで判断せず、本文の具体的な根拠や数字、引用を確認するクセをつけると、情報の受け取り方がずっと冷静になります。最後に覚えておきたいのは、どちらの文章でも「読み手を想定した伝え方をしている」という点です。読み方を変えると、同じ文章でも受け取る意味が変わります。
ねえ、説明文と論説文の違いって、難しそうに見えて結構シンプルなんだよ。説明文は“情報を正しく伝える”ことが目的だから、数値やデータ、手順などを客観的に並べることが多いんだ。たとえば科学の教科書の説明ページや百科事典の解説文は、説明文のいいお手本。対して論説文は“読者を動かす”ことを最終目標にするから、筆者の意見を根拠とともに示して、結論へと導こうとする。だから同じテーマでも、説明文には感情が少なく、論説文には説得力のための工夫が盛り込まれていることが多い。ここで大切なのは、読み手として自分が何を求めているかを決めること。新しい知識を得たいなら説明文を、自分の考えを深く考えたいなら論説文を優先的に読むと、情報の取り扱い方がぐんと上手くなる。私たちがニュースを読むときも、まず“事実か意見か”を分けて、続く根拠を確認する癖をつけると、偽情報や感情的な誘導に惑わされにくくなるよ。だから次に記事を読むときは、先に結論を見ずに、どの部分が事実でどの部分が筆者の主張なのかを意識して読み始めてみよう。そうすると、同じ話題でも新しい発見がきっと見つかるはずさ。





















