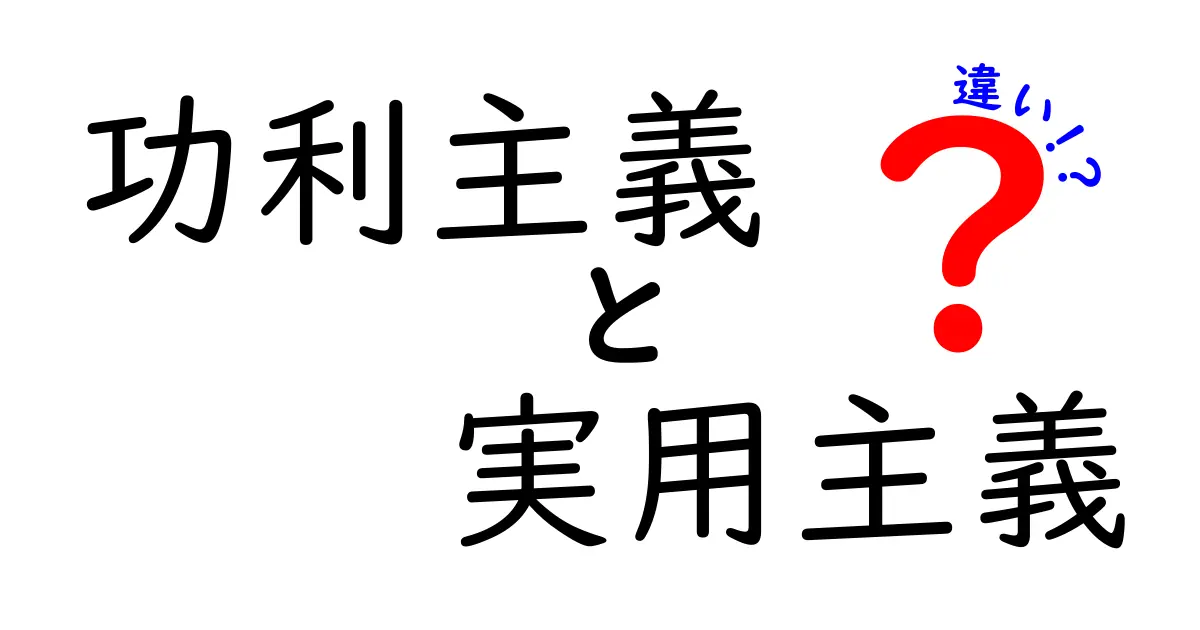

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
功利主義と実用主義の違いを徹底解説
はじめに、功利主義と実用主義は私たちがどう判断するかを考えるときの重要な考え方です。
この二つは似ているところもありますが、何を「よい」とみなすかの基準が違います。
功利主義は社会全体の幸福を最大にすることを目的とする倫理理論であり、行動の良し悪しを生まれる幸福の総量で評価します。
実用主義は知識や考え方の正しさを決める基準を別の観点に置きます、それは現実の生活に役立つかどうかという点です。
つまり、最大幸福という結果が重視されるか、使えるかどうかという実用性が重視されるかの違いです。
この二つの考え方を理解すると、ニュースや日常の議論を整理する手がかりになります。
以下では、特徴を詳しく見ていきます。
1. 基本の考え方を比較する
功利主義は「行動の結果として生じる総幸福量」を最も大切にします。誰がどれだけ幸せになるかを数え、総和の最大化を目指します。具体的には、Aさんを助けるとBさんとCさんの幸福がどう変わるかを比べ、全体として幸福が増える選択を選ぶことが基準です。ただしこの考え方には、少数の人が苦しむことを正当化する可能性がある点が議論の的になります。
これに対して実用主義は「その考え方が現実の問題を解決するか」を最優先します。理論的に正しいかどうかよりも、現場で使えるかどうか、実際の結果がどうなるかを観察します。新しいアイデアを試してみてうまくいけば採用し、うまくいかなければ修正するという柔軟さが特徴です。
この二つの違いを頭の中に置いておくと、難しい倫理の話題でも「何をもって正しい判断か」という問いに対して、さまざまな角度から考えられるようになります。
2. 日常の例で見る違い
日常の場面での違いを具体的な例で考えてみましょう。学校のルール作りを例にすると、功利主義なら全体の幸福を最大化するための配慮を第一にします。例えば、多くの生徒が楽しめるイベントに多くの資源を配分し、少数の生徒には制限を課すという判断も生まれるかもしれません。これは結果として全体の満足度を高めることを狙います。一方で実用主義では「このルールが現場で機能するか」を最優先します。実際に試してみて、予算の都合や実施の難易度と照らし合わせ、必要に応じてすぐに変更します。こうした実験的な進め方は、現実の問題解決に強い点が特徴です。
比較表を使うとより分かりやすくなります。項目 功利主義 実用主義 評価基準 総幸福の最大化 実用性と結果 調整の仕方 多くの人の幸福を優先 現場での修正を前提 局所的影響 少数の不幸を許容する場合がある 現場での使える解決を重視
このように表で並べて見ると、違いがはっきりと見えます。
最後に大切な点は、どちらの考え方にも長所と課題があるということです。
私たちは日常の決断で、時には「総幸福量を最大化する」必要がある場面、時には「現場で使える解決を優先する」場面を選び分ける力を磨くことが重要です。
ある日の放課後の話です。友だちと功利主義と実用主義のどちらを支持するかで盛り上がりました。功利主義は全体の幸福を考える考え方で、たとえば文化祭の予算をどう配るかを決めるとき全体の満足度を最大化する方を選ぶ、という発言が出ます。実用主義は「この方法が役立つかどうか」を最優先します。現場で試してみて、失敗したらすぐに修正するという考え方です。正直、どちらが正しいかを決めるのは難しい場面もあります。私はこの話を通じて気づいたのは、実用性と幸福の影響の両方をバランスよく見る視点が大切だということです。だから、日々の決断も「使えるかどうか」を最優先しつつ、誰かが傷つかないかを意識していきたいと感じました。さらに友だちと私は、先生が出す課題の取り組み方についても雑談しました。ある課題は時間がかかるが結果が良くなる可能性が高い、別の課題は早く終わるが成果が薄いかもしれない。そんなとき私たちは互いに意見を出し合い、できるだけ多くの人にとってメリットがある選択を探そうとします。こうした対話を通して、哲学的な話が遠いものではなく日常生活の道具になることを実感しました。
前の記事: « 5W1Hと5W2Hの違いは? 基本から使い分けまで徹底解説





















