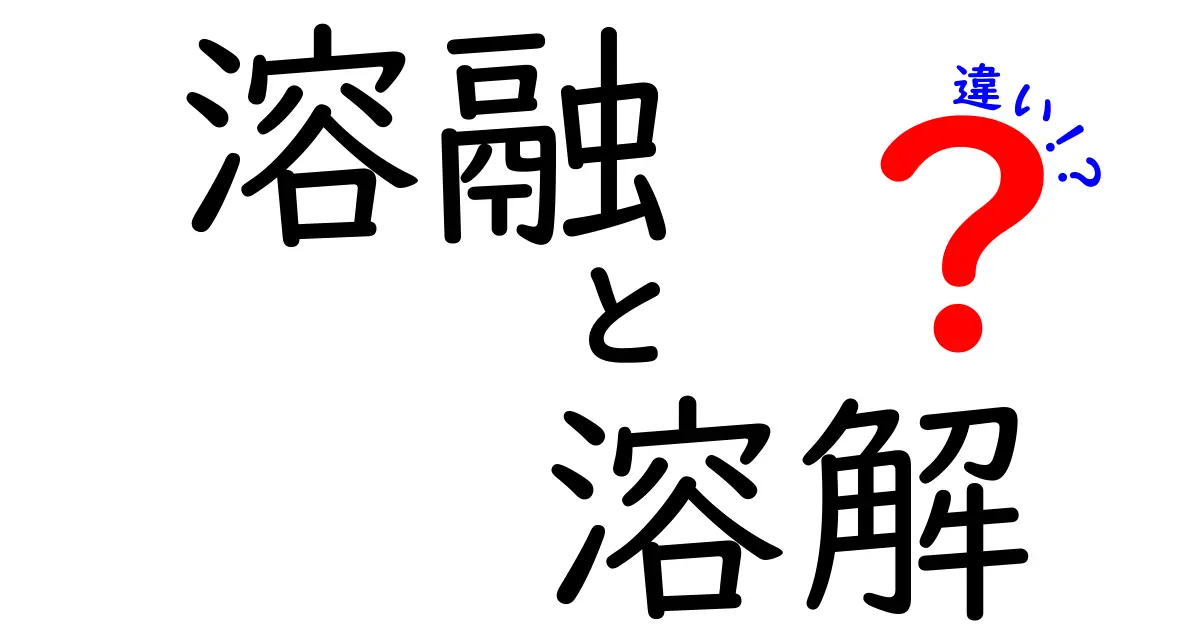

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:溶融と溶解の違いを知ろう
日常で私たちは氷が溶けて水になるのを見ます。この現象は溶融と呼ばれ、物質が固体から液体へと状態を変える大事な相変化です。
溶融はただの温度の変化ではなく、分子の結びつきが緩み、自由に動けるようになることを意味します。アイスキューブが机の上で小さくなり、やがて完全に液体になる様子をイメージするとわかりやすいでしょう。
対して 溶解 は別の現象です。固体の物質が液体の中に分散して、見た目には固体の粒がなくなるように感じますが、実際には分子が液体の中で新しい場所を得て混ざり合います。
この違いを押さえると、実験の結果を見るときに「物質がそのまま別の状態になったのか、それとも別の物質の中にうまく入り込んだのか」を判別できるようになります。
溶融とは何か:状態の変化を見てみよう
溶融は固体が熱を受けると分子の振る舞いが大きく変わることが分かります。融解熱という量が必要で、物質ごとに違う温度で起こります。たとえば氷の融点は0℃で、鉄の融点はとても高い温度です。溶融は相変化なので、溶けても同じ物質の液体として存在します。体積がわずかに変わることもあり、液体になったあとの流れや粘り気も変化します。実験では温度計を使って温度を測りながら、融点付近で氷が急に動き出す様子を観察すると、現象の全体像が見えやすくなります。
溶解とは何か:新しい混ざり方を学ぶ
溶解は別の現象で、溶質と溶媒が互いに“分子の道”を作って混ざり、均一な液体ができる過程です。水に砂糖を入れると砂糖の粒は消えるように見えますが、実際には分子が水の分子の間を潜り込み、周りを取り囲んでいます。溶解は溶解熱を伴い、溶質と溶媒の相互作用の強さが速さを決めます。一般に分子間の引力が強く、水との相互作用が良いほど溶けやすいです。逆に油は水と混ざりにくい性質を示します。溶解度という概念があり、一定の温度でどれだけ溶けるかを表します。温度が上がると多くの固体溶質はよく溶けることが多いですが、エネルギーの出入り、圧力、溶媒の種類によって結果は変わります。溶解は体積の変化を少なくする場合もあれば、大きくなる場合もあり、混ざった後の味や色、粘度に影響します。
今日は溶解を深掘りする雑談形式で話します。友達と理科の話をしているとき、溶解は砂糖を水に消してしまう現象のように見えることが多いですが、実は分子の動きがカギです。温度が高いと速く溶けやすい、低いと遅い。水と油の混ざりにくさも溶解の話とつながります。こうした身近な体験を通じて、科学の面白さを感じてほしいです。





















