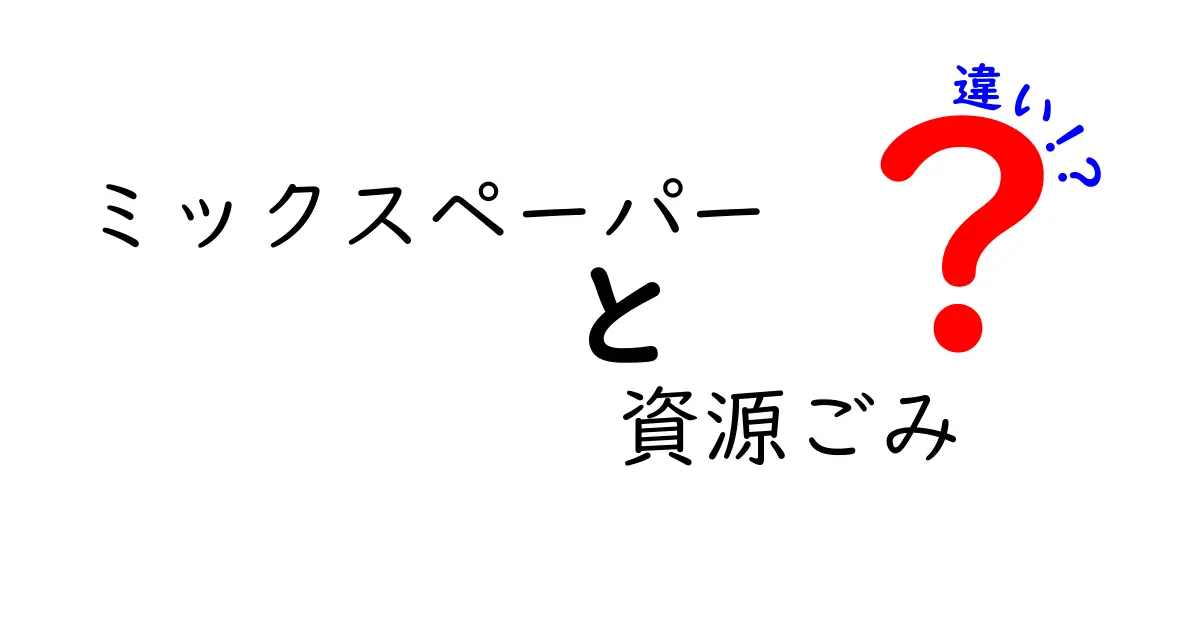

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ミックスペーパーと資源ごみの違いを徹底解説
近年、家庭から出る紙の分別で、ミックスペーパーと資源ごみの違いがわからず困る人が増えています。まず前提として、日本のごみ分別ルールや名称は自治体ごとに異なります。ミックスペーパーは、紙でできた包装や印刷物をまとめた「紙類」のひとつですが、資源ごみの中で扱いが変わることがあります。ミックスペーパーと資源ごみの違いを理解する鍵は、素材の性質と清潔さ、そして地域の収集ルールです。例えば、新聞はミックスペーパーとして出せる場合が多いのですが、紙袋にビニールの加工がしてある場合は特性が変わることがあります。また、ダンボールはミックスペーパーではなく資源ごみの紙として出すことが求められる場所もあり、細かい分け方は自治体の案内板に従うのが確実です。ここでは、よくある疑問を整理し、実生活で役立つポイントを紹介します。
結論として、正しい分別のコツは“地域のルールを確認する”“紙は水分を避けて乾燥させる”“汚れや粘着のある紙は避ける”ことです。これらを守れば、リサイクルの品質を保ち、資源をムダにしません。
ミックスペーパーとは何か
ミックスペーパーとは、新聞、雑誌、カタログ、紙袋、薄紙の紙箱など、印刷された紙製の資源のうち、プラスチックを含まないものをまとめて出すためのカテゴリです。地域によって含まれるものが微妙に異なることがありますが、基本的には「きれいで乾燥している紙」を対象にします。湿っている紙、油分がついた紙、ティッシュペーパーやハガキの裏紙、感熱紙などはミックスペーパーの対象外になることが多いです。また、紙の表面に金属やプラスチックの加工がされているものは、除外されたり別の区分になることがあります。分別時のポイントは、紙の間に挟まる金属粘着テープをはがす、包んだ薄い包装材を取り外す、光沢のあるコーティングがある紙は別扱いかどうかを確認することです。地域のルールが変わる場合もあるので、自治体の案内を必ず確認してください。
資源ごみの定義と分別ルール
資源ごみは、リサイクルの対象として自治体が回収する資源の総称です。紙類だけでなく、瓶・缶・ペットボトル・プラスチック製品・金属製品・ガラスなど、再利用を目的とした素材を広く含みます。紙の分野では、ミックスペーパーと同様に紙の汚れや湿気を避け、可能なら広げて乾かす、封筒のテープや粘着剤を剥がす、ホチキス跡を取り除くなどの下処理が求められます。紙以外の素材は、別の資源ごみのカテゴリに分けて出します。注意点は、地域ごとに紙の「再生の品質を高めるためのルール」が違う点です。地元の自治体が発行するパンフレットやウェブサイトには、回収日や分別の細かな規定が載っていますので、出す前に必ず確認しましょう。
実生活での分別のコツとよくある誤解
日常生活での分別は、難しく見えるかもしれませんが、基本を覚えると案外簡単です。とくに、ミックスペーパーは乾燥・清潔さが命。新聞や雑誌をまとめる際には、表紙や中身の紙がくっついていないか、油分がついていないかをチェックします。うっかり水分がつくと、リサイクル過程で紙が固くなり、破砕機に引っかかってしまうことがあります。だから、使い終わった紙は風通しの良い場所で乾かしてから束ねてください。次に資源ごみの紙については、段ボールを小さく潰してまとめ、角を折りたたんで平らにすると、搬送・選別が楽になります。さらに、自治体ごとに違いがありますので、出す前にご近所さんと情報を共有したり、自治体の公式通知を確認する癖をつけましょう。分別は面倒だと感じる人もいますが、長期的にはゴミ処理コストの削減につながり、清潔な町を維持するための小さな行動です。こうした小さな工夫が、ゴミの山を減らし、自然環境の保全にも寄与します。
ぜひ、今週から実践してみてください。
友達A: ミックスペーパーって結局何を入れるの?いつも混乱するんだけど。 B: 基本は新聞・雑誌・カタログ・紙袋・薄紙の紙箱みたいな、紙でできていて汚れていない紙だよ。ただし油分がついた紙やホチキス跡のある紙、コーティングされた紙は対象外になりがち。自治体ごとにルールが違うから出す前に地域の案内を必ずチェック。僕の家では出す前に紙を乾燥させ、表面の汚れを拭き取ってから束ねるだけで、リサイクルの質がぐっと高まると感じてる。分別のコツは、紙以外の異物を混ぜないことと、紙の山をきちんと整えること。たとえばパンフレットの透明フィルムは剥がす、粘着テープは剥がす、紙の大きさがばらつかないようにする、これだけで回収車の作業もスムーズになるんだ。
前の記事: « ゴミ収集車の色の違いとは?地域ごとのルールと安全性を徹底解説





















