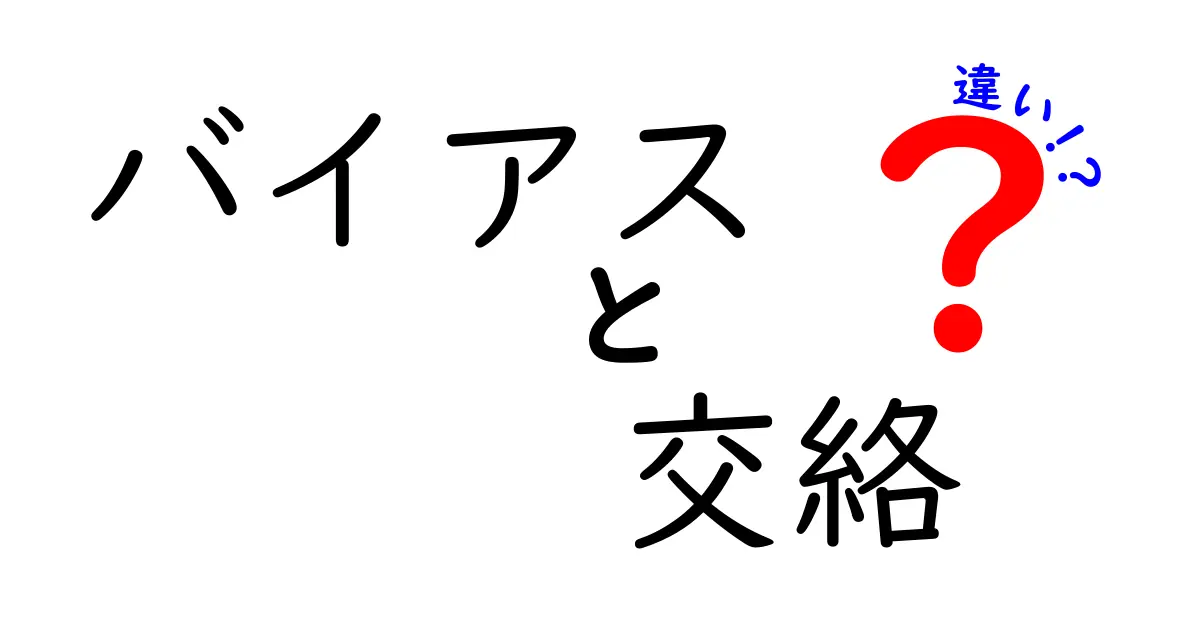

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:バイアスと交絡の違いを正しく知ろう
この話を始める前に、"バイアス"と"交絡"という二つの言葉を別々に覚える理由を伝えます。バイアスはデータそのものの偏りを指し、測定方法・選択・観察の仕方にいつも潜んでいます。例えばアンケートで「はい」と答える人だけを集めると、結果が全体の姿を正しく映さなくなることがあります。こうした偏りは、私たちが何を測るか、どこで測るか、誰に答えさせるかといった決定の向きによって自然に生まれます。
一方、交絡は因果関係を見誤らせる“影”のようなものです。原因Aと結果Bの間に、本当は関係があるとは思えない別の変数Cが絡んでいると、AとBの間に因果関係があるように見えてしまいます。Cが影響を及ぼしているのに、それを見逃すと、結論が間違ってしまいます。これら二つは似ていますが、発生の場所と読み解き方が違うのです。
基本のポイントを整理する
この章の要点は三つです。第一にバイアスはデータの“偏り”そのもの。測定器の精度、回答の取り方、集め方の選択などが原因になります。第二に交絡は“隠れた因子”が関係を見かけ上変えること。第三に、違いを正しく理解するには、データの取り方と分析の設計を別々に考えることが大切です。こうした考え方を身につけると、結果を読む力がぐんと上がります。
身近な例で整理するバイアスと交絡の違い
現実の例を使って理解しましょう。たとえば、夏休みの宿題と成績の関係を調べるとします。宿題を多くこなす人は成績が良いように見えるかもしれませんが、ここには交絡の可能性があります。家での勉強時間が長い、塾に通っている、先生のサポートを受けている、といった別の要因が同時に成績に影響している場合が多いのです。こうした要因を無視すると、「宿題の量=成績」という因果関係を誤って結論づけることになります。
このような状況を正しく分析するコツは、まず観察の枠を広げ、複数の変数を同時に扱うことです。次に、仮説を複数立て、それぞれを比較していくと交絡の影響を分解しやすくなります。以下の表は、バイアスと交絡と違いのポイントを一目で見比べるためのものです。
ねえ、データの話しててさ、バイアスって何だろうって友だちに聞かれたんだ。僕は「バイアスはデータの“偏り”そのものだよ。集め方が偏ってると、結論も偏っちゃう」と答えた。友だちは「じゃあどうやって偏りを減らすの?」って。そこで僕は「いろんな視点でデータを集める練習をして、仮説を何個も並べて比較すること」と提案した。小さな実験をくり返して、どの条件が結果に影響するかを一つずつ確かめる。
前の記事: « コホート研究 横断研究 違い





















